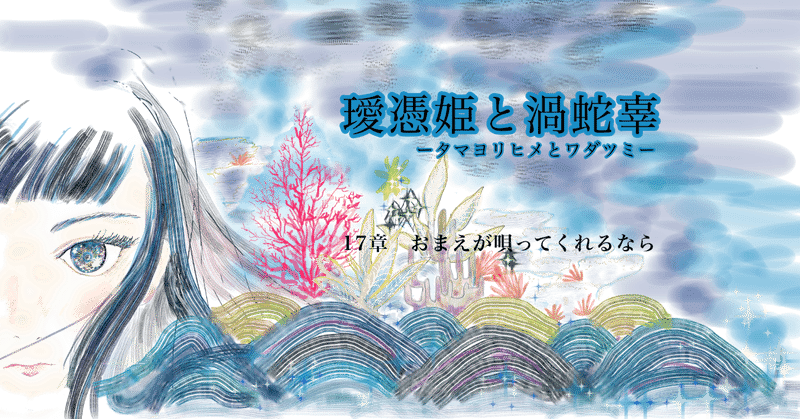
璦憑姫と渦蛇辜 17章「おまえが唄ってくれるなら」②
砂の上にぴくりともせず横たわっている妹を見ながら海彦は思案した。
「地べたで寝るは風邪の元ってお婆さがよく云っとったでな」
キョロキョロと首を動かすが見えているのかいないのか、いずれにせよタマヨリを寝かせて置くような場所はない。
「うううむ」
と唸ってうろつきはじめると、背後から大挙して上陸する魚類に驚きふらついて、足元にある『いさら』を踏みつけた。
今にも影にーーー巨大な魚影の中に『いさら』が吸い込まれそうになっているのに気づき、何を思うよりも先に飛びついて影から引き離した。すると魚影は砂に溶けるように消えてしまった。
「これはあれか?タマの子安貝か?」
その大きさに対してまるで重みを感じさせない剣を、撫でたり嗅いだりして、
「大きくなったなぁ」
と感嘆の声をもらした。そして『いさら』をひょいと腰紐の間に差し込むと、タマヨリを抱きかかえてまたうろうろしはじめた。
そこにひときわ嵩ました海水の魚が現れた。ゆったりとその巨体の腹を浜に投げ出し、流れる川となった魚たちの群れの上にずるずると乗ったのは白長須鯨だった。
迫る巨大な水の魚に海彦は感じ入ったように立ち止まって、くんくんと鼻腔を広げた。ふと思いついて鯨の脇腹に足をかけると、水の体は程よく反発し沈むことなく登れる。うまくいったのをこれ幸いと、そのままぽちゃんと水音をあげながら脇腹を登りはじめた。タマヨリを抱えたままでもすいすいと脚は動き、登りきった鯨の背を見渡すと、
「ここならええか」
と納得した顔になった。ちょうど鯨の目の上あたりで、胡座をかいてタマヨリを膝の上に寝かせた。
鯨はふたりが乗っても素知らぬ風でばしゅんばしゅんと水をかいて進む。
せっかちな魚が鯨の中を流れて先へ先へと泳いでいく。
鯨に追いつかれた死者も鯨と混じりあい、しばらくするとその腹から抜け出し、また人の形になって歩き出す。
まことに怪奇な光景だった。
体を持たぬ死んだもの達が海水の体を得て我が物顔で陸を行く。人も魚類も境目がなくなり、混じっては別れ混じっては別れ、互いが互いの体を泳ぎ進む。
おおよそ彼らがどんな心持ちでいるかは、外からは窺い知れない。しかし自由闊達なようで何者かの意思によって統率されているようにも見え、奇異でありながら天然自然の不可思議のひとつのようでもある。
「いやあ、ここは風があって良いなあ」
と鯨の背で海彦は満悦していた。
死者の行軍のしんがりのほど近くに位置し、鞍はなくとも高々と大魚の背に揺られる様はいかにも総軍の大将格といった感じだ。
眠り続けるタマヨリに傅く死者達はひたすら行進を続ける。
土地の高い低いも関係ないが、山に辿りつけば谷に沿って進んだ。
高見の見物に悦に入っていた海彦の背に迫る者があった。死者達の背を渡ってきた波の獣が、大口を開けて鯨の尾に喰らいついた。獣の背には抜き身の『波濤』を携えたワダツミが乗っている。
「止まれ!」
食いつかれてもびくともしなかった鯨は、その号令に巨体の動きを止めた。鯨だけでなく、その号令は賽果座の全ての死者に伝播し、その歩みを止めたのだ。
波の獣は鯨の背で水に戻り、そこから飛び降りたワダツミは迷いない足取りでタマヨリに近づいた。
「あれえ?タマがふたりおるでねえか」
海彦が首を傾げながら、ワダツミに向けて鼻をもたげた。
「おかしいぞ。こっちもタマじゃが、あっちもタマの匂いがする」
海彦は膝で眠るタマを見て、背後から来るタマらしき者を見たが、その目は生前と同じに見えているとは言い難かった。
ワダツミは海彦には目もくれず、眠るタマヨリに近づいた。
「おい、起きろ。お前はいつも余計なことばかりしてくれる」
そう云って『波濤』の柄で海彦の膝から小突き落とした。
海彦は驚いて立ち上がったが、タマヨリが転げ落ちた先は柔らかくぼよぼよとした水面である。まだ昏睡の中にあるタマヨリはそのままに、ワダツミの顔を仰ぎ見た。
鼻の穴を大きく広げ、海彦はこのもうひとりのタマヨリから何かを嗅ぎ取ろうとしていた。それから立ち上がり、両腕をワダツミの背にまわしそのまま抱きしめたのだ。
思いもしない行いにワダツミは微動だにしなかった。
「タマ、おまえずっと寂しかったんじゃな」
そう云って海彦は自分よりも大きな男の背中を、そろそろと撫ではじめたのだ。
「ずーっとずっと、なんだかタマがさみしげじゃと思っとったが。あっちとこっちに分かれてしまったんなら、そりゃあ心細かろう………」
海彦はそっとそっと背をさすった。
ワダツミは我に返ったように体を引き、そのまま『波濤』で海彦を切ってしまった。
海水の体はふたつに分かれてしまったが、流れて崩れ去る前にまた海彦の形に戻った。犬が水を飛ばすようにぷるぷると体から余計に滴った水を飛ばすと、のっそりとワダツミの前に立ち尽くした。
「タマよぉ、分からねえか、おまえの兄ぃさじゃ。なんてことないさぁ、なんてことないさぁ」
全ての死人と同じように切ったところでどうしようもないのは、ワダツミにも分かっていた。しかし腰にどういうわけか『いさら』を下げているのは無視できない。
「死人の言葉は分からん。名乗ることを許す」
と云えば、海彦の口は生者の言葉を話しだした。
「おらはさぁ、海彦さぁ」
海彦は生真面目に答えた。
「なぜ『いさら』を持っている」と聞けば、
「そりゃあおまえの大事なものだからさぁ」と答える。
「なんでそれを大事と知っておる」
「タマのことは島の誰よりよおく知っとるからな」
「おまえは誰だ」
「海彦じゃ」
「何者だ」
「おらか?おらは漁師だ」
「漁師だと?どこの………痴れ者だ」
訥々と話す海彦とのやり取りに痺をきらしたワダツミはやり方を変えた。死人の心の内を水鏡のように鯨の体を使って、そこに映し出そうとしたのだ。
「え?どこなんかのう………」
すると海彦が心に浮かべた風景が、鯨の背面いっぱいに広がった。
狂おしいほどの夕焼けが天蓋をおおった。海彦とワダツミは鯨の中に沈んでいた。左右上下を水に囲まれ、そこに四方の情景が映り込んだ。
日暮れの海にいらさ波が立ち浅い海の面を駆ける。振り向けば白い砂浜があり、デイゴの花が燃えるように赤々と咲き誇るその下に、質素な漁師小屋が一軒だけ建っていた。
低い山を囲むように茂る熱帯の木々は、今、藍色の影にのまれようとしている。
影と共に甘い花の香が濃くなり、いよいよ夕焼けは浜を桃色に染めるほど燃え上がった。
水底に目を移せば色とりどりの魚が珊瑚の間を泳ぎまわり、時折り海面でぴしゃりと跳ねて銀に光った。
「ああ、あの島か」とワダツミは呟いた。
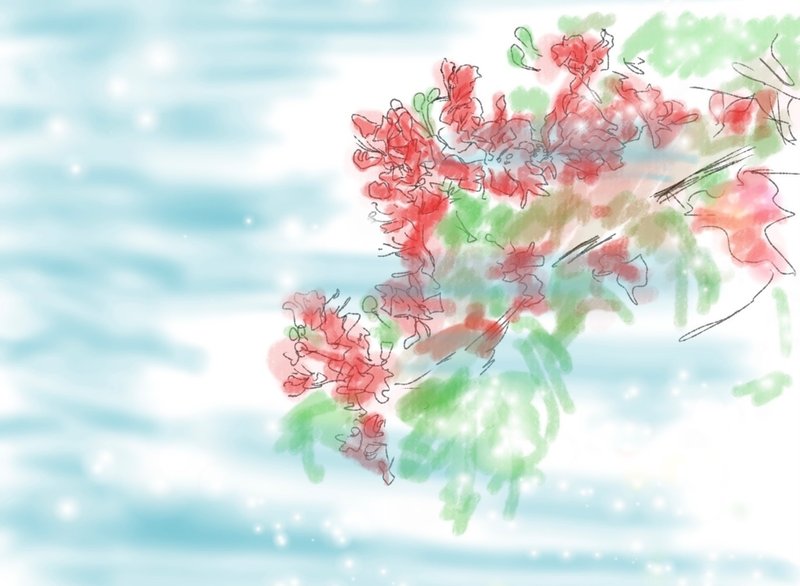
「タマ、何しとる?」
と聞いたのは死人の海彦ではなく、鯨の中の海彦で歳の頃は十二かそこらだった。
「兄ぃさ!」
舌っ足らずな声をあげて幼いタマヨリが振り返った。むちむちした白い指の間には、タマの子安貝が握られている。それは瑠璃色の小さな貝殻片だった。
「タマね、見してるの」
「ほう」
「タマね、海の向こうのお母しゃとお父しゃに、これ見せてる」
「ああ貝殻見せとったのかぁ?」
「うん。タマ、これ持ってるから、タマのとこ来てくれるよ」
「ああ、それ持ってたらなぁ。会えるからなぁ」
「会えるの」
ふたりは浜に並んで立って、タマがお椀の形にした手の中の貝殻片を見つめていた。海の向こうにいる親が、形見に気がついて迎えに来てくれるとふたりは信じているのだ。
「タマ、さみいしいんか」
暮れていく空を仰ぎ見て海彦は云った。
「さみしくないよ。タマ、兄ぃさとお婆さと一緒じゃ」
「ああ」
「……お母しゃとお父しゃがえんえんじゃ」
「えんえん云うとるんか?」
「うん。海がえんえんするの。タマ、どこだーって。海から声がするの」
「さみしいのはお母さとお父さのほうじゃな」
と云うと海彦は、石を拾って海に投げた。とんとんとんと3回波を切って石は沈んだ。
わあ!とタマヨリが歓声をあげると、海彦は大きな口を開けて夕日に向かって叫んだ。
「タマはここにおるぞ!もう泣くな!さみしくないぞー!」
それを聞いて小さなタマヨリは頼しそうに目を輝かせた。
海彦はまた大きく息を吸うと、
「そんでもさみしかったら帰ってこーい!ここに帰ってこーい!」
と喉を乾さんばかりの声で叫んだ。
その声に呼応するように島の景色は一変し、右も左も水で覆われそこに『竜宮』が現れた。
島の珊瑚は水府の珊瑚と混ざり、どちらがどちらなのか分け隔てがなくなった。その艶やかな珊瑚林の向こうに美しい都が広がっていた。
とこしえの都は神が手ずから創った万象にいだかれ、地上の夕焼けを映して紅く照り映えていた。白砂の果てで、陽炎のように水の中に揺らめいていた。
ワダツミは思わず手を伸ばした。
夕暮の色は一層濃くなって、その赤さは見る間に増して血の色となった。視界を覆うように赤色は広がり、都の姿を隠した。
走ろうとすれば足元は脆く崩れ去った。死んだ珊瑚と人魚の骨が累々と積み重なり、ワダツミが歩くことを拒んでいた。
進むほど崩れる地面と、頭上を染める鮮血。『竜宮』の景色は暗い海の彼方に溶け混じり消えていく。
焦りと苛立ちとも、諦めとつかぬ心持ちでワダツミは『波濤』を揮った。
赤色が割けて、その向こうには海彦が立っていた。死人の海彦だ。
「帰ってこい」
と海彦は云った。
「まだ云うか、漁師風情が」
ワダツミは再び『波濤』を向け、今度は切り刻んだ。
「うおおおおおいい」
とおかしな声をあげて海彦の水の体はぐるぐるとワダツミのまわりを回ったが、今度は人の形には戻らずに鯨の中に溶けた。溶けて鯨と境目のなくなった大きな水の塊となってワダツミを包んだ。
たゆんたゆんと海彦は揺籠のように揺れ、水流となって鯨を巡り、また流れ寄っては抱きしめた。
そうするうちに先程は聞こえなかった死者の言葉が、小さな音の粒となって再生する。それは小さな泡粒のようにささやかで儚い音だった。
「おまえずっと寂しかったんじゃな」
ふつふつと生まれ水の泡のようにワダツミを包む言葉は儚かったが、はじけた端から美しい水の記憶を呼び覚ました。
それは『竜宮』だった。それは南の小島だった。同時にふたつの場所であった。
風景は重なり合い溶け合いながら、ワダツミの望郷の想いを貫いてそこに縛りつけた。
「故郷はそんなに遠いんか」
海彦の魂が水の言葉でたずねる。
「………ああ、遠い」
とワダツミは応える。
「遠ければ迷ってしまうなぁ」
水になった海彦は睡るタマヨリを運んできた。その手をワダツミの手に重ねると、
「帰るまでは離しちゃいかんぞ」
とその手を上からぎゅっと握った。そうやってひとつの魂の片割れ同士を繋ぎ合わせて、それで安心とばかりにもう何も話さなくなった。そして鯨の中で海彦は仄白く光る魂となった。光はタマヨリとワダツミの周りをゆらゆら揺蕩いながら巡った。
「………ん」
とタマヨリの口から声が漏れた。
「…………兄ぃさ、そこにおるんか?」
ゆっくりとタマヨリが目を覚ますと、あたりを包んでいた鯨から魂が抜けた。すると水の鯨は形を失い、その場に流れ出した。
「あっ」
体に急に重さが戻り、地面に引き寄せられるのを感じたが地に落ちることはなかった。ワダツミの腕の中にいたのだ。
消える鯨とともに海彦の魂も消え、他の死者達も魂は海へ、体は水へと戻っていった。死者の行軍はこれにて退散したのだ。後には大きな川と夜空が残された。
続く
読んでくれてありがとうございます。
