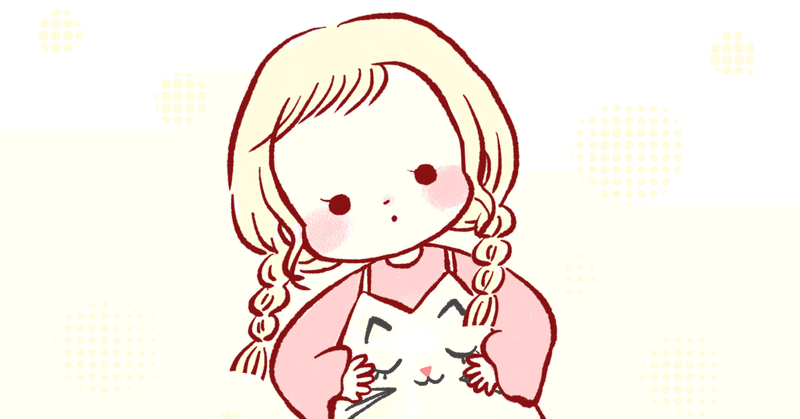
生きてることって、私がいることって不思議。
生きてることって、私がいることって不思議だと常々思います。
まずは、もし「私」がいなかったら...?
という哲学的な思考実験を載せさせてください。
1.我々の世界には意識体験がある。
「意識」「クオリア」「経験」「感覚」など様々な名前で呼ばれるものが、「ある」という主張である。ここは基本的に素朴な主張である。
2.物理的には我々の世界と同一でありながら、我々の世界の意識に関する肯定的な事実が成り立たない、論理的に可能な世界が存在する。
現在の物理学では、意識・クオリア・経験・感覚を全く欠いた世界が想像可能であることを主張する。この哲学的ゾンビだけがいる世界を、ゾンビワールドと言う。
3.したがって意識に関する事実は、物理的事実とはまた別の、われわれの世界に関する更なる事実である。
ゾンビワールドに欠けているが、私達の現実世界には、意識・クオリア・経験・感覚が備わっているという事実がある。それは、現在の物理法則には含まれていない。
4.ゆえに唯物論は偽である。
以上の点から現在の物理法則・物理量ですべての説明ができるという考えは間違っている。
哲学的ゾンビ(てつがくてきゾンビ、英語: Philosophical zombie、略: p-zombie)とは、心の哲学で使われる言葉である。「物理的化学的電気的反応としては、普通の人間と全く同じであるが、意識(クオリア)を全く持っていない人間」と定義されている。
デイヴィッド・チャーマーズが1990年代にクオリアの説明に用いた思考実験であり心の哲学者たちの間で有名になった。
・・・
仮に“哲学的ゾンビが存在する”として、哲学的ゾンビとどれだけ長年付き添っても、普通の人間と区別することは誰にも出来ない。それは、普通の人間と全く同じように、笑いもするし、怒りもするし、熱心に哲学の議論をしさえする。物理的化学的電気的反応としては、普通の人間とまったく同じであり区別できない。
しかし普通の人間と哲学的ゾンビの唯一の違いは、哲学的ゾンビにはその際に「楽しさ」の意識も、「怒り」の意識も、議論の厄介さに対する「苛々する」という意識も持つことがなく、“意識(クオリア)”というものが全くない、という点である。哲学的ゾンビにとっては、それらは物理的化学的電気的反応の集合体でしかない。
哲学的ゾンビは、私たちの持っている不思議な感覚、意識を持っていないと仮定した存在のこと。
精神科医の益田さんが、人の心は脳の現象であり、内部刺激(DNAと記憶・経験)× 外部刺激(現在の状況や環境)を通して現れる現象だと言っていました。私もそうだと思っていて、身体内部と外部環境との相互作用によって、私たちの意識・感覚ができていると思います。
でも、不思議だとは思いませんか?
脳の中で私たちが「自分自身を自分だと認識」したり、「目の前にある水を飲みたい」と思ったり、「リンゴが赤い」と感じたりする。
今だって、私の目の前には最愛のインコちゃんがいますが、無邪気にたくさんおしゃべりしてるこの子を見たら、愛おしくて仕方ない感覚を持ちます。小さな生き物が近くにいてくれて、本当に可愛らしくて、手を差し出したら乗っかってきてくれて、見つめたら見つめ返してくれるんです。
こんなに幸せな気持ちを感じられる、こんなにありがたいことはないんですが、いつも不思議に感じるんです。
上部に引用した、哲学的ゾンビの話を見て頂けたでしょうか。
私たちの体は、大体が物理的に説明できるはずです。細胞がこんなふうになっていて、電気信号でシナプスの情報伝達が行なわれて、化学反応が絶えず起こっていて、DNAの配列はこんな構造で、というようにして。
しかしながら、心はどこから生まれているのでしょう?というか、どこにあるんでしょうか?
お腹が減ったと思っているとき、お腹が減ったと思っているのは誰なんでしょうか?「私」に違いないんですが、「私」ってなんでしょうか?
水とタンパク質と・・・色々合わさって人間ができて、
その人間がなんとなく動いていたら、この世界を、自分の目を通して見ることができて、耳で聞いて、匂いを嗅いで、味を感じて、触れてテクスチャを感じる。
五感を通して手に入れた材料を料理して、頭の中で思考を結晶化する。
意図を動作として現して、行動をこの世界に与える。
これは、「これをしよう!」と「私」が意図して、実際に身体を動かしたりして活動することを指すんですが、このとき、私たちの頭には自由意志のような感覚が芽生えます。自分で何かを考えて、行動して、というふうに「私」が活動しているんです。
なんとも不思議なことです。だって、こんなふうに認識主体としての「私」がいて、世界を感じて、自分を感じています。
いったい、「私」ってどこにいて、どこからこの感覚を得ているんでしょうか?
脳と身体全体が活動して、外部知覚をし、内部からの刺激も受け取り、「私」は身体の機能の中で意思決定を下して行動したり、感情を持ったり、思考をしたりする。そして、脳に「私」という主体の意識が生み出されるのかもしれませんが、
本当に不思議だと思うんです。生きてること、「私」がいるということ。
自分ってどこにいるのかな?と思いませんか?
頭部と脳、内臓、四肢、胴体、骨、血管、肉・・・
物質的に私たちの身体があるわけですが、その化学的・物理的な反応と統合で「私」という意識が生み出されているって、凄いですよね。
心身二元論とか、身体と精神を同一とみなすものとか、色々ありますが、いずれにせよこんな私たちの〈感覚〉が生じている事自体がすごく不思議なんです。
この不思議さを、先人たちは神で説明したり、自然法則のみがあるとか言ったりしたわけですが、その不思議さを追求しても、答えには至らないと思います。生の、心の理由が神にあるのか、自然法則にあるのか、どこまで考えてもわかりませんけれども、
でも、ただ実感として、日々の活動と感覚を通して、私たちはこの不思議さの中で、色んな体験をすることができます。
いつもはあまり景色とかは注目していないけど、夕方にふと空を見上げてみたら、思いがけない、綺麗な色をした夕日が目に映って、心が動いたり。
たまに小さな幸せを発見できるのは、心のおかげ。私たちの身体が活動できて、色々な感覚を得ることができるおかげ。
では、私たちは生活世界とどのように向き合っていけばいいのでしょうか?
サルトルとフランクルについて引用します。
人間は自分の本質を自ら創りあげることができるということは、例えば、自分がどのようにありたいのか、またどのようにあるべきかを思い描き、目標や未来像を描いて実現に向けて行動する「自由」を持っていることになる。ここでのサルトルのいう自由とは、自らが思い至って行った行動のすべてにおいて、人類全体をも巻き込むものであり、自分自身に全責任が跳ね返ってくることを覚悟しなければならないものである。このようなあり方における実存が自由であり、対自として「人間は自由という刑に処せられている(人間は自由であるように呪われている(condamné à être libre))」というのである。
とはいえ、人間は自分で選択したわけでもないのに、気づいたときにはすでに、常に状況に拘束されている。他人から何ものかとして見られることは、わたしを一つの存在として凝固させ、他者のまなざしは、わたしを対自から即自存在に変じさせる。「地獄とは他人である(l'enfer, c'est les autres)」。そのうえ、死においては、すでにかけ離されたものであって、もはや切り札は残されていない。わたしを対自から永久に即自存在へと変じさせる死は、私の実存の永遠の他有化であり、回復不能の疎外であるといわれる。
しかしながら、これを常に状況によって自分が外から拘束されているとみなすべきではない。自由な対自としてのかぎりでの人間は、現にあるところの確実なものを抵当<gage>に入れて、いまだあらぬところの不確実なものに自己を賭ける<gager>ことができる。つまり、自己が主体的に状況内の存在に関わり、内側から引き受けなおすことができる。このようにして現にある状況から自己を開放し、あらたな状況のうちに自己を拘束することはアンガージュマン<engagement>といわれる。
ロゴセラピーは、ジークムント・フロイトの「精神分析」やアルフレッド・アドラーの「個人心理学」と並び、心理療法のウィーン学派三大潮流のひとつとして挙げられることもあるものである。
「ロゴ」は、ギリシア語で「意味」の意である。ロゴセラピーは、人は実存的に自らの生の意味を追い求めており、その人生の意味が充たされないということが、メンタルな障害や心の病に関係してくる、という見解を基にしている。(心的な疾患は、当事者に人生の意味に関して非常に限定的な制約を課していると言える。)ロゴセラピーは、人にその生活状況の中で「生きる意味」を充実させることが出来るように、あるいはその価値の評価の仕方を変えることが出来るように援助しようとするものである。
そのためロゴセラピーは手法として、実存主義的アプローチをとり、下記の3点を基本仮説とする。
意志の自由 - 人間は様々な条件、状況の中で自らの意志で態度を決める自由を持っている。(決定論の否定)
意味への意志 - 人間は生きる意味を強く求める。
人生の意味 - それぞれの人間の人生には独自の意味が存在している。
フランクルは、人の主要な関心事は快楽を探すことでも苦痛を軽減することでもなく、「人生の意味を見出すこと」であるとする。人生の意味を見出している人間は苦しみにも耐えることができるのである。
⸺人生の意味こそが幸せ?
人には、身体活動の中で、コントロールできるものと、コントロールできないものがあります。
まず、今目の前にある外部環境をどう知覚するかということは変えられません。雨が降っているのに、晴れているように見えるなんていうことはありません。視覚や聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの五感を通した外部知覚、また人は身体内部においても現在の体の状況などを内部の感覚として感じ取っています。
次に、そのような外部環境への知覚から、感情が生まれるときはそれをコントロールできません。怒っている人を見て、自分の気持ちも暗くなってしまう、というように反射的に出てきた感情はコントロールできません。
次に、今ある習慣が慣性的に行なわれることや、例えば熱湯が手にかかって手を引っ込めるような「反射」は、あまりコントロールできません。意識が介在できない、無意識が強く影響する領域です。あとは身体の生命維持活動なども無意識的に行なわれています。
では、コントロールできる部分はなんでしょうか?
一つは行動。もう一つは思考です。
行動は、意図と運動で成り立ちます。自分がこの行動をするという選択をして、そこから体を動かす、例えば本を読むとか誰かに話しかけるとか。
思考は、例えば今日の晩ごはん何食べようか考えたり、過去の思い出に浸ったり、勉強したことについて考えたり、どうやって現状を良くしようか考えたり、目の前の景色や状況を見てそのことについてよく考えてみたり。
行動と思考に、感情が随伴的に生じたりもするわけですが、今まで確認してきた、このような外部環境への知覚や習慣・反射・生命維持・行動・思考など様々な身体活動を通して、その全ての活動に伴って何らかの身体感覚を人は感じています。
好きな人に振られて悲しいという一連の感覚だったり
家族モノの名作ドラマを見て感動している感覚だったり
雨音を聞いて心が落ち着いたり落ち着かなかったりする感覚だったり
冬でとても寒い中、やっと温かい家に帰ってきた気持ちだったり
緊張してお腹が痛い中で頑張って前に出てスピーチする感覚だったり
友達と一緒にドライブに行って美味しいものを食べた感覚だったり
昔やらかしたことを思い出して辛くなったり
おもむろに絵を描いていたら夢中になって時間を忘れたり
家に帰る途中で中華飯店からの匂いがしてお腹が減ったり
ペットが言うこと聞かなくて少し怒鳴っちゃって後から後悔したり
そんな主観的な体験、個別具体的な活動の中で、人は幸せだったり幸せじゃなかったりする感覚を感じています。
自分が何に意味を感じて、何に幸福な感覚を覚えるのか
生きて活動していく中で、生活の中で、だんだんと自分のことを知っていって、だんだんと色んな感覚を記憶に刻んでいく
その感覚を大事にしながら、ちょっとずつ自分にとっての幸せを覚えていって、「私」という不思議で魅力的な意識を楽しんでいけたらいいのかなと考えています。
全てが、人生の意味を発見していく過程なんです。
長い記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
ぜひ、他の記事や YouTube なども訪れてみてくださいね!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
