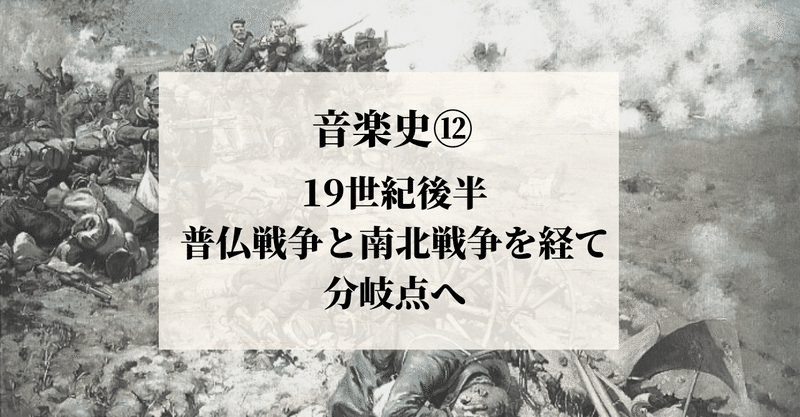
#17 音楽史⑫ 【19世紀後半】 普仏戦争と南北戦争を経て分岐点へ
クラシック音楽史からポピュラー音楽史までを並行でつなげる試みです。このシリーズはこちらにまとめてありますので是非フォローしてください。
前回は、ヨーロッパ各地で革命が起こって社会の潮流が変化した1848年以降を紹介しました。パリやウィーンでは、ワルツ・ポルカ・カドリーユなどの流行のダンス音楽のほか、オペラを親しみやすくした「オペレッタ」が発生し、“軽音楽”として人気となりました。そのころアメリカでは、娯楽としてミンストレルショーが発達したほか、ギルモアによって吹奏楽・軍楽も発達し、1861~65の南北戦争でもブラスバンドが鳴り響きました。イギリスではミュージックホールが発生し、上流社会の文化とは違った労働者階級の娯楽空間が発展していく土壌が生まれます。一方、ドイツでは特有の美学をアイデンティティーとした「真面目な音楽(純音楽)=クラシック」を下地として、ワーグナー派の革新的な総合芸術・和声拡張傾向と、ブラームス派の純粋芸術的な方向性とのあいだで論争が起こりました。
今回は1870年頃からです。ちなみに日本では1868年に明治維新が起こっています。ここで、それまでの日本の伝統音楽文化が断ち切られ、西洋音楽の流入が起こります。このシリーズでは日本音楽史は一旦扱わず、いつかまた別途で調べてまとめていきたいと考えていますが、ひとまずこの時代に日本に入ってきた「西洋音楽」の実態が、この地点でのこのような状況だった、ということを把握するだけで、認識の解像度が上がるような気がします。
また、今回は、通常は同時には語られることのない「クラシック音楽史のクライマックス」と「ポピュラー音楽のプロローグ」が同時代現象としてついに本格的に重なり合う時期になってくるので、内容としては一番雑多になってしまうと思います。しかし、この同時代現象をしっかりと並列として認識することがこのシリーズの目標であり、音楽ジャンルの分断の疑問を晴らすカギになると僕は考えているので、頑張ってまとめたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。
普墺戦争と普仏戦争により、ドイツ地域ついに統一へ
まず世界史的な情勢を確認してみます。これまで何度も書いてきたとおり、ドイツ地域は長らくまとまりのない諸邦乱立の後進地域でした。しかし、19世紀には北からプロイセンが力をつけていきます。“鉄血宰相” ビスマルクが軍拡を進めたことで有名ですね。
ゲルマン民族のナショナリズムが煽られ、ドイツ地域統一の機運が高まる中、1866年にプロイセンとオーストリアの間で普墺戦争が起き、プロイセン軍が勝利。プロイセンがドイツ統一の中心勢力となります。ハプスブルク家が治めるオーストリアを含む南ドイツの諸邦はカトリックが多く、プロイセンはまずプロテスタントの多い北ドイツをまとめあげました。
そして、隣国に強大な統一国家の出現を恐れるフランスとのあいだで、1870~71にプロイセン・フランス戦争(普仏戦争)が勃発します。
それまでのヨーロッパの大国だったフランスに対し、なんとプロイセンが圧勝し、衝撃を与えます。ついに南ドイツも含めた「ドイツ帝国」を成立させ、念願のドイツ地域統一がなされます。フランスに対しては、多額の賠償金のほか、ドイツ帝国の皇帝戴冠式をヴェルサイユ宮殿で行うという屈辱までフランスに与え、フランスはドイツに対し不満と復讐心を抱くようになります。
また、ハプスブルク家(オーストリア)はのけものにされて、ドイツからはずされてしまいました。異民族で今まで支配していたハンガリーにも自治を認めることとなり、ここに「オーストリア=ハンガリー帝国」という二重帝国(1人の王のもと、2つの自治)が誕生します。
普仏戦争のプロイセンの勝利によりヨーロッパのパワーバランスは変わり、そのインパクトはここから第一次世界大戦までの約40年間の世界の軍事思想に影響していきました。明治維新を果たした日本もプロイセン軍を参考にして国家づくりを進め、国民皆兵制を採用しています。
ドイツ音楽の論争のその後
ようやく軍事的にも文化的にも念願の影響力を獲得したドイツ。そんな19世紀後半のドイツ音楽の流れは、引き続きワーグナー vs ブラームスを中心に語られます。
1872年、ワーグナーはバイロイトへ移住。念願だった自分の劇場を建築開始。1876年に「バイロイト祝祭劇場」が完成しました。この劇場で、自身の作品だけを上演するために「バイロイト音楽祭」を開始(現代まで続いています)。ここでたった一曲だけ演奏されることの認められたワーグナー以外の作品が、ベートーヴェンの第九なのです。第九は、第四楽章のみに合唱が入り、統一性に難がある代わりにメッセージ性や革新性が強い作品で、ワーグナーはベートーヴェンのこういった面に影響を受けています。
一方、ブラームスも1876年に交響曲第一番を完成させます。20代の初めに構想したというこの作品は完成するまでに20年以上かかり、ブラームスは43歳になっていました。それは、ベートーヴェンという巨大な壁があったからだといわれています。ブラームスは、ベートーヴェンの「交響曲第五番(運命)」を模範としていたようです。第五は、第一楽章冒頭から提示される有名な「ダダダ・ダーン」という音型によって楽曲全体が構成されています。緊密に構成された統一世界。ブラームスはベートーヴェンのこういった面に影響を受けています。
「ベートーヴェンの交響曲に並ぶものを書き残さなければならない」というプレッシャーの甲斐あって、ブラームスの交響曲第一番は、ベートーヴェンの交響曲の系譜を正統的に受け継いだ名作として聴衆に受け入れられました。ハンス・フォン・ビューローはこの作品を「ベートーヴェンの第10交響曲だ!」と絶賛しました。
ワーグナーやリストは、楽劇や交響詩といった新しい表現を開拓しており、交響曲は古い形式だと考えて、交響曲を作曲することはほとんどありませんでした。そこで、交響曲に名高いブラームスに対抗する、ワーグナー派の交響曲作曲家として担ぎだされたのがブルックナー(1824~1896)です。ただ、ブルックナーは政治的思考は疎く、対立に首を突っ込むつもりはなかったとされます。しかし、ワーグナーを尊敬していたがために、ハンスリックの酷評・罵倒の標的となってしまいました。批判されると自信を無くし、すぐ書き改めるブルックナーは「改作魔」として知られ、同じ作品にさまざまな版が存在しています。
ブルックナーの作品の特徴は
・45~80分かかるほど長大で大規模。
・弦楽器のトレモロから始まる「ブルックナー開始」、オーケストラ全体によるユニゾンが展開される「ブルックナー・ユニゾン」、曲調の変化時に長い休止を多用する「ブルックナー休止」などのパターン化
このような特徴の、無骨で巨大なスケールの交響曲を作曲し続けました。
ハンス・フォン・ビューローは、ブラームスの売り出し文句として
「バッハ、ベートーヴェン、ブラームスがドイツ3Bだ!」と評しました。
(このキャッチフレーズが現在まで広く残り、何故か日本の音楽の授業でもこの売り出し文句が真面目に教えられています。)これに対しワーグナーは「ドイツ3Bはバッハ、ベートーヴェン、ブルックナー」を提案していたそうです。
その後ブラームスは、1877年に第二番、1883年に第三番、1885年に第四番を発表し、いずれも好評価となります。1897年に息を引き取るまで、標題音楽や舞台音楽には最後まで手を出しませんでした。
一方、音楽家の枠を超えて多大な影響を与え、「ワグネリアン」と呼ばれる宗教的崇拝者まで生んだワーグナーは、1883年に死亡。祝祭劇場は妻コジマが運営を続け、今でも音楽祭に行くことを「バイロイト詣で」と称するなど、聖地となっています。さらに、ワーグナーの音楽はこの後ナチスドイツのテーマソングにもなっていきます・・・。
さて、ここで構図をもう一度整理すると、
ブラームス陣営(ハンスリック、ハンス・フォン・ビューロー)
=絶対音楽(メンデルスゾーン、シューマンを引き継ぐ純粋芸術)
ワーグナー陣営(リスト、ブルックナー、ブレンデル)
=標題音楽(ベルリオーズを引き継ぐ総合芸術)
※どちらも前提としてベートーヴェンの存在があった。
こうなりますが、この背景にドイツ的音楽観として「演奏会が教育としての存在意義もあり、聴衆には教養が求められる」という思想があった点が重要です。(そのまま現在のクラシック音楽の演奏会に引き継がれていますね。)これにより、バッハ~ベートーヴェンを経て自分たちに至るドイツ中心的な歴史観を強固なものにしていったのです。
ここでブラームスが「保守」、ワーグナーが「革新」と位置付けられたため、革新派が用いた半音階的手法、「トリスタン和音」に代表されるような調性拡大傾向がその後の「芸術音楽」の歴史観の方向性を決めることになります。ベートーヴェンに端を発する進歩主義的な考え方は、同時代のヘーゲル哲学の弁証法や、ダーウィンの進化論ともリンクする歴史観だといえます。
ドイツ音楽だけを軸にとったバロックから古典派~ロマン派への流れを、和声・形式が一方向に拡張されていくようになぞらえて体系化したために、「わかりやすいものは古い。新しいものはより複雑でなければならない」という物差しが音楽界に敷かれてしまいました。現在、西洋音楽史が語られる語り口は皆、このストーリーに沿っています。現在のクラシック音楽の批評・解説も基本的にすべてこの前提のもとで展開されています。この時代ドイツでは医学、心理学、社会学など他の学問もたくさん発達し、先述した戦争にも勝利して影響力も増していたため、同じようにドイツ的な音楽美学も「普遍的な音楽の学問の前提」として定着し、現在まで君臨してしまったのです。
しかし、このシリーズの初期に書いた通り、ジャズやロック、ヒップホップやポップスなどまで視野にいれると、人類全体の音楽史というものは、必ずしもそのような音楽理論的な一方向のストーリーではないことはすぐにわかるはずです。僕がクラシック音楽史を学んだ時に腑に落ちない点はここでした。音楽の正統な学問が19世紀ドイツ人の美学にいつまでも沿っている限り、クラシック音楽とそれ以外の分断は深まるばかりではないでしょうか。この一連の音楽史記事は、このような音楽史観からの脱却を試みて書いていますが、理解していただけているでしょうか・・・? ただ、この主張が説得力を持つのは物語が本格的にポピュラー音楽史へとシフトしてからだと思っているので、根気強く地道に書いていこうと思います。
フランス音楽の変化
さて、パリではここまで、貴族のサロンコンサート文化や、オペレッタの発生など、比較的、娯楽音楽の性格を持っていました。当時のフランス人やイタリア人から見ても、ドイツ音楽は小難しいものでした。「宗教や哲学」に比肩するような「深さ」「内面性」が求められるドイツ音楽は「真面目な音楽」と呼ばれていました。イタリアオペラやワルツは当時の「ポピュラー音楽」で、現在の「娯楽音楽 vs 芸術音楽」の対立のルーツともいえます。
ところが、普仏戦争でフランスがプロイセンに負けたことにより、フランスにも「真面目な音楽」の伝統をつくろう!という動きが発生します。敗戦のショックによる文化ナショナリズムの発生です。
フランク(1822~1890)を中心として、サン・サーンス(1835~1921)らとともに、1871年 「フランス国民音楽協会」が設立されます。協会への入会資格がフランス国籍を持つものに限定されているなど、ナショナリズムの色が強いものでした。ここでは他にシャブリエ(1841~1894)やフォーレ(1845~1924)が活躍しました。
こうして、それまでフランスにはなかった交響曲や弦楽四重奏曲などが多く作られるようになり、ドイツ音楽の美学に追従した形でフランスの「真面目な音楽」の礎が生まれることとなりました。
一方で、オペレッタなどの「大衆娯楽」は引き続きヨーロッパのブルジョワ市民に流行していましたし、さらにこのころからパリでは、上流階級の閉じられた「サロン」から、「カフェー」や「キャバレー」などへと、新しい溜まり場が広がっていった時期でもあり、これが芸術家や文化人たちの情報交換や新しい流行の発信源となっていくのでした。こういった部分には既にクラシックではなく20世紀のフランスのポピュラーミュージック「シャンソン」の系譜につながる予兆としてもとらえることができます。
「国民楽派」という視線
19世紀、「近代国家」という概念が浸透し、「国」の意味は単なる貴族の支配版図から国民国家へと変質し、住民たちの帰属意識として「民族国家」が意識され始めました。特に東欧など、国家の政治的独立が脅かされる状況にあった地域ほど、この傾向は強調されました。これまで、ポーランド出身のショパンなどをはじめとした地方出身者は活動の場を求めてパリなどへ上京していましたが、1860年代以降、ヨーロッパ各地方に、祖国の国民意識を重視した作品を生み出す作曲家があらわれはじめます。これらは国民主義音楽と呼ばれ、作曲家は国民楽派と称されました。代表的な作曲家を簡単にまとめます。
【ロシア】
〈ロシア5人組〉
ボロディン(1833~1887)
キュイ(1835~1918)
バラキレフ(1837~1910)
ムゾルグスキー(1839~1881)
リムスキー=コルサコフ(1844~1908)
〈モスクワ〉
チャイコフスキー(1840~1893)
【チェコ(ボヘミア)】
スメタナ(1824~1884)
ドヴォルザーク(1841~1904)
【ノルウェー】
グリーグ(1843~1907)
この時代、ナショナリズムはヨーロッパ全体に渦巻いていました。しかし、ドイツやフランスの音楽は民族主義的とは言われず、それ以外の地域の音楽家が「国民楽派」として「民族主義的な音楽」と括られたのです。ここに、「中心地」ドイツから「辺境」の地方への視点があらわれています。
そもそもドイツ音楽もドイツの文化ナショナリズムの表出だったはずなのですが、ドイツ国民は「音楽民族」としてのアイデンティティを獲得し、その「美学」をもとに音楽の価値を学問的に追及していくのち、それがヨーロッパ全体の音楽の普遍的な基準へと成り上がらせてしまったのです。
ドイツ、イタリア、フランス。この3国が普遍的な音楽を発展させていく「スタンダード」であり、周辺国に「民族的」な芸術音楽があらわれはじめた。そういう位置づけがなされたのでした。
クラシックを学んでいると、この視線を疑うことなく受け入れてしまいますが、クラシック音楽の学問的な美学の前提には常にドイツ人の視点がある、ということを意識して、一度相対化してみることも大切だと思います。
「クラシック」と「ポピュラー」
こうして、音楽文化的にも軍事的にもドイツの権威がヨーロッパ全体に確立され、フランス音楽も「真面目化」し、追従する形で東欧諸国の国民主義音楽も位置付けられた、という流れの中で、逆に「理解しやすく、民衆向き」という条件が「ポピュラー音楽」の定義として強調されていったと考えられます。そこからあぶれると「クラシック」の仲間入りになっていったのです。
もともと「クラシック」とは「古典」という意味のはずでした。しかし、「真面目な音楽」の芸術文化が学問的に浸透していくうち、「新しくてもむずかしい」ものも「クラシック音楽」とされていくようになりました。さらにもちろん「新旧」という意味も含んでいたため、「少し前までポピュラーだったけど流行が去った」ものも「クラシック音楽」の仲間入りをしていったのです。
こうして、ロッシーニやヴェルディなどのイタリアオペラや、ショパンなどのサロン音楽、オッフェンバックらのオペレッタなど、19世紀ヨーロッパの作品がすべて「クラシック」のカテゴリーに吸収されていくことになったのでした。
そしてそれらが「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー」という、音楽理論の進歩主義的なドイツ美学の歴史観のストーリーに当てはめられ、西洋音楽史の視点が決定していきます。一方で、その美学と関係のない、イギリスやアメリカでの娯楽空間や労働歌、ラテンアメリカでの民衆音楽など、「ポピュラー音楽」「ポピュラー文化」が誕生していきつつありました。
イギリス・ミュージックホールの展開
1852年にイギリスに誕生したミュージックホールという施設ですが、枠組みとしてはパブなどから更新されたものの、しばらくのあいだ、音楽内容としてはそれ以前のパブと変わらないものでした(芸人によるバラッドなど)。チャールズ・モートンの目論見としては家族路線を目指していたものの、実態はまだまだパブ的な場として機能しており、お客さんも芸を酒の肴としか見ていませんでした。ですが、1870年代になると、ミュージックホール用の歌をつくる専門家が登場します。スター・システムが登場し、「売るため、売れるための曲作り」がなされるようになります。つまり、商業性を帯びた流行歌の量産がはじまったのです。歌のテーマとして「労働者の夢物語」「都会をスマートにエンジョイする洒落者(ライオン)を気取る歌」が労働者をターゲットに成功し、「ライオン・コミックス」と呼ばれました。
しかし、この時期に前後して普及していった鉄道旅行やスポーツ観戦など、中産階級のブルジョワジーらの文化では、酒から切り離して健全に楽しむことが模範とされていた中、酒を煽り立ててアドリブやアンコールがとめどなく続くミュージックホールの音楽文化はまだまだ悪印象でした。そこで、中産階級の新しい客層を招き入れるべく、レスペクタビリティ(健全化)の追求がなされていきます。それに伴って流行したのが、“愛国的ソング”でした。
19世紀の世界はイギリスの覇権でしたが、19世紀後半になるにつれて徐々に揺らぎ始め、各国は「帝国主義」による植民地の相互防衛連合作りがはじまっていきます。1853~56のクリミア戦争、1877の露土戦争などでイギリスはロシアに対して畏怖のイメージが強まり、中産階級の間で特に反ロシア感情が高まっていました。中産階級以上の人々は文字が読め、メディアによって政治の話題を吸収していましたが、労働者階級にとってはミュージックホールの場で政治の話題を共有していたようです。そういった場で、音楽を通じて「大英帝国愛」を高揚させていったのです。
1877年、G・W・ハント作曲による「マクダーモットの戦争の歌」が大ヒットします。曲中の「バイ・ジンゴ!」の掛け声がキャッチフレーズとなり、10年以上のロングヒットとなります。この掛け声にもともと意味はなかったのですが、1880年代の政治ソングの流行と結びつけられ、「愛国主義=ジンゴイズム」「愛国歌=ジンゴ・ソング」と呼ばれるようになります。もっとも、ミュージックホールの客に政治の難しいことが理解できていたわけではなく(そんなことはどうでもよく)、ただ単に植民地と本国イギリスとの「絆」が強調され、ロマンを感じていたのが実態だったようです。その無責任さは当然、アカデミズムからは批判されていますが、ともあれ、こうしてライオンコミックスの猥雑さがなくなり、健全化が進んでいきました。
このころ、社会階層自体にも変化がおきていました。まず、産業革命の進行にともない、1870年代以降、労働者階級の生活水準が上昇していったのです。(同時に、貧困や極貧層は残されましたが。)大半の労働者が、それまで上流階級の口にしか入らなかった砂糖やタバコまでを消費できるようになりました。余暇時間の増大にともない、何をしようか「選べる」時代になったとき、ミュージックホールは「選ばれた」のです。同時に、中産階級の人々も、それまでの「働くことが善、娯楽は悪」という考え方から「遊ぶことは罪悪ではない」という方向へシフトしていき、それまで教会などで行われていたネガティブキャンペーンも緩められて、牧師自ら「ミュージックホールや劇場に行こう」と説教する時代になります。中産階級上層部以上は主に、シェイクスピアなどの正当な劇場へ行く「劇場派」といえるのに対し、中産階級下層部と、労働者階級の上層部(いわゆる「労働貴族」)が「ミュージックホール派」と分類できる客層になってきます。このようにして、ミュージックホールは巨大娯楽産業に発展していきました。
アメリカ・南北戦争後の奴隷解放につれて
1861~65年の南北戦争はアメリカの経済戦争でした。南部は黒人奴隷をおもな労働力として綿花のプランテーション農業を営んでいたのに対し、北部は工業化の時代に入っており、利害の対立から5年近くにわたる戦争につながったのです。結果、北部の連邦軍が勝利し、南部の奴隷は解放されることになりました。しかし、奴隷解放は、新たな人種差別を生むことにもなります。奴隷解放後、そのまま労働力として雇われなおされてこき使われたり、教育されぬまま社会の荒波に放り出され、また「アフリカ」も遠い過去となってしまっていた黒人たちは疎外感の中にありました。農園時代に「フィールド・ハラー(野の叫び)」として歌われていた労働歌は戦争後も歌われていき、やがてギター(和声)が取り入れられ、「ブルース」として発達していきました。特にミシシッピ州のデルタ地帯で発達していったこの初期ブルースは、デルタ・ブルースと呼ばれています。
辛い悲しみを詠嘆に近い形で歌われたフィールド・ハラーやブルースに対し、讃美歌の流れをもつスピリチュアルズ(黒人霊歌)は救いを求める性格を持っていました。南北戦争後の1866年、解放奴隷や若いアフリカ系アメリカ人に対して教育を施す目的でテネシー州ナッシュビルにフィスク大学が設立されます。しかし、創立5年で深刻な財政危機に陥りました。そこで、9人の生徒が集められ、フィスク・ジュビリー・シンガーズというアカペラ・グループが結成されました。この活動により、スピリチュアルズが洗練化されていき、のちのブラック・ゴスペルの源流となっていきます。
吹奏楽の展開
ギルモアが主導して発展させていったブラスバンドの奏でるマーチ(行進曲)は、ヨーロッパとアメリカの両地域で人気でした。前回書いた通り、ブラスバンドのコンテストは各地で開催されていおり、1867年にパリで開かれた各国の軍楽隊コンテストには、フランス、プロイセン、オーストリア、ロシア、スペイン、ベルギー、バーデン、オランダ、バヴァリアが参加し、審査員にはクラシック音楽論壇の中心人物だったハンス・フォン・ビューローやハンスリックも参加していました。
南北戦争後、アメリカではギルモアの次の世代としてジョン・フィリップ・スーザ(1854~1932)が発展させていきます。海兵隊バンドの隊員から産まれたスーザは、1880年、26歳で同バンドの指揮者となり、同バンドを一流のバンドに仕立て上げました。
スーザの功績は以下の3つです。
①レパートリーの充実。
大量の楽譜をヨーロッパから取り寄せ、当時の大作曲家、ワーグナー、チャイコフスキー、グリーグらの作品を取り上げて演奏し、技術向上に貢献した。
②数々のマーチを作曲。
現在にまでのこる行進曲の名曲を次々に作曲し、レパートリーに加えた。
(「星条旗よ永遠なれ」など)
③編成の改革
現在の吹奏楽の標準的な編成をつくりあげた。
南北戦争が終わり、開拓に打ち込んでいた時代。サーカスの人気などにみられるように、人々はさらなる娯楽を求めていました。そこでスーザは、展覧会、博覧会、フェスティバル、地方の催しなどにバンドの需要を見出し、有料コンサートを開いて商業化を進めていきました。
このような功績により、スーザは「マーチの王」と呼ばれています。
ミンストレルショーとケーク・ウォーク
さて、白人達が黒塗りによって黒人性を消費する形で楽しんだ差別的なショー、ミンストレルショーですが、もともとフォスターらがミンストレルズのために生んだ黒人の憂いや苦さも含んだ歌が、南北戦争頃に歌だけが独立して広まるにつれ、歌詞が変えられてアフリカン・アメリカン色が無くなることで、白人中心の国民唱歌へと吸収されていっていました。中流階級の自宅の居間で口ずさまれるような家庭向きの歌として、「パーラー・ソング」と呼ばれました。イングランド・スコットランド民謡からの影響もあると言われています。
一方でショー自体は戦争の頃には構成が定型化していき、三部構成が普通になります。
①ミンストレル・ライン
(導入のジョーク、歌、ダンス)
②オリオ
(動物真似・マジック・漫才・曲芸や雑芸)
③アフターピース
(1幕ものの音楽劇)
1870年代までは初期の精神が継続する形で人気のピークを保っていましたが、80年代を過ぎると、他の大型ショーが台頭してきます。あわせてミンストレルショーも内容が自由になっていきました。このころ、ニューヨークのブロードウェイに劇場が増加していきます。もともとニューヨークでは19世紀を通じて、イギリスの正統な正規劇や、ヨーロッパのオペラやオペレッタの導入、ミンストレルショーやサーカスショーまでさまざまなショーが提供されていましたが、特に南北戦争後になり、ユニオン・スクエアが劇場街の中心となり、ここから北へ北へと広がっていきます。最初にニューヨークの街灯がガス灯から電気に変える試みが始まったのが1880年です。中心街は格段に明るくなり、世紀末までで一気に数が増大するようすは、国民が娯楽に生活を割くゆとりが広がっていったことを物語っているともいえます。
ところで、ミンストレルショーの中で、景品のケーキを目指して競争させられる黒人たちのようすを茶化した「ケークウォーク」というダンスが流行っていましたが、その音楽としてマーチやポルカ風の軽快な2拍子の音楽にイギリス民謡系のフィドル音楽が黒人風のシンコペーションで組み合わさって表現されていました。
この部分が独立してピアノで演奏されることで、ラグタイムの誕生につながっていきます。南部の黒人たちはピアノを演奏する時に、左手ではマーチに起因する2拍子の伴奏を奏でながら、右手では独特のシンコペーションのリズムを多用するという演奏スタイルを編み出しました。これが従来のクラシック音楽のリズムとは違う「ずれた」リズムと見られ、ずれた時間「ragged-time」略して「ragtime」となったと言われています(諸説あり)。
クレオールとニューオーリンズ・ジャズ
ニューオーリンズという街は15世紀から200年ほどスペインの領地で、その後は17世紀にフランスが統治し、奴隷制度が始まりましたが、フランス国内の女刑囚や売春婦もニューオーリンズに送り込まれ、混血が進んでいきます。黒人とスペイン・フランス系の白人との混血者はクレオールと呼ばれました。クレオールは当初、白人と同等の扱いを受け、音楽教育も含めてヨーロッパスタイルの教育を受けていました。
1803年、ナポレオンがルイジアナをアメリカに売却。アメリカの法と奴隷制が施行されたのち、1861~1865の南北戦争を経て奴隷解放となります。
ここで、人種基準も北部の論理に従うことになり、「一滴でも黒人の血が混じっていれば黒人とみなす」という基準により、今まで恵まれた生活をしていたクレオールの人たちは一転して地位が転落してしまいます。黒人エリート階級は崩壊し、職を奪われたり生活基盤を失う者も多く出ました。こうした中で、音楽の教養のあるクレオール人は、黒人ブラスバンドの教師役を務めたり、キャバレーの演奏者となって日銭を稼いだりしました。こうして、アフリカ系の音楽や歌に、クレオールたちが身に着けた西洋音楽の要素が自然に溶け込んでいったと言われています。アメリカ全土ではフォスターのパーラー・ソングやスーザのマーチが大人気の時代です。
南北戦争の終戦を機に、南軍の音楽隊は次々に解散していき、それまで使われていた楽器が市場に大量に放出されることになります。安価で流通し始めた楽器を手にし、見よう見まねで覚えた黒人たちが、やがて独自の音楽を奏でることになっていきますが、クレオールは黒人たちにヨーロッパ音楽の橋渡しをした形となります。譜面通りに演奏する白人ミュージシャンと違い、黒人たちは耳と頭で覚えたものをフィーリングで演奏しました。ヨーロッパ系のマーチやカドリーユ、ワルツやポルカなどに、黒人音楽のフィーリングを加えたり、ブルースやラグタイムの要素も加味されていき、ジャズの誕生となっていきます。
黒人ブラスバンドが上達するにつれ、白人達から「おもしろい」「パレードでやってくれ」と相手にされるようになります。スーザやフォスターなど、世の中全般が音楽を必要としていて、多くの楽団が必要とされていた時代、ニューオーリンズでの暑さは異常で、葬儀や埋葬時の演奏、酒場や売春宿での演奏、街頭での呼び込み演奏、冠婚葬祭のパレード演奏など、白人にとって好ましくない条件でも、奴隷経験のある黒人たちにとっては十分活動できました。ニューオーリンズ特有の文化として、埋葬が終わると「聖者の行進」のように陽気な音楽でパレードをしました。天国に召されることこそ、現世の苦しみから解放される唯一の道という奴隷時代からの意識の表れでもあり、お祭り好きのラテン系の風習でもあるといえます。このようなパレードはセカンド・ラインといいます。
こうして誕生した初期のジャズがニューオーリンズ・ジャズと呼ばれます。
新たな伝達メディアの登場
1870年代まで、音楽の伝達方法としては、口承か楽譜かのどちらかでした。主に楽譜自体が作品として重要視されたのがクラシック音楽であり、それ以外の、主に口承で伝えられる音楽が民俗音楽とされます。しかし、1870年代に、第3の伝達方法が登場します。「音そのもの」が残されるようになったのです。
アメリカの発明家トーマス・エジソンは1877年、「フォノグラフ」という蓄音機を発明します。当時はまだ電気を使わない「アコースティック録音」であり、振動を直接原盤に伝達して刻み込む録音方式です。ラッパに直接音を吹き込む「ラッパ録音」とも呼ばれ、音質は貧弱でしたが、それでも音楽史上大きな転換点となります。これをきっかけとして、人々の音楽の接し方や「作品」の概念が変わっていくことになり、「ポピュラー音楽」がはっきりと「クラシック」から分化して発展していくことになるのです。
はじめて録音されたのはエジソンの歌う「メリーさんの羊」であるというのは有名です。その後いくつかの録音が行われましたが、1889年にエジソンはブラームスに依頼し、ピアノ演奏を録音します。これが史上初のプロの演奏の録音だとされています。
エジソンのフォノグラフは円筒形でした。それに対し、1887年、ベルリナーが円盤型の「グラモフォン」を発明します。こちらがレコードの基礎となり、発達していきました。
ラテン音楽史のはじまり
ラテン民族とはもともとスペイン語、ポルトガル語、フランス語などを話す人々をさしていました。古代ローマで話されていた言語がラテン語であり、そこから発達したのがスペイン語やフランス語なのです。古代ローマは巨大なラテン文化圏でした。15~16世紀の大航海時代、スペインやポルトガルが中南米に進出したことにより、中南米がラテン民族化します。19世紀初頭には中南米諸国が植民地からの独立を果たしましたが、その後も、サロン、劇場、ダンスホール、カフェなどのヨーロッパの都市文化は中南米都市へも伝わり、その音楽(ワルツ、ポルカ、マズルカなど)が流行していました。その影響下において、アフリカ音楽のリズムとの融合が進んでいくことにより、ラテン音楽が発達していきます。
まずは、キューバの首都・ハバナでハバネラという音楽が発生し、スペイン本国でも流行し、さらにスペイン経由でアルゼンチンにも伝えられ、1870年頃に流行していました。ハバネラは正確にはスペイン語読みで「アバネラ」と発音し、「ハバナの舞曲」のことを言います。ハバナの社交界から始まった優雅なダンス・リズムで、ヨーロッパから伝わった舞曲がハバナスタイルに形を変えて「ダンサ・アバネラ」となり、これがふたたびヨーロッパにも逆輸入されたのでした。
ちなみに、「ハバネラ」のリズムは、ビゼーのオペラ『カルメン』の中の一曲にも取り入れられて有名なクラシック作品として残っていますね。『カルメン』の初演は1875年なので、時期的にも一致していますね。こういう部分からも、クラシックとポピュラーの接着点(分岐点)を見出すことができます。
このハバネラが発展し、アルゼンチンではさらにミロンガというジャンルが誕生します。19世紀後半のアルゼンチン音楽として流行したミロンガは、やがてアフリカ系民族音楽のカンドンベなどと融合し、タンゴの誕生につながります。
さて、キューバでは19世紀後半、オリエンテ地方にて、土着の音楽やスペイン音楽、トローバ(吟遊詩人の歌)などが融合してソンというジャンルが誕生します。これがのちにルンバやマンボなど、20世紀の多様なラテン・キューバン音楽に発展する、キューバの基幹音楽となります。
中南米で唯一、スペイン語圏ではなくポルトガル語圏であるブラジルでは、ヨーロッパ系移民が持ち込んだ当時流行のポルカが基本となり、1870年頃にリオの酒場でショーロという器楽音楽が確立されます。スペイン語圏とは一線を画すブラジル音楽はこのあとサンバに発展していきます。
このような黎明期のラテン音楽を聴いていただくと、意外にもクラシック音楽の要素も強く感じることができると思います。
こんにちのあらゆるポピュラー音楽の発生について「西洋音楽と黒人のリズムの融合」というフレーズで説明が為されることは非常に多いですが、その意味するところはこのような部分に着目することで理解しやすくなると思います。
まとめ
今回は本当に盛り沢山でしたね・・・。
まずドイツ音楽のトピックとして「ワーグナ vs ブラームス」を軸に紹介し、フランス音楽もドイツのように真面目化していき、東欧の音楽家たちの民族主義的音楽が国民楽派として位置づけられるようすを書きました。普仏戦争を経て、軍事的にも学問的にも文化的にもドイツの影響力が増し、ここでワーグナー派の和声拡張傾向によってバッハからベートーヴェン、ワーグナーに至るクラシック音楽史の軸が音楽理論の進歩史観的に定められ、現在に至るという点を指摘しました。
一方でイギリスではミュージックホールが発達していき、アメリカでは南北戦争を経て、黒人音楽と白人音楽が融合しながら、デルタブルース、スピリチュアルズ、マーチ(スーザ)、ミンストレルショーの音楽(フォスター)、ケーク・ウォークやラグタイム、ニューオーリンズジャズなどの発展を紹介しました。また、蓄音機の登場により、音楽の伝達方法や作品の概念が変質していくという音楽史上の転換点になりました。
また、白人音楽と黒人音楽の融合は中南米のラテンアメリカでも起こり、キューバから発生しヨーロッパまで波及したハバネラ、アルゼンチンでのミロンガ、キューバの基幹音楽となったソン、ブラジルのショーロなどが各ラテン音楽の源流として誕生しました。
こうして書くと、やはり同時代現象で切り取ると煩雑になってしまうのは否めず、各分野ごとに書かれたものしか資料が存在しないのも納得できます。しかし、こうやって同時代現象を一気に認識することで、やはり視点が違ってきますよね。今回はあらゆる分野でクラシックとポピュラーの分岐点が見えたと思います。
こうなってくると次回からも引き続き、この範囲の広さを同時間軸でまとめなおすという気の遠くなる作業になってきますが、是非、気長にお待ちいただいて、読んでいただけたみなさんに少しでも新たな気づきがあればとても幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)