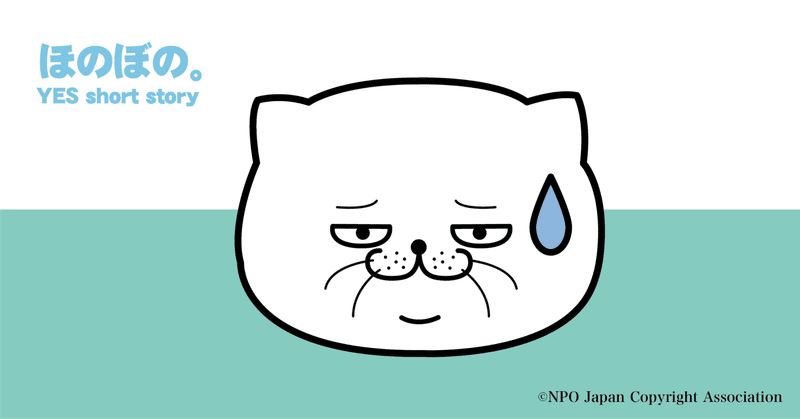
457.去る者は追かけてはいけないんだよ!だけどね、来るものは拒ばんじゃいけないよ!
(18)人生を好転させる方法
how to turn your life around⑱
1.人と出合い、去る人たち
私たちって、今までたくさんの人と別れてきたね。
それって、生まれたときから始まる。
幼稚園、小学校、中学校、高校や大学、そして社会。
たくさんの友だちやたくさんの好きになった人、かけがえのない人、父や母や家族と、別れ続けてきたね。
私たちって、
この世を去るまでに一体どのくらいの人と別れていくのかな?。
世界の人口は約73億人といわれている。
その中で自分と接点のある人はどのぐらいかな?
もちろん、何かの会合や、飲み会、コンサート会場や映画館での簡単な接点もあるけれど、挨拶する関係、友だちの友だち、わずかでも会話したり、初めての名刺交換、新しく友だちとなったり付き合いが始まる。
そう、考えると、仕事や生活の中で1日3人の人に出会うと想定してみる。
そして80歳まで生きたとしたら、
1日3(人)×365(日)×80(年)= 87,600人
となる。
つまり、80歳まで生きると延べ人数で換算すると一生で87,600人と出合うことになるんだ。
その中から1人を選んで結婚する。
親友を1人だけ選ぶ。
かけがえのない人を選ぶ、とすると、
0.00002283%の確率で相手を選んでいることになるという。
これって、驚くべき数字だよね。

でも、不思議なこともあるんだよ。
例えば25歳の人はこの計算方法でいえば27,375人と出合い、その半分が男性若しくは女性だとしたら13,688人の異性がいたはずなのに、それでも結婚していない人がいたり、付き合う人がいないと嘆いている人がいるということなんだ。
現在、50歳だとしたら、54,750人、その半分が男性若しくは女性だとしたら27,376人の異性がいて、現在独身又は好きな人がいないと嘆くのも不思議なもの。
あくまでも単純計算だから、13,688人~27,376人といったって、お爺さん、お婆さん、年上、年下の人もたくさんいるわけだから充てにはならない、と考える人もいると思うけれど、じゃあ、あなたが望んだ世代の数が1,000人だったら、100人だったらどうなのでしょう?
10人でも良い。
だから、ただ単純な数式ではなく、「人生の中の出会いの確率」だと考えれば良うんだ。
ここでみなさんに伝えたいことは、13,688人~27,376人の出会いがあった事実の中で、自分にとって「良い人」との出会いを見つけられなかった、という事実を知ることも必要かもしれないからさ。
さて、すべての人の平均が1日3人ではないと思うけれど、こんな比較も面白いよ~
1日3(人)×365(日)×80(年)= 87,600人
1日4(人)×365(日)×80(年)= 116,800人
1日5(人)×365(日)×80(年)= 146,000人
1日6(人)×365(日)×80(年)= 175,200人
1日7(人)×365(日)×80(年)= 204,400人
どうかな?物凄い数字だけれど、学校や会社、その他の数を入れたらこの何十倍になる可能性もあるような気がする。coucouさんは講演会やイベント集団を引き連れているので数字を出し切れない。もっと、凄い人たちは毎日数万、数百万人とすれ違う人々だっている。
(例として駅員さんや芸能人、イベント関係者、大企業、その他)
これらも縁なんだね、きっと。

2.逃がした魚は戻らない
私たちの人生の出会いをあくまでも一日3人との簡単な計算だけど、13,688人~27,376人の人たちと最低限出合い続けていることがわかるよね。
でもね、これを逆算して考えると、50歳~80歳までに13,688人~27,376人の別れがあるということになる気がする。
一度逃がした魚と同じ魚を手に入れることができない、といわれるように大海に放した魚ともう一度会うことは不可能に近いといえる。
このことを人は「去る者は追えず」、
「去る者は追わず」という諺になったかもしれないね。
ただ、出会いの数字の確率論にも驚くけれど、別れはさらに驚いてしまう。だって、こんなにも人は別れ続けているのだもの。
3.去るものを追ってはいけない
人は必ず、出会い、必ず別れがある。
これって、たとえ嫌だと言ったからと言って解決するものじゃあないよね。どっちにしても、誰もがこの世を去るのだから、必ず終わりがあるんだよね。
ともに仕事をしてきた仲間が去る。
会社を辞める。
長い間、友としてきた付き合いがなくなる。
大好きだった彼女と別れる。
離婚する。
あれだけ信頼し合い、心を許し合ったのに他の男性と一緒になった。
他の女性と一緒になった…。
あれだけ仲が良かったのに、あれだけ愛し合ったのに離れ離れとなった…。
別れたくないのに別れてしまう。
離れたくないのに、離れてしまう。
もう、二度とあのような時がないかもしれない…。
もう、二度と会えなくなる…。
追っても、追っても、離れていく。
追っても、追っても、逃げていく。
どんな形であっても、信頼関係があったり、好きな人と別れるのはつらく寂しいもの。だから、人には「未練」というものが残り「悔い」というもの「後悔」が残るのかもね。
でもね、去るものを追ってはいけないんだよ。
去る者は去りたくて去るわけなんだからね。
出合うのも「縁」ならば、
別れるのも「縁」、
結ばれることも「縁」、
離れることも「縁」だからさ。
だから、別れって、淡々とその人の幸せを願って見送ればいいような気がする。また、互いがなかなか離れられないという「腐れ縁」というものもあるよね。だけど、「腐れ縁」というと悪い言葉のように感じるけれど、「腐れ縁」って言葉はとても素敵な言葉のひとつなんだよ。
「出会う縁」「別れる縁」を超えたものが「腐れ縁」だからさ。
ずるずると続く腐れ縁。
それは腐っても互いが認め合っているという証かもしれないからね。
それに、「腐れ縁」って、嫌なら簡単に切ることができるものだからね。

4.来るものは拒まない
さて、別れる人の話ばかりだけれどで、50歳~80歳までに13,688人~27,376人の別れがあるということは、13,688人~27,376人以上の出会いもあるということがわかりますね。
縁というものには「新縁」という新しい出会いもあれば、
再び、もう一度の「再縁(復縁)」という縁もあるという。
去る者は去りたいから去るのであり、その人を尊重しなければならない気がする。強制で縁など戻るわけがないのだもの。
(coucouさんはね、若い頃、フラれるたびに追いかけたけれど、誰も戻ってくれなかった…。当たり前だよね~)
反面、「来るものの縁」というものがあるわけだから、そのことが「来るものは拒まず」というのかもしれないね。
去るのも自由ならば、出会うのも自由なわけなんだもの。
これは、ありがたい、大切な「ご縁」というもの。
このように縁とは自然なものですが、来るものも自然なありがたいご縁だということがわかる気がした。
去る者は追わない
don't chase those who leave
来るものは拒まない
don't refuse what comes
それでいいんだね。

5.13,688人~27,376人以上の出会い
13,688人~27,376人以上の出会い。
coucouさんはね、は家族や友人を含めてたくさんのお別れをし続けてきた。
でも、去ろうとする、離れようとする人を引き留めることはできないし、そんなことは無理だとわかるようになった。
その理由はね、相手が去りたいと思っているんだもの。
よく人って、
「それでも引き留めてほしい…」
「嘘でもいいから、いてほしい」
と言ってあげることも大切なことだ、という人もいるけれど、その言葉でその人の考え方が変わるなど、ほんのわずかなものだと思うんだ。
だから、あくまでも相手の意志、本人の考えを尊重してあげて、あとは未練を断ち切り、相手の幸せを願えば良いことだから。
寂しいとか、悲しいとか、辛いとか、酷いとか、は自分勝手な我儘に過ぎないよね。でもね、「来るもの」というものが必ずあるわけだし、来るという意味も、縁と言う意味もあるんだもんね。だから、それを最優先、大切にし続けることが本当の佳き縁なのかもしれない気がする。
私たちには誰にでも、最低13,688人~27,376人以上の出会いがあるのだものね。

coucouさんです~
みなさん~
ごきげんよう~
みんな、読んでくれてありがとう~
とっても、感謝しているんだよ~
また、あしたね~
Brenda Lee "All Alone Am I" on The Ed Sullivan Show
Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
