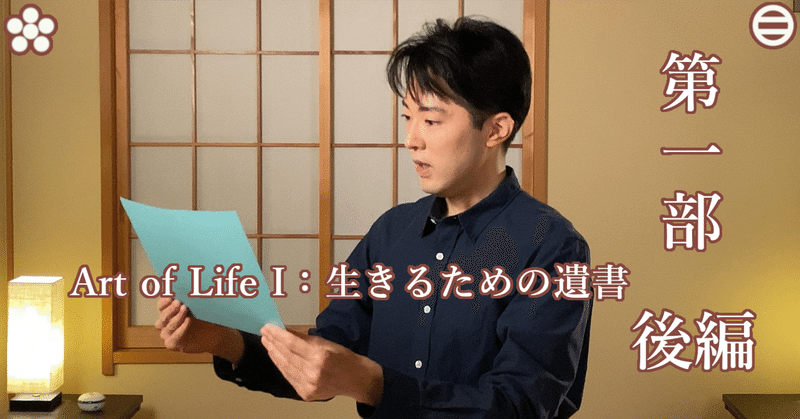
【文学作品】Art of Life I:生きるための遺書 第一部 後編
本稿は拙作『Art of Life I:生きるための遺書』第一部後編です。前編は以下の記事にてお読み頂けます。
第八章 天国のようなところ
祖父にとって唯一の同性の孫であった私は、祖母にとっては唯一の異性の孫だった。祖父と同様、祖母もまた孫たちを隔てなく愛してくれたが、自身で男の子を育てた経験のない祖母にとっては、私が示す表情や仕草の一つ一つが新鮮に感じられ、特に強く印象に残る部分はあったかもしれない。
私が小学校に上がるよりも前、祖母と二人で街に出かけ、店でハンバーガーだかフライドチキンだかを食べさせてもらったことがあった。建物の二階か三階の窓際の席に座ると、大きなガラス越しに外の景色が良く見えた。外食をさせてもらうというだけでも子供にとっては充分に心躍るものだが、賑やかな商店街を高いところから一望するという、それまでには経験したことのなかったようなその眺めは、幼い私にとりわけ鮮烈な印象を与えた。ちょうどその日は雨が降っていた。通りを行き交う人々が差している色とりどりの傘が、眼下に水玉模様となって動いていた。少年は大きく見開いた目を輝かせ、「天国みたいなところだね」という言葉で印象を表現した。家庭や学校といった目に見えない足枷によって、未だ致命的には心を害されていなかった当時の私には、自身の感動を天真爛漫な笑顔によって表すということが、自然にできたのだった。
私は本当に楽しく、嬉しかったのだと思う。このときのことは祖母の心にも強い印象を残した。私がとうに大人になり、教員として大学で授業を持つような身となってからもなお、祖母はこの思い出を話題にすることを好み、その都度幸せな表情を浮かべていた。
私が学校に通う年齢になった後、祖父母の家で、私にとっては母と二人の伯母にあたる三姉妹に、最近学校で困っていることなどを話すと、伯母たちは私を応援したいという気持ちから、それぞれに助言をしようとするのだが、身内の気楽さゆえ言葉は遠慮を欠いたものとなりがちで、座談がいつしか討論のようになってしまうこともあった。基本的にはそれぞれの情愛から、私はどうするべきか議論を戦わせる三姉妹の様子に、私が戸惑うような、少し困った表情を見せると、見かねた祖母が「私は創ちゃんの味方よ」と割って入り、その場を収めようとしてくれた。なりふりを構わない、あまりに真っ直ぐな祖母の振舞いにくすぐったさを感じながらも、私はそこに、世に愛と呼ばれるものの、最も素朴な発現を認めた。
反抗期と呼ばれるような時期に差し掛かると、祖母が可愛がってくれることに対してさえも、いつまでも子供扱いされることへの恥ずかしさが先に立ち、背伸びをした口調で愛想のない返答をしたこともあった。そんなときでさえ、笑みを絶やさないばかりか、それまで使わなかった言葉を使うようになったことにむしろ成長を感じて私を愛おしむ祖母の姿に、これは敵わないなと思ったものだった。
第九章 挙手の礼をもって
私が遊びに行くと、祖父はいつも莞爾として笑い、挙手の礼をもって迎えてくれた。徐々に足腰が弱り、杖を日常的に必要とするようになっても、やがてベッドから起き上がることさえほとんど出来なくなっても、その習慣は変わらなかった。敬礼の動作は変わらずきびきびとしていた。元来小柄で、手足などは特に細々としていた祖父だけれど、指の先まで神経の行き届いたその手つきは、子供心にとてもきれいだと感じていた。
私との対面をいつも心から喜んでくれた祖父母の笑顔は、共に決して忘れることはないが、殊に祖父のそれは、私にとり、自分が受け入れられていると感じることのできる、生まれ育った家庭においては一度として見たことのない、同性の表情だった。全身全霊で私を慈しんでくれる祖父の変わらぬ思いが、私を見つめるその瞳の輝きの内に宿っていた。不自由となってゆく肉体を超えて、直接心が伝わって来るようだった。
晩年、祖父は「これまで十分幸せだったから、自分がいつ死んでも悲しまないで欲しい」と、繰り返し周囲に伝えていた。それは祖父の偽らざる本心であったと思う。しかし、死への過程において、体が徐々に弱ってゆく辛さ、不自由が増えてゆく恐怖は、実際どれほどのものだったろうか。祖父が長い年月耐え続けたそうした心身の苦しみについて、自らにも関係するかもしれないものとして精一杯思いを致すことは、未だ私にはできていない。
祖父は最後まで、祖母以外には苦しみを見せることを好まなかったが、一度だけ私に、抱えきれない胸の内を明かすようなことがあった。自室のベッドから居間まで、何とか独力でその身を運んで来た祖父は、食卓の椅子に腰かけ、しみじみと私に話し始めた。加齢という現象がもたらす現実が、身体の様々な機能が否応なく衰えてゆく悲しみが、淡々と、切々と語られた。そして祖父は目をぎゅっと瞑り、一転して力強い口調で、「(それでも)俺たちは男なんだ」と、訴えかけるように、振り絞るように発した。それはまるで、動かし難いものをそれでも動かそうとするような、人間である限りそうせずにはいられないというような姿だった。
このとき祖父が「俺たち」という複数の一人称を用いて私に語りかけてくれたことの重みを、同性としての連帯を表してくれたことの幸福を、私がひしひしと感じることができるようになったのは、ようやく最近になってのことだった。それは、自身が男であるということを受け入れ、肯定する基となり得るような、私の生い立ちにおいてはほとんど唯一と言っても過言ではない体験だったのだ。
第十章 最期の言葉
自分が先に死んだら、祖母がやって来るまで待っている。かつて笑みを浮かべてそう話したこともあった祖父は、長い寝たきり生活の末、自宅で妻と三人の娘たちに看取られて亡くなった。訃報に接し、夜だったけれど都合がつく限りの親族が集まった。次々に駆けつける孫たちを、長年連れ添った夫を看取ったばかりの祖母が、変わらぬ柔和な表情で迎えてくれた。到着した者から順に、祖父にあいさつをした。祖母が呼びかけても、祖父はもう返事をしなかった。どれだけ見つめていても、体はぴくりとも動かなかった。まるで祖父の体の周りだけ時間が止まっているかのようだった。私にとり、初めて見る人間の亡骸だった。自然と涙が出た。
自分たちを心から愛してくれた人を亡くすという特別な情況において、妻、娘、孫という立場の違いを越えて、皆がある種の興奮を共有していた。悲しみに浸るゆとりは、様々の意味でまだなかった。エンバーミングや葬儀の手配といった目の前の実際的な問題には、一番上の伯母が中心となって対処してくれていた。私はできるだけ祖父の、そして祖母のそばにいようと思った。祖母は私に「亡くなる直前にはまるで四十代のときのような若々しい顔になったのよ」と話してくれた。その目には、真実を訴えかける光が宿っていた。「おじいちゃまはきっと、一番元気だったその姿で天国に行ったのだね」と、祖母の目を見て淀みなく、自信をもって答えることができたそのとき、私は人生において自分が果たすべき役目の一つを、細やかではあってもとても大切な役割の一つを、果たすことができたように感じた。その夜、祖母は一人文机に向かい、旅立った夫に宛てて手紙を認めた。
晩年の祖父は、かつての交通事故の影響もあり、寝ていても痛みで足を真っ直ぐ伸ばすことができなくなっていた。無理をすることなく足を曲げたまま入れるような棺を、葬儀社に頼んで特別に用意してもらうことになった。胸にこみ上げる気持ちを抑えきれぬという風に、「痛くないですか?」と思わず問うた祖母に対し、担当者は優しい口調で、「痛くないですよ」と静かに答えた。
葬儀において、祖父とは血の繋がりを持たない伯父が涙を滂沱として流し、代表のあいさつを行った。真率な思いは言葉を超えて心に伝わる。出棺前、あるだけの花を手向け、それぞれが祖父との最後の別れを惜しんだ。祖母と共に最後まで側で祖父を世話した伯母は涙ぐみ、「ここがずっと痛かったのよね」と言いながら、祖父の足を愛おしげにさすっていた。祖父の妻も子も孫も、皆泣いていた。それは決して悲しみだけを表すものではなかった。普段はそれぞれの人生、生活で手一杯とならざるを得ない親族が気持ちを同じくし、共に流すことのできた幸せな涙だった。祖父の最期の言葉は間違いなく、「ありがとう」であった。
祖父の葬送には、ある種の明るさ、清々しさがあった。いつかは経験しなければならない出来事に際し、力を合わせ、それを最も良い形で執り行うことができたという充実を皆が感じていた。そして、祖母がまだ元気で生きてくれているということが、皆にとって本当に大きな救いだった。身内の不幸によって、心情的にも実際的にも、残された者たちに負担がかかることを大変嫌っていた祖父は、自身がこのように送られたことをきっと喜んでいたと思う。
私個人の歴史においてもその頃には、不本意の極みであったけれど、それでもキャリアが、生きる世界があった。社会の中に自分の居場所があり、一定の人間関係があった。自分本来のものでは全くなかったけれど、それでも人間としての生活が、人生があった。その後、悲劇と言う他ない巡り合わせの連鎖によって私から奪われたすべてが、当時はまだあったのだった。
第十一章 星梅鉢と二つ引き
祖父の先祖は、清和源氏満快(みつよし)流大屋氏と伝わる。武士として代々朝廷に仕え、古くは保元の乱や承久の乱で武功があったとされる。京の室町に幕府が置かれた時代には、第六代将軍足利義教(よしのり)と、その子である義視(よしみ)に仕えた。
足利義視は第八代将軍義政の弟であり、将軍後継問題に端を発する応仁の乱の中心人物となった一人である。十年以上に渡り、京の都に徹底した破壊と混乱をもたらした戦乱は、山名宗全、細川勝元という東西両軍の実質的な大将が相次いで死去したこと、義政が息子の義尚(よしひさ)に将軍職を譲ったことなどを契機として両軍の和解が進み、ようやく終息に向かった。
義視は結局将軍となることはなかったが、それでも殺されることはなく、美濃に下向した。義視の家臣であった祖先も京を離れ、同じく清和源氏を称する尾張の豪族水野氏を頼った。この水野家は徳川家康の生母の里としても知られている。江戸時代には譜代大名となり、天保の改革で知られる水野忠邦をはじめ、幾人かの老中を出している。
鎌倉時代末期から戦国時代にかけて、祖父の一族は姓を主に長谷川と名乗り、「幸」という字を通字としていた。祖先の一人は、豊臣と徳川のいくさに際して秀頼に属し、夏の陣で討ち死にしている。大坂落城後、戦禍を生き延びた先祖の一人は近江国に移り住んだ。その姓を祖父も受け継いだものへと改め、時を同じくして、それまでの「幸」にかえて「永」という字を通字として用いるようになった。この一字は祖父の名にも引き継がれている。やがて一族は再び朝臣となり、徳川時代を通じて禁中仕官を続けた。
天保年間に生まれた高祖父は、和宮親子(かずのみやちかこ)内親王の降嫁や、孝明天皇の葬送などに際して供奉を仰せ付かった。満三十五歳で亡くなった孝明天皇に代わって即位した明治天皇により、慶應三年、王政復古の大号令が発せられた。これにより徳川幕府は廃止され、明治政府が新しく成立する。
しかし、形の上で廃止されたとはいえ、旧幕府を支持する勢力は依然として大きく、明治新政府の統治は決して確立されてはいなかった。やがて、これら新旧両勢力の対立に起因して戊辰戦争が始まる。改元を挟んで一年半に及んだ戦いに新政府軍が勝利を収めたことで、名実共に日本は明治政府によって統治されることが定まった。明治二年には東京への事実上の遷都が行われた。同年三月に天皇が東京に行幸し、以降江戸城を皇城とした。
王政復古当時、高祖父は出納所で書記をしていたと記録にある。明治改元の前後は会計官(後の大蔵省、現在の財務省の前身)に勤めていた。天皇に続き、明治二年十月に皇后が東京へ行啓した際には供奉を仰せ付かった。その後、高祖父は太政官制によって新しく設置された宮内省に属し、直丁(じきてい)や仕人(つこうど)などの職務に就いた。直丁は内舎人(うどねり)局の職員を指す。内舎人も仕人も、現在は宮内庁侍従職に分類され、いずれも皇族の身の回りの世話をする役目である。高祖父の仕事についても、そのように想像して良いのかもしれない。
新政府軍が戊辰戦争に勝利して後も、明治新政府に不満を抱く士族たちによる反乱は各地で続いていた。士族最後の反乱と呼ばれる西南戦争が終結する明治十年頃まで、日本社会は大きな変革に伴う混乱と不穏を経験していた。そのような時代にあって、同じ士族でありながら、高祖父が硝煙や血煙からは距離を置いていたこと、政治や経済という世俗の原理とは異なるものを重んじる生き方をしていたことに、私は自身の人間的本質の源流を見る思いがする。
やがて高祖父は自ら願い出て仕人を免ぜられた。その後、西陣織の一種である金襴の製造などを手掛けたこともあったが、結局は皇太后宮職としてかつてのような生き方に復している。時あたかも日清戦争の最中だった。
革命によって自らの政府を新しく作った、かつて地方の下級藩士だった人々が、自分たちが遮二無二推し進めて来た近代化路線、西洋化政策の正しさを示さんとばかりに、初めての対外戦争に血眼になる中、高祖父の赤誠は専ら、武とは関わりを持たず、近代というよりはむしろ前近代に属するような、一人の女性皇族に捧げられていたのだった。孝明天皇の女御であり、明治天皇の嫡母とされた、その英照皇太后が崩御すると、再び葬送の供奉を仰せつかった。
明治二十年代の半ば、高祖父が皇太后宮職を拝命する前の年、一族は東京に転居している。ほぼ一千年に渡って代々暮らしてきた京都の地を離れるというのは、決して気楽な決断ではなかったと思う。幕末維新の動乱による被害に加えて、東京へ事実上の遷都がなされたことにより、それまでずっと日本の都だった京都の町は、当時かなり荒廃し、疲弊していた。そのような現実的な背景は当然あっただろうが、代々帝にお仕えして来た一族として、東京にお移りになった天子様のおそばへ行きたいというような素朴な気持ちも、決して小さくはなかったのではないかという気がする。
高祖父と共に、当時はまだ少年だった曾祖父も、このとき一緒に東京に移り住んでいる。曾祖父については詳しいことがあまり分からないが、建築技師を生業とし、高祖父と同様、公に関する仕事を主にしていたようだ。明治三十年代に東宮御所御造営局に雇用されたというのが職歴の始めである。東宮とは後の大正天皇のことで、この建物は現在迎賓館として用いられている。
その後、明治政府は二度目の対外戦争となる日露戦争を始めた。この戦争には、後の時代に軍人として指導的役割を果たすことになる堀悌吉や山本五十六らが、兵学校を卒業したての少尉候補生として参戦していた。戦場というものの地獄を実際に味わったことは、二人の有為の若者がそれぞれに戦争観を形成する上で決定的な体験となった。ちょうど山本五十六と同年の生まれであった曾祖父も徴兵され、兵卒としてこの戦争に従軍した。あらゆる面で日清戦争とは比べることができないほど大きな負担を国民に強いた日露戦争だったが、幸いにして曽祖父は無事に生還を果たした。
明治が終わって大正の御代となり、祖父が生まれた。一族を通じて、東京生まれは祖父が初めてである。当時、高祖父は未だ健在だった。齢七十を超えて初めて授かった同性の孫に接して、どのような気持ちがしただろう。祖父が私にむけてくれたような眼差しを、高祖父もまた祖父に注いでいただろうか。
直接の親子という関係が、本質的にある種の緊張や反目の上に成り立つことを考えると、守られるべき大切なものはむしろ世代を飛び越えて受け継がれるのかもしれない。旧幕時代に生まれ、社会と共に日本人が大きく変質していった明治という時代を生き抜いた高祖父は、祖父の生誕を見届け、まるで魂のバトンを無事受け渡したことに安堵したかのように、その三年後に亡くなった。
続く
私に魅力をお感じ下さるそのお心を、もしサポートとしてもお伝え下さいましたなら大変幸せに存じます。体質上、生きるために私にはどうしても日々必要な、保険適用外の医療を含め、制作に充当させて頂きます。より美しい作品、演奏をご披露することで、頂戴したお気持ちにきっとお応え致します。
