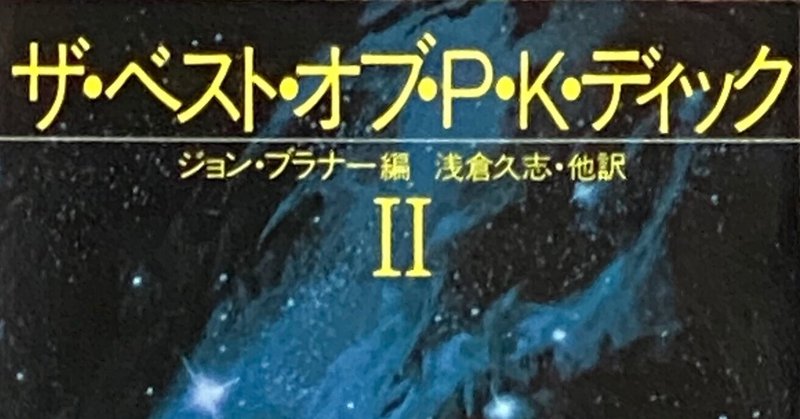
フィリップ・K・ディック の 「人間らしさ」について : ジョン・ブラナー編 『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック 〈2〉』
書評:ジョン・ブラナー編『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック〈2〉』(サンリオSF文庫)
「ヒューマニズム」とは「ヒューマン・イズム」、つまり「人間主義」のことである。
そして、「人間主義」とは「人間・中心主義」のことであり、この言葉が生み出される背景にあったのは、キリスト教世界における「神・中心主義」だ。
つまり、「神殺し」を行われた「近代」西欧において、初めて「人間」が世界の主役に躍り出た。
それまでの長らく、人間とは、神に仕えるべき存在、神の望むところに従って生きなければならない存在だったのだが、そんな「神」が存在しないというのを知って、人間は「人間中心主義」で良いし、それでやっていける、と考えるようになった。
西欧「近代」とは、人間が「神の桎梏」から逃れて独り立ちし、希望に溢れた第一歩を踏み出した時代だったのだと言えるだろう。

だが、こうした「近代ヒューマニズム」の希望は、第一次世界大戦の惨禍によって打ち砕かれた。
「神がいなくても、人間はやっていける」と信じていた「人間的な理想」が、第一次世界大戦における桁外れの「大量殺戮」という現実の前に、もろくも砕け散ったのだ。
だから、当然のごとく「神中心主義」を固守し、「人間主義=ヒューマニズム」に反対していた、カトリック教会は「そうれ見ろ」と言わんばかりの反転攻勢に出た。
第一次大戦と第二次大戦の「大戦間」に時期は、「反近代」的な思想が流行った、保守反動の時代、「近代の超克」が叫ばれた時期だったのである。
ともあれ、「ヒューマニズム」という言葉には、このような二面性がある。
一方は、「人間の理想」を信じる立場からの「ヒューマニズム」で、「ヒューマニズム」という言葉が「人間的愛他主義」という肯定的でロマンティックなニュアンスを持つものであり、もう一方は、カトリック教会的な立場からの「自己中心的人間主義」という否定的ニュアンスを持ったものである。
つまり、同じように「ヒューマニズム=人間主義」と言っても、まったく違った使われ方をする「二面性」が、この言葉には今でも生き残っているのだ。
○ ○ ○
さて、「今頃になって読む」サンリオSF文庫、ジョン・ブラナー編『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック』の第2巻には、次のような短編が収められている。
(1)おとうさんみたいなもの
(2)アフター・サーヴィス
(3)自動工場
(4)人間らしさ
(5)ベニー・セモリがいなかったら
(6)おお! ブローベルとなりて
(7)父祖の信仰
(8)電気蟻
(9)時間飛行士へのささやかな贈物
本巻には、以上に、書き下ろしエッセイ「著者による追想」が付録する。
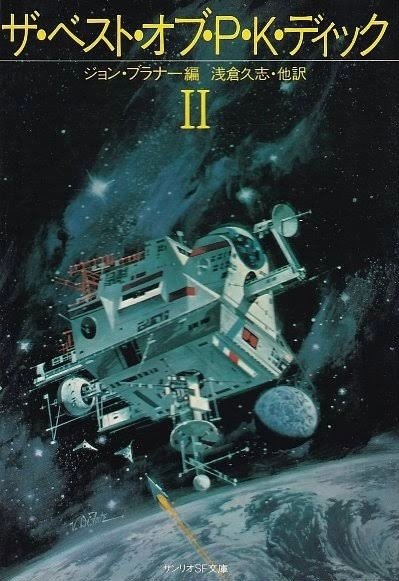
私がこの短編集で、最も気に入ったのは、(4)の「人間らしさ」だ。
後の邦訳短編集では、「時間飛行士へのささやかな贈物」が表題作に選ばれることが多いので、「人間らしさ」は、本集を代表する作品というわけではないのかもしれない。
あるいは単純に、最も「SF短編集」らしいタイトルが『時間飛行士へのささやかな贈物』だったということなのかもしれない。たしかに、作品集のタイトルが『人間らしさ』では、ディックを知らない人には、何の本だかわからないだろう。

だがまあ、そうした事情は抜きにして、私はこの「人間らしさ」という短編が、とても気に入った。
たぶん、この先「ディックの短編で好きなものは?」と問われれば、きっとこの「人間らしさ」を挙げることだろう。「ディックの短編」という縛りを外しても、私は今後この短編を、「お気に入り」として愛することになると思う。
では、私は「人間らしさ」のどこが、そこまで気に入ったのだろうか?
それは、この作品が、フィリップ・K・ディックという人の「人間的な優しさや真っ当さ」を端的に表した、「ヒューマニズムあふれる作品」だからである。
私はこれまで、自身がフィリップ・K・ディックという作家が好きな理由を、その「メタフィクション性」や「自己批評性」あるいは「哲学的思弁性」といったところにあると理解していたのだが、「人間らしさ」を読んで、私がディックが好きな理由とは、そういったことだけではなく、何よりディックの「人間的な優しさや真っ当さ」にあったことに、初めて気づかされた。
いまさら言うのもなんだが、ディックは「とても良いやつ」なのだ。

そして、その「良さ」とは、「古き良きアメリカ」が持っていた「人間的な理想」を、それが失われた時代にも持ち続けていた「古き良きアメリカ人」としての、「人間的な魅力」だと言えるだろう。
ディックは「古き良きアメリカ人」であったからこそ、独善的な「世界の警察」に変わってしまったアメリカとアメリカ人を「偽物」だと感じ、嫌悪したのである。
また、それにとどまらず、そう感じてしまう自分の中にある「古き良きアメリカ」という「イメージ」さえ、実は「偽物」だったのではないかと疑うことを忘れない、しごく気真面目な「古き良きアメリカ人」だったのだと、そうも言えるだろう。

短編「人間らしさ」は、次のようなお話である。
レスターとジルのヘリック夫妻には、子供がいない。夫のレスターは、毒物開発という仕事のことしか頭にない、野心家の仕事バカであり、かなり人間味に欠ける人物だ。一方、妻のジルの方は、生活を愛し、子供が好きな、心優しい女性である。つまり、まったく相反する性格の夫婦なのだが、結婚しているからには、レスターの方も、昔は今ほど極端な性格ではなかったようなのだが、だんだんと自己中の偏屈者になっていったようだ。
そんなレスターは、今や仕事中心、自己中心で、ジルのことを思いやることもなければ、嘘でも優しい言葉の一つをかけることさえしない男だ。ジルが心を込めて美味しい料理を作ろうとしても、レスターは食事なんて何でもいいという態度を隠さないし、子供好きのジルが、実兄の息子である可愛い甥ガスを自宅に招くことを喜ばなかった。
ジルの実兄には、家庭的な問題があって、ガスの面倒を十分に見られないようなので、ジルは喜んでガスを引き受けたのだが、レスターにとっては、ただただ「騒々しい子供がいては、仕事にならん」というわけだったのである。
しかし、それでもこれまでは、ジルがガスを自宅に招くことを許していたのだが、レスターはとうとう、今後はガスを招くことは、あいならんので、今日来ることになっているガスに、ジルの口からそれを伝えろと、非情な絶対命令を下したのである。
そんなレスターのもとへ、一通の機密通信文が届く。
そこには、彼がかねてより希望していた、惑星「レクサーⅣ」への研究出張旅行の指示がなされていた。「レクサーⅣ」には「古い世界」「古い遺跡」が残されており、ジルも「レクサーⅣ」にはロマンティックな憧れを抱いていたので、夫に、旅に同伴させてくれとねだるが、当然のことながらレスターは、それをにべもなく拒絶して、自分が旅行に行っている間だけなら、ガスを自宅においてもいいと許可を出す。それで、妥協したつもりなのである。
そんなわけで、ジルは、ほとほと夫に愛想をつかしており、レスターが2、3週間の出張旅行から帰ってくれば、離婚するつもりでいた。

ところが、旅行から帰ってきた夫は、完全に人が変わっていた。見かけは元のままだが、性格が真逆に近いほど変わっていたのだ。
思いやりがあって優しく、子供好きで、生活を楽しむことを第一とする。しかも、古典文学からその一節を引用するような、趣味人的な余裕まで持つ人。まるで文句のつけようのない「良き夫」になってしまっていたのだ。
無論、ジルにとってはありがたい変化ではあったけれども、その変化が極端すぎて、到底まともなことではないと訝っていたところ、「連邦政府出入国管理官」がやってきて、どうやら、レスターは「レクサーⅣ」での作業中に、レクサー人に捕獲されて、その体を乗っ取られたようだ、という。
「レクサーⅣ」は、すでに惑星としての環境荒廃が進んでおり、生き残るための生命力に乏しいレクサー人は数少なくなっていたが、彼らはその生き残りをかけて、異星からの収奪者たる地球人の体の乗っ取りを、「レクサーⅣ」からの脱出を企てていた。
またそのために、自星に持ち込まれる「書物」を研究して、「人間らしさ」を身につけようとしたのである。だから、彼らが乗り移った人間は、どこか「古風にロマンティック」だったのだ。
無論、このことについては地球人の側でも把握していて、「レクサーⅣ」での作業にあたっては、それなりの防備をしなければならないことになっていたのだが、仕事バカのレスターは、それを怠ったようで、そのためにレクサー人に捕らえられ、「心」を抜かれ、代わりにレクサー人の「心」が注入され、それがレスターとして、地球に帰還してきたのだ。一一というのが「連邦政府出入国管理官」の説明であった。
こうした事例は、当然、これまでも数件あったのだが、しかし、これまでは、外宇宙にいる段階で、その「地球人の体を得たレクサー人」を見つけて抹殺することができた。
ところが今回は、地球にまで入り込まれたために、話が面倒なことになってしまった。地球上においては、人間の体を持っている以上、人間に対する法律が適用されるため、外宇宙でのように「乗り移られているから、即抹殺」というわけにはいかなくなったのである。
そんなわけで、この問題を解決するには、ジルが法廷で「レスターの性格が一変してしまっており、今のレスターは本物ではない」ということを証言しなければならない。その立証証言さえあれば、「偽レスター」を抹殺することもできる、という話になってしまった。
一一そして、ジルは法廷に立って、証言した。
無論、その言葉は「私はなにも変化なんて気づかなかった」というものであった。
『 ジルは隅におとなしく立っている男のほうへ歩いていった。「さあ、行きましょうか、あなた?」ジルは男の腕をとった。「それとも、夫がまだここにいなくてはいけない理由でもありますの?」
男と女は無言で暗い通りを歩いていった。
「さあ」ジルが言った。「家に帰りましょう」
男は彼女にちらりと目をやった。「すてきな午後だ」彼は胸いっぱいに深く息を吸った。「春が近い一一と思うけど。そうだね?」
ジルはうなずいた。
「ぼくにははっきりそうと言える自信がなかった。いい匂いだ。植物や土や、育ってくるものの匂いなんだね」
「そうよ」
「歩いて行くの? 遠いのかい?」
「それほど遠くじゃないわ」
男はじっと彼女をみつめた。真剣な表情だった。「君には大変な恩をうけたね」
ジルはうなずいた。
「礼を言いたい。実を言って、ぼくは予期していなかったよ、あんなに一一」
ジルは不意に振り向いた。「名前はなんというの? あなたの本当の名前よ」
男の灰色の目がかすかに揺らいだ。ほのかに、やさしい、穏やかな笑みを浮かべた。「君には発音できないんじゃないかな、音にならないし……」
そろって歩きながら、ジルは物思いにふけって黙っていた。町の明かりが二人のまわりに点り始め、薄暮の中に点々と黄色く輝いていた。「なにを考えているんだい?」男が訊いた。
「やはりレスターと呼んだらどうかなどうかって考えていたの、あなたさえかまわなければのことだけど」
「ぼくはかまわないよ」男は片腕を彼女の体に回し、引き寄せた。次第に深まりゆく闇の中で、行く道を照らす黄色い明かりの間を歩きながら、彼は優しくジルを見おろした。「君の望むことなら何でもかまわない。君を幸せにできることならなんでも」 』(P122〜124)
まるで、クラーク・ケントとロイス・レインのような、絵に描いたようなカップル。
なんとも「古き良きアメリカ」的に、ロマンティックなラストではないだろうか。

もちろん、中には、このラストが「甘すぎる」と思う人もいるかもしれない。
なにしろ、相手は、体こそ元旦那だが、中身は異形の異星人なのである。それを受け入れることなんか、できる話ではないのではないか、と。
だが、そうではないのだ。
そうではないからこそ、このラストは、単なる「ロマンティック」なものではなく、フィリップ・K・ディックらしい、彼の本質的な人間性の表れた、「ヒューマニズム」に溢れたラストになっていると、そう言える。
一一つまり、ディックにとっての「人間らしさ」とは、生物学的に「人間」らしい、ということではなく、他者を思いやり、理想を持って生きる「心優しい」存在である、ということなのだ。言い換えれば、「人間的愛他主義」としての「ヒューマニズム」なのである。
だから私は、ディックのそんなところに惹かれるのだろう。
私は以前に、「ロボットの心」を扱ったレビューのタイトルを『つまらないヒトより、 愛すべきロボットを、 私は選ぶ。』としたのだが、これはジルの選択と、まったく同じものだといっても、過言ではないはずだ。
もちろん、現実においては「見かけ」の問題は、大きな障壁となるだろう。しかし、それは決して「絶対的なもの」ではない。
例えば、昔の「白人」は、「黒人」を人間だとは思っていなかった。「猿の一種」くらいに考えていたのである。そのため、アメリカでの黒人差別においては、長らく「黒人男性に犯され(汚され)る白人女性」という「性的妄想」が、白人男性の間に広がり、その「嫌悪感」を生理的な根拠として、黒人を憎悪し、差別迫害した。要は、「人間の尊厳」が「犯され(汚され)る」と感じていたのである。


しかし、「黒人」の「心」に触れる機会が増えるにつれ、「黒人」もまた「同じ心も持つ存在」であることに気づく者が増えてゆき、それはやがて肌の色を超え「男女の愛」ともなって、婚姻が結ばれるようになっていった。
だから、たとえ相手が「ロボット」だろうと、一見グロテスクな「異星人」であろうと、その「心」が、普通の人間以上に「人間的なもの(ヒューマニズムあふれるもの)」なのであれば、人は「外見という障壁」を超えて、彼らを愛せるようになれるはずなのだ。これは決して「理想論」などではなく、結局は「馴れ」の問題でしかないと、私はそう考えるのである。
そして、このような「感性」を、ディックもまた持っていたのであろう。
彼は「古き良きアメリカ人」として、当たり前のように、弱き者、差別される者の側に立った。
例えば、のちの短編「人間以前」(旧邦題「まだ人間ではない」)は、今アメリカで問題になっている「堕胎」についての、「殺される側」に立った寓話であった。

この作品では、子供が12歳になるまでは、「人間」とは認められていない世界が描かれる。「野犬狩り」ならぬ「野子供狩り」の存在する世界なのだ。
実際、現実の世界でも「子供は、・歳までは動物同然」などという言葉もあるくらいで、たしかに幼い子供は「人間的に未熟」であり「理性が十分に発達していない」から、「動物的」な存在だとは言えるだろう。
つまり、「十分に人間的には成っていない」という意味で「12歳までは、人間以前」の存在だとする考え方も、決して不合理なものではないし、実際、現実においても「子どもの人権」は一部制限され、「親」に帰属することになっている。
しかし、では、そもそも、どこからが「人間らしい人間」なのかと言えば、その「線引き」は、「年齢」で決められるようなものではない。なぜなら、発達生育には「個人差」があるからだし、そもそも「基準」自体が、恣意的な「社会的合意」でしかないのである。
しかしながら、そう考えると、「堕胎」を「殺人」だと考える「キリスト教」の人間観も、決して誤りではない、ということになる。
子供が、お腹の中にいるうちは「人間以前(まだ人間ではない)」で、体の一部あるいは全部が「外」に出た段階で「人間」と認められ、併せて「人権」が発生するとか、「妊娠何ヶ月」以降の「胎児」は「人間と認める」とか、そんなものは、現に生きている人間の、一方的な都合の、押し付けでしかない。
したがって、「堕胎」を「妊婦たちの権利」だと認めるというのは、実のところ「胎児たちの人権は認めない」ということであり、結局は、いま現に生きて「発言できる人間」の都合でしかないのである。

しかしまた、現実社会を回していくためには、確定し得ない「原理的な善悪問題」ではなく、「現実問題」として、現に生きている人間である「妊婦」たちの都合を優先せざるを得ない。
両方を同時に立てるわけにはいかず、どちらかを選択しなければならないとしたら、「仕方がない(止むを得ない)」ので、現に生きている人間の方を優先する、ということであり、そうでしかあり得ない。一一というのが、「堕胎の権利」の現実なのだ。
けれども、多くの人は、そうした「事情」に無自覚なまま、自身の属する「現実に生きる人間社会」の側に立って、「妊婦たちの堕胎の権利」は「当たり前の人権」だ、というくらいにしか考えていない。
それを認めない「宗教家」や「保守主義者」は、非科学的な伝統主義者だと、ただイメージだけで一蹴してしまう。
だが、そうした現実認識は、「現実そのもの」ではない、のだ。
それは、「現に生きている人間」の都合を優先した、「やむを得ざる選択」でしかなく、「殺されていく胎児たちの権利」を訴える人たちが、自明に、あるいは論理的に「間違っている」という話ではないのである。
無論、多くの「宗教家」や「保守主義者」は、そう深くは考えずに、「神の教え」にしたがい、その「慣習」にしたがって、「堕胎」に反対しているだけなのかもしれない。
少なくとも彼らは、人間と非人間では、非人間の側に立ったりはしないのだ。
だが、ディックは違う。
彼は、「人間」たちによって「虐げられる側」「差別される側」「非人間の側」である、声なき「胎児」たちの側に立って、「人間以前」という作品を書いた。
そして、それとまったく同じスタンスで、彼は「非人間的な人間よりは、人間的な異星人(非人間)を私は選ぶ」ものとして書いたのが、ほかでもない、「人間らしさ」という短編だった(のであり、映画『ブレードランナー』にもなった長編『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』といった諸作だった)。
そこで問題にされる「人間らしさ」とは、「人間であること」ではなく、「(理想的な)人間らしさ=人間的な美質」ということだったのである。

たしかに、「良き人間らしさ」を十全に満たす人間など滅多にいない。
けれども、フィリップ・K・ディックという人は、「生物学的な人間」であることよりも、彼の考える「人間らしい存在」であることにこそ価値を見いだし、それにこだわった。
その意味でディックは、頑固なまでに「古き良きアメリカ人」だったと、そう言えるのではないだろうか。
(2023年1月19日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
・
