
加藤隆 『キリスト教の本質 「不在の神」はいかにして生まれたか』 : 身も蓋もない「本当の話」
書評:加藤隆『キリスト教の本質 「不在の神」はいかにして生まれたか』(NHK出版新書)
まず、メインタイトルがシンプルに『キリスト教の本質』である。
新書のわりには「大きく出たもんだなあ」というのが第一印象だ。しかも、サブタイトルが『「不在の神」はいかにして生まれたか』とある。この言葉を額面どおりに受け取るなら、著者は「(キリスト教の)神」は「存在しない」と言っているのであり、このサブタイトルの意味は「(キリスト教は)いもしない神を、いかにして捏ち上げたのか」ということになる。したがってこれは、キリスト教の「全否定」だと言っても良い。
それにしても、そんな大胆なことを、本当に本書でやっているのだろうか? 読者の目を惹くために、大袈裟なタイトルをつけているだけで、結論的には「しかしながら、キリスト教はこんなに素晴らしい」とかいう感じで「フォロー」して終わり、なんて本なのではないのだろうか?
しかしまた、本書の帯には、次のような文言が刷られている。
『 神を裁く者
その名は
パウロ
ストラスブール大卒の神学者が、
自らの研究の集大成として放つ。
「あなたのキリスト教観が
180度変わる」
類書皆無の宗教論!』
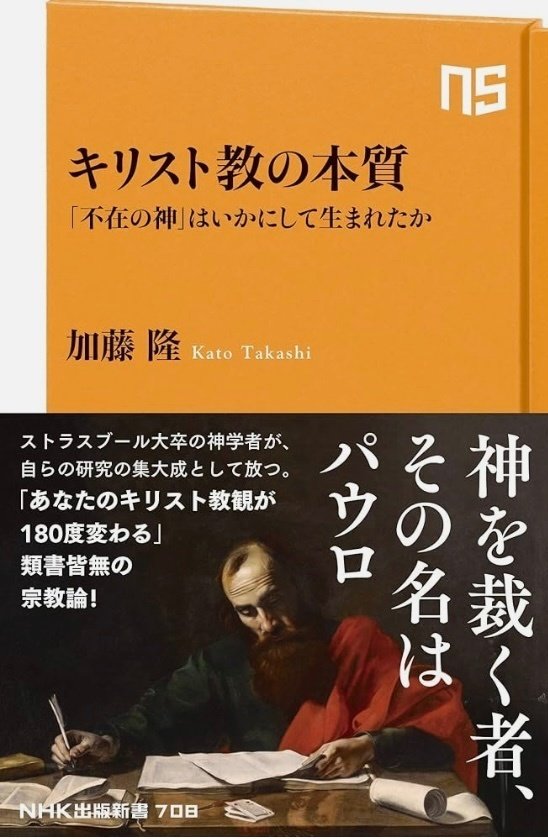
これを見ると、パウロに批判的だというのは、どうやら間違いなさそうだ。
しかし、パウロに批判的だからと言って、キリスト教そのものを否定するとは限らない。プロテスタント神学においては、パウロに批判的な神学者(神学研究者)も、決して珍しくはないからだ。要は、パウロが、本来の「神信仰」を歪めてしまった、という立場もあるからである。
パウロは、イエスと直接面識のあった十二使徒ではないにもかかわらず、その書簡が「聖書」に収められてその一部をなしているように、「今のキリスト教」を作った最重要人物である。しかしながら、「キリスト教の歴史」をユダヤ教にまで遡って見るならば、パウロの示した「キリスト信仰」観は、元来の「神信仰」を歪めるものと考えることも、十分に可能なのだ。
また『あなたのキリスト教観が180度変わる』とまで書いているのだから、少なくとも、当たり前に「しかしながら、キリスト教はこんなに素晴らしい」といった無難なところには収まらないのかもしれない。ここまで煽っておいて、そんな結論だと、ほとんど「看板に偽りありの詐欺だ」と言われても仕方がないからである。
さらにダメ押し的に『類書皆無の宗教論!』とまである。ここまで言うからには、よっぽどの「キリスト教批判」あるいは「否定」をやっていなければならないはずなのだが、はたして今どき、そんな本が出るだろうかと私はかなり懐疑的な気持ちで本書を紐解いたのだった。
で、結果はどうであったか? 一一「看板に偽りなし」であった。
真っ向からの「キリスト教批判」であった。「キリスト教否定」であったのだ。しかも、この私でも「そんな言い方はしない」と思うほどの、身も蓋もない、軽いと言ってもいいほどの言葉づかいで「キリスト教徒の信仰」を、バッサリ斬って捨てている。
そもそも、キリスト教とは「神を無視するところから始まった、人集め目的の宗教ビジネスでしかない」と、そう斬って捨てているのだ。それを、ユダヤ教まで遡ってやっているのだから、徹底しているというか、情け容赦がないと言うか、完全に真っ向唐竹割りの切り捨て御免であり、情け容赦のかけらもない。
だが、間違ったことは何も言っていないのだから、キリスト教徒にとっては「タチが悪く」ても、これは仕方のないことである。
しかし、こんなことをする本書著者・加藤隆とは、いったい何者なのであろう?
少なくとも『ストラスブール大卒の神学者』というのは、嘘ではないだろうから、神学者は神学者なのだろうが、神学者にもピンからキリまでいて、例えば、「創価学会」を大絶賛する「佐藤優」にようなタレント作家でも、かつて神学を学んだことがあるからということで「神学者」と呼ばれることもある。
したがって、本書の著者も、その手の三流神学者であり、そんなのが奇を衒って書いたキワモノなのではないのか?

しかしながら、天下の「NHK」の名を冠した出版社の刊行だし、本書著者の名前には、どことなく見覚えがある。ごく普通の姓名だから、私の勘違いなのだろうか?
と、そんなことを考えながらも、所詮、新書1冊だからと購読してみることにした。そして、驚いたのだ。「ここまで、身も蓋もなく言ってしまうのか」と。
だが、私自身「キリスト教批判者」だから、本書著者の「真っ向唐竹割りの切り捨て御免」が嫌いなわけではない。ただ、よくもここまで書いたものだなと、そう感心したのである。だから、少々あきれながらも、とても面白く読んだのだ。
著者が何者かというのも、本書の終盤に書かれていたので大筋のところ判明したし、読了後、Wikipediaを確認して「ああ、あの本の著者か。ここまで書く人だとは思わなかった」と感心したり、驚いたりもした。
著者の出自とは、次のとおりである。
『 私は日本の大学では、フランス文学を専攻した。大学卒業の後、もっと普遍的な広がりのある分野で考察したいと考えて、神学を勉強することにした。日本では、神学といっても、実は狭隘なピューリタン的自己満足の「信仰」「思い込み」をいかに上手く述べ立てるかという工夫がされているばかりで、学問になっていないし、神学になっていない。フランス文学を勉強しフランス語がそれなりにできたので、フランス語圏で神学を勉強するのは悪くないかもしれない、と考えた。紆余曲折があって、結局はフランスのストラスブールという町の大学の神学部に入学した。聖書の言語であるヘブライ語と古代ギリシア語を習得していない、ということで、学部の一年生から勉強することになり、博士号を取得するまで、十一年ほど滞在することになった。
(中略)
ストラスブールの神学部で私は、「聖書学」、特に「新約聖書学」を専攻した。ドクター論文では「ルカ文書」(ルカ福音書と使徒行伝を合わせて呼ぶ際の名称)の「社会思想」をテーマにした。なぜ「社会思想」なのかというと、ルカ文書には「神学思想」がないからである。「ルカ文書」に限らず、新約聖書の諸文書には、本来的な神学思想が欠如している。
このことは本書でも指摘した通りである。』(P234〜235)
これだけでも、この人の「ぶっきらぼう」と評していいような物言いがよく表れているが、これはこの人が、日本人によくある「面従腹背」的なものを良しとしない「馬鹿正直な人」だからである。
もちろん、自身の学問や自分自身に自信があるからこそ、人に嫌われることなど意に介していない。「嫌いたければ嫌えばいい」と、そう思っている。本書の中でも「こう言うと、異端だ無神論者だと言われるが」みたいな記述が何度か出てきて、この人が「敬虔なキリスト教徒」から、いかに「誹謗中傷」されてきたかがよくわかる。
だが、この人は、そんなものなど意に介さずに、ずばりと「真っ向唐竹割りの切り捨て御免」で、「身も蓋もない、本当のこと」を書いてしまうのだ。「文句があったら、反論してみろ。これが、学問というものなんだよ」という、傲然たる態度を崩さない。要は、クリスチャンによくいる「表づらだけは非常に良い、エセ謙遜」とか「卑下慢」ではないのだ。
またそのあたりが、物分かりの良さそうなニコニコ顔で無知な信者を誑かす、そこいらの「牧師・神父」とは真逆なところで、とても面白い人なのだ。
ちなみに、
『日本では、神学といっても、実は狭隘なピューリタン的自己満足の「信仰」「思い込み」をいかに上手く述べ立てるかという工夫がされているばかりで、学問になっていないし、神学になっていない。』
というのは、本文で縷々説明されていることではあるけれど、ごく簡単に説明すると、「ピューリタン(清教徒)的」とは、要は「ろくに聖書を学ぼうともせず聖書に無知であっても、自分たちが勝手に立ち上げた、神が褒めてくれるであろう行動規範に沿って行動することで、自分は敬虔な信者だと、勝手に思いこんでいる人たち」という意味である。だから『自己満足の「信仰」「思い込み」』ということになる。
そして、こうした態度が、なぜ「信仰者として不遜」なのかというのを、著者は、キリスト教に止まらずユダヤ教にまで遡って論証する。
ユダヤ教の信仰が、どのように生まれてきて、どのように「聖書(旧約聖書)」が生まれたのか、から説きおこす。
旧約・新約を含めた、今の一般的な「(キリスト教の)聖書」しか知らない、しかも、それを通読したこともないようなキリスト教徒の大半は、当然のことながら、ユダヤ教の聖書たる「戒律=トーラー」がどのようなものかを、よくは知らない。
だが、そっちに多少なりとも興味のある人なら、ユダヤ教徒が学ぶべき「聖書」は、いわゆる「旧約聖書(タナハ)」の部分に限るものではなく、そこに付け加わった膨大な「口伝書と注釈(ミシュナ+ゲハラ=タルムード)」まで含んでの総体だということを知っているだろう。つまり、ユダヤ教における「聖書=戒律」というのは、それを正しく守ろうとすれば、その文書して膨大な教えをすべて学び、実践しないわけにはいかないのだが、しかし、その量的な膨大さにおいて、それは人が生涯をかけても学びきれないものであることもまた事実なのだ。すべてを学び切って知っている者など、ラビと呼ばれる指導者も含めて一人もいないのだから、ユダヤ教の場合には、それを「すべて理解して、それをすべて守る」ということが、実際には「不可能」なのである。まただからこそ、それを生涯にわたって真摯に「学び続けること」が、最低限かつ実行可能な「敬虔な信仰」ということにもなるのである。

しかし、「聖なる教え」が厳格に限定されていない(戒律が文書化されて、聖書として限定されていない)段階では、こうした信仰は、大衆が無知であり、教える側と学ぶ側が、はっきりと二分されていないかぎり、成立しない。なぜなら、大衆に多少なりとも知恵がついてきて「自分なりの解釈・意見」を持ち、それを公然と語るようになると、ユダヤ教の信仰は、「解釈学的立場の違い」をめぐって、分派が発生して揺らぐことになるからだ。
そして、事実そのとおりになったから生まれてきたのが、「神の教えをすべて理解しようなどと思わなくてもいい。大切なのは、神を敬い、隣人を愛することで、生活規範ではない。だから戒律もまた絶対的なものではない」という「お手軽な信仰」を掲げた、分派としてのキリスト教(※ ユダヤ教イエス派)だったのである。
そして、こうしたキリスト教の教義的基礎を示したのがパウロだった。先鋭な反キリスト教的ユダヤ教徒から、キリスト教に転向したパウロによって示された神学は、おのずと反ユダヤ教的なものとなった。割礼の廃止や異邦人宣教によって、キリスト教は、民族宗教たるユダヤ教から、完全に別物となったのだ。
したがって、キリスト教はユダヤ教の「聖書」から、基本的な文書(タナハ)だけを残して、後の口伝・注釈部分(タルムード)は全部切り捨てて、「旧約聖書」とした。くだくだしい「戒律(教え)の理解」など不要だということなのだが、キリスト教における「旧約聖書」となる部分だけを残したのは、それはそれらが「神信仰」の基本文書だからで、それがないと「キリスト教」の「出自」もわからなければ、その「正統性」も示せなくなってしまう(復活したイエスが、主だというストーリーの根拠が示せなくなる)からである。
一一しかしながら、今でも、キリスト教神学者の中には「旧約聖書は必要ない」と公言する者もいる、ということは知っておくべきだろう。要は、キリスト教の神(主)は、実際のところ(イェホバではなく)「イエス・キリスト」なんだから、それ以前の「経緯」を証かすためだけの「権威づけのための文書」なんて、もはや必要ない、という理屈である。
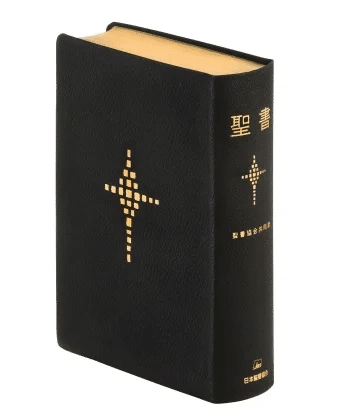
ともあれ、そんなわけだから、キリスト教徒というのは、本質的に「聖書の教え」を軽んじる。一一こう書くと「そんなことはない。たしかに、信者の中には、ろくに聖書も読まないような者も少なくないが、少なくとも教会へ行けば、牧師や神父が、聖書を引用して、その教えを説いているではないか」と、そう抗弁するだろう。
だが、本書著者にすれば、そんなものは、すべてインチキである。
というのも、そうした「聖書引用」というのは、いつでも「部分的かつ恣意的なもの」でしかなく、聖書全体の理解を踏まえてなされるものではない、勝手気ままな「権威利用」でしかないからである。
しかも、「新約聖書」にしてからが、それぞれに内容的に「矛盾」のある「四つの福音書」を収めたものなのだから、そもそも「合理的で筋の通った(一意的な)解釈」など出来ないような構造になっており、その結果、その時々「自分たちに都合の良い部分」を引用しては「自説」を「権威づけする」ことにしか、役立たないものになっているのだと、本書著者はそう「論理的」に指摘する。
一一このあたりなど、私から言わせても「それを言っちゃあ(キリスト教は)お終えよ」というくらいに「本質的な批判」である。
なぜなら、「聖書の矛盾した教えを、統一的に正しく理解し、それに沿って正しく信仰するなんてことは、論理的に(絶対に)不可能」だからである。
だが、本書著者の偉いところは、そうした「むにゃむにゃ」式になんとなく誤魔化してやり過ごすという、キリスト教の「ペテン的語りくち」の土俵には乗らずに、ごく理性的に「出鱈目なものは出鱈目と言うほかない」と言ってのけてしまうところなのだ。

したがって、本書著者の、この情け無用の「断罪」に対しては「論理的(学術的)な反論は不可能」なため、多少なりとも「聖書」を齧ったキリスト教関係者は「こいつは懐柔不可能だな」とガン無視するしかないし、ろくに聖書も読んでもいないような「頭の悪い一般信徒」の中には、感情的な反発だけで、なんとか本書著者の言葉を否定したいなどと思い、わかりやすく「匿名の誹謗中傷」に走ることにもなる。
そして、そういう視点で、本書の「Amazonカスタマーレビュー」を見れば、大変わかりやすい状況を、そこに見ることができる。
本書著者の「学問的立場」を支持する「非キリスト教徒」または「プロテスタント信者」のレビューは、レビュアー「ib_pata」氏のレビューが、
と題されて「5点満点」であるのに典型されるものだし、それに対し、「カトリック信者」または「プロテスタントの保守派信者」のレビューは、例によって、自身が「キリスト教信者」であることを隠した上での、誹謗中傷になっている。
『 Nat(5つ星のうち1.0)
ユダヤ教、キリスト教への評価の主張が、余りにも一方的です。その割には自分自身の考えは述べない。
2023年11月10日
著者は、ユダヤ教もキリスト教も(そして大なり小なり宗教一般も)、神のことを宣べ伝えているようにみせかけつつ、結局、著者の言葉で言うと「神をダシにして、どのように宗教組織を作るかという工夫をしている宗教指導者たち」の宗教ビジネスであり、そこに神はいない、という主張を持っており、この本一冊で色々書いているつもりであるが、言いたいことはそれだけである。(以下略)』
このレビューの面白いところは、タイトルに『余りにも一方的です。』と入っているように、要は「こちらの立場にも、配慮しろよ」とか「配慮して当然だ」とか、いかにも日本人的な常識に立っての「忖度」を求めていることだ。無論こういう人には、「批判」とは何なのか、なんてことは、金輪際、理解できない。
『 カスタマーレビュー(5つ星のうち1.0 )
2ちゃんねるの自伝
2023年10月12日
分厚いキリスト教研究を概観できる資料を求めて購入しました。
解釈の根拠となる引用が殆どなく、好き勝手な解釈を並べている感の否めないご著書。
冒頭とあとがきを読むかぎり、引退記念の出版といった感じでしょうか。ご自分の思い出や私怨が中心的に綴られています。
次に繋がる文献リスト等も皆無なので、勉強のために探されている方は他の書をあたられることをオススメします。』
この「カスタマーレビュー」氏は『分厚いキリスト教研究を概観できる資料を求めて購入しました。』という段階で、すでにアウトである。一一そんなもん、新書1冊でできるわけがないのは、少し考えればわかることなのだが、ろくに「聖書」すら読んだことがないから、こんな見当違いな期待をしてしまうのだろう。
高齢者丸出しの『2ちゃんねるの自伝』とか『私怨が中心的に綴られています。』とかいった言葉には、いかにも自分の信仰が否定されたがための「私怨」で書いているというのが、逆に丸出しでありながら、自身のそれにはまったく気づいていないところが、多くの哀れなキリスト教徒の実像なのだ、とも言えよう。
『 hidehiko(5つ星のうち1.0)
執筆の動機は「俺はスゴイ」と言いたいのと神学会での何らかの怨嗟や私怨では?
2023年10月24日
全部読む気になれず(読んでいて気分が悪くなったので)途中で放棄しましたが、あなたは神にでもなったおつもりですか?とお尋ねしたいぐらいの上から目線。
冒頭部分ではどこかの大学教授への恨み節がつづられ、途中でも教会のことを「宗教ビジネス」と超絶上から目線で断罪する始末。買って損しました!』
この人も、先の「カスタマーレビュー」氏と、同工異曲である。
同じように『私怨』という言葉が出てきているし、『超絶上から目線で断罪する』と、まるで、無知な自分に対しても「配慮・忖度して書け」「書くのなら、ほめて当然」といったご意見である。
現時点で、たった8本しか寄せられていないレビューのうち、3本が「このレベルのクリスチャン」でしかない事実が、「キリスト教信仰の現実」をよく表している。
前述のとおり、要は「真正面からの反論」は「不可能」だから、多少なりとも知恵のある信者は、こうした批判を「無視」するのだが、頭の悪い信者ほど、こうした「ネット右翼」並みの「匿名での誹謗中傷」をやらかしてしまい、しかも、こんなものに「参考になった(いいね)」を押してしまったりする者も少なくないのである。
繰り返すが、これが「キリスト教信仰の現実」なのだ。
ちなみに、上の「頭の悪いキリスト教信者」の3人は、本書著者のことをろくに調べもせず、ただただ「誹謗中傷」によって、多くの人に対し、著者についての「悪印象」を刷り込もうとしたのだが、ちょっと「Wikipedia」を調べれば、本書著者が、彼らのような「ど素人」が云々できるような相手ではないことくらいはわかったはず。
だが、なにしろ頭が悪くて堪え性がないものだから、何も調べずに、こうしたレビューを書いたのであろう。
『加藤 隆(かとう たかし、1957年2月 - )は、日本の聖書学者。千葉大学 人文科学研究院名誉教授。
人物・来歴
神奈川県生まれ。東京都立日比谷高等学校卒。東京大学文学部仏文科卒。1983年にストラスブール大学プロテスタント神学部入学。フランス政府給費留学生。聖書の言語であるヘブライ語と古代ギリシア語を習得していないということで、DEUG(フランス語版、英語版)課程の1年生(学部の1年生)に入学。
修士論文、博士論文の指導教官は、エチエンヌ・トロクメ(フランス語版、英語版)。1993年にストラスブール大学プロテスタント神学部博士課程修了。神学博士。
1998年に"La pensée sociale de Luc-Actes"(1997)を評価されて中村元賞を受賞。1999年、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学比較文学比較文化博士課程入学、2003年に同満期退学。
1995年から、千葉大学文学部助教授。後、同大学院人文科学研究院教授。聖書学・神学についての考察から発展して、比較文明論を行う。 2022年から、千葉大学人文科学研究院 名誉教授。
著書
La pensée sociale de Luc-Actes, (coll. Etudes d'Histoire et de Philosophie Religieuses, No.76), Presses Universitaires de France, Paris, 1997
『『新約聖書』の誕生』(講談社選書メチエ) 1999年
『新約聖書はなぜギリシア語で書かれたか』(大修館書店) 1999年
『一神教の誕生 ユダヤ教からキリスト教へ』(講談社現代新書) 2002年
『福音書 = 四つの物語』(講談社選書メチエ) 2004年
『『新約聖書』の「たとえ」を解く』(ちくま新書) 2006年
『旧約聖書の誕生』(筑摩書房) 2008年、のちちくま学芸文庫
『「新約聖書」とその時代』(日本放送出版協会、NHKシリーズ) 2010年
『歴史の中の『新約聖書』』(ちくま新書) 2010年
『武器としての社会類型論 世界を五つのタイプで見る』(講談社現代新書) 2012年
『旧約聖書』(NHK出版、NHKテレビテキスト「100分de名著」) 2014年
『集中講義 旧約聖書』(NHK出版、別冊 NHK 100分de名著) 2016年
翻訳
『家屋と日本文化』(ジャック・プズー=マサビュオー、平凡社、フランス・ジャポノロジー叢書) 1996年
『受難物語の起源』(エチエンヌ・トロクメ(フランス語版、英語版)、教文館、聖書の研究シリーズ)1998年
『キリスト教の揺籃期 その誕生と成立』(エチエンヌ・トロクメ、新教出版社) 1998年、のち改題『キリスト教の幼年期』(ちくま学芸文庫) 2021年
『共観福音書の社会科学的注解』(ブルース・マリーナ, リチャード・ロアボー、新教出版社) 2001年
『四つの福音書、ただ一つの信仰』(エチエンヌ・トロクメ、新教出版社) 2002年
『主の祈り イエスの祈りから弟子たちの祈りへ』(マルク・フィロネンコ、新教出版社) 2003年
『聖パウロ』(エチエンヌ・トロクメ、白水社、文庫クセジュ) 2004年
『新約聖書入門』(レジス・ビュルネ、白水社、文庫クセジュ) 2005年
『カトリシスムとは何か キリスト教の歴史をとおして』(イヴ・ブリュレ、白水社、文庫クセジュ) 2007年
論文
「ユダヤ教・キリスト教の伝統から見た現代西欧社会の課題」2020.2.1(平和政策研究所、政策オピニオン)p.1-14(Web上公開)(『世界平和研究』226、2020夏、p.53-67、再録)
「人類の文明世界構築と中国文明」2020.7.20(平和政策研究所、政策オピニオン)p.1-9(Web上公開)
Takashi KATO, “Les changements significatifs du sens de « guerre » dans la civilisation occidentale moderne“, Théologie et Civilisations 1, Tokyo, 2023, pp.2-18
「21世紀20年代、人類における「宗教」の位置づけ」『世界平和研究』236、2023夏、p.29-36 』
(Wikipedia「加藤隆」)
前に本書著者の著書を読んだのは、おおよそ15年ほど前にもなるから、すっかり忘れていたのだが、私は、キリスト教の勉強を始めた当初に、本書著者の『『新約聖書』の誕生』『一神教の誕生 ユダヤ教からキリスト教へ』『旧約聖書の誕生』や、著者による訳書である『聖パウロ』(エチエンヌ・トロクメ)、『新約聖書入門』(レジス・ビュルネ)といったものも読んでいる。もっといろいろ買ったのだが、例によって積読の山に埋もれさせてしまったのだ。

ともあれ、この経歴から分かるように、著者は「日本における聖書学の泰斗」と呼んでいい「一流の学者」であって、ろくに聖書すら読んでいないような有象無象のクリスチャンが、「2ちゃん並み」だとか「上から目線で威張るな」などと言えるような相手ではないのは明白だ。
また、多少なりともその自覚があるからこそ、彼らは「匿名」でしか書けないのだし、自身が「キリスト教徒」だと明かすことすらできない。正々堂々と反論することなどできないのである。
しかしながら、「神への、あるいは主イエス・キリストへの敬虔さ」さえあれば、「聖書的な知識」など必要ない、というのが、本当に「正しい信仰」なのであれば、彼らがこのような「頭の悪い卑怯者」に止まっているようなことにはならなかったはずである。
なぜなら、「実在する神」が、彼らに向けて「聖霊」を発して「賢明なる知恵」を授けたはずで、彼らに「さすがはキリスト教徒」だという言動を採らせたはずだからだ。
だが、本書著者の言うとおり、「神は不在」であるからこそ、神は今も昔も「沈黙」するしかなかったし、こうした「頭の悪い信者」や「こずるい信仰セールスマン」や「人殺しのローマ教皇」や「セクハラ神父」なども野放しにしてきたのであろう。
つまり、残念ながらこれが「キリスト教の、身も蓋もない現実」であり、本書のタイトルである『キリスト教の本質』なのである。
○ ○ ○
ちなみに、最初にも書いたとおり、本書著者の書き方(文体)は、いかにも「ぶっきらぼう」であり、さらに言うなら、文書は下手である。その学識は本物でも、それと文章の巧拙とは、また話が別なのだ。
だから、仮にも本書を「読みやすい」とは言えないのだが、別に娯楽のための読書ではないのだから、それは重要なことではないだろう。
ただ、著者の「文体」において、ひとつだけ勘違いしてはいけないのは、著者は決して「無愛想な人」だとか「ユーモアに欠ける人」ではない、という事実である。
たしかに、その「ぶっきらぼう」な文体や、「呵責のない批判」からも分かるとおり、「繊細さ」にはやや欠けるから、その「ユーモア」も、決して洗練されたものではないのだけれど、人並みのユーモアなら、ちゃんと持ち合わせている、ごく当たり前の「おじさん」ではあるのだ。

例えば、こんな具合である。
『 (※ 「第三イザヤ書」の預言は、)先ほどの、「第二イザヤ」の預言と、同様の構造になっている。(※ 「第三イザヤ書」の救いの預言が書かれた)今の状態は悪い(※ 好ましくない)。しかし(※ いずれ)神が(※ 我々ユダヤの民を)救うだろう、という(※ 問題先送りの空約束の)構造(※ が繰り返されているの)である。「第三イザヤ」が、今の状態は悪い、と認めているのだから、「第二イザヤ」で約束された救いは(※ 結局)実現していないことになる。「結婚」の比喩が用いられているので、これに沿って、次のようなことが言える。
男(※ 神)が女(※ ユダヤの民)を(※ 「第一イザヤ」の記述な反して)捨てた(※ バビロニアの侵攻から救わなかった)が、必ず呼び戻すと(※ 神は)約束する(「第二イザヤ」)。「呼び戻す」とは、「結婚する」という意味である。ところが、それから半世紀ほど経って、「君(※ ユダヤの民)は、(捨てられた女)なんて呼ばれやしないよ。将来、必ず結婚するからね」とまた(※ 神は)言っている(「第三イザヤ」)。
民としては、愛想がつきる、ということになって当然ではないだろうか。「愛想がつきる」とは、「見切る・見限る・見捨てる・見放す・さじを投げる・見切りを付ける」とった意味である。女が、ウイスキーの水割りを頼んで、「ここには幾つの嘘が溶けてるの?」と言いたくなる状況である。 』
(P129〜130、「※」印は引用者補足)
ここは、「旧約聖書」に含まれる「イザヤ書」を解説した部分である。
「イザヤ書」というのは、三つの時期に(預言者イザヤ本人および、その預言を信じ引き継いだイザヤ派によって)書かれた三文書がまとめられたもので、「第一イザヤ」「第二イザヤ」「第三イザヤ」となるわけだが、ユダヤ人が異教徒バビロニアに占領される前の「第一イザヤ」では「神は我々を守る」と言っていたに、あっさりと占領された後の「第二イザヤ」では「我々の信仰に問題があったから、神は動かなかったが、決して神は我々をお見捨てになったわけではないから、必ず妻として呼び戻してくださる」と言って、神が動かなかった理由を誤魔化した。そして、いざ占領が解けたのに、しかし彼らの苦難が続くと「第三イザヤ」では「君は、(捨てられた女)なんて呼ばれやしないよ。将来、必ず結婚するからね」といったような調子で、また問題解決の先送りで誤魔化している、という説明である。
つまり「神は動かない=実は存在しないから守れない」という事実を誤魔化すために、「自己正当化の理屈を場当たり的に捏ねたのがイザヤ書(であり聖書)だ」ということだ。神が実際に守ってくれたら、「(めったに)守ってくれない理由=信仰が足りなかったから云々といった理屈=信仰的戒律の明記」など、そもそも必要なかったのである。
だが、私が上の部分を引用したのは、こうした「聖書学」的な説明をしたかったからではなく、最後の部分を紹介したかったからだ。
『女が、ウイスキーの水割りを頼んで、「ここには幾つの嘘が溶けてるの?」と言いたくなる状況である。』
これが何の話なのか、年配者ならばわかろうが、若い人には理解不能で当然だ。
『「メモリーグラス」(作詞作曲:堀江淳、1981年)
水割りをください 涙の数だけ
今夜は思いきり酔ってみたいのよ
ふられたんじゃないわ
わたしがおりただけよ
遊びの相手なら誰かを探してよ
ゆらり揺らめいて
そうよあたしは ダンシングドール
踊り疲れても もう何処へも行けない
ねェ...キラキラと輝くグラスには
いくつの恋が溶けてるの
水割りをください 涙の数だけ
あいつなんか あいつなんか あいつなんか
飲みほしてやるわ
(以下略) 』
そう。本書著者は、上の部分で、何の説明もなく、この古い歌謡曲の歌詞をもじった比喩表現を使っているのである。
このように、本書著者は「ぶっきらぼう」な書き方はしているけれど、読者にはお構いなしに、じつは本書を「楽しみながら書いている」のだ。まるで、他人にはお構いなしにダジャレを連発して喜んでいる「おじさん」のように。
で、私は、こういう人がけっこう好きなのだ。なまじウケなど狙わず気にもせず「マイペースで楽しく生きている」、こんな人がだ。
私も、真面目な批判論文の中に、しれっとこうした「ネタ」を仕込むのが好きなのだが、こうした「イタズラ心」が、本書の著者にはある。
だから、この人は、直接会ったらけっこう面白い人だろうし、一緒に飲んだら愉快な人なのだろうと、そう推察している。
私も、かつて論争家として鳴らした若い頃、大森望から「文章から受けるイメージと全然違う」と言われた者として、本書著者には、親近感さえ覚えているのである。
(2023年12月9日)
○ ○ ○
・
・
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
