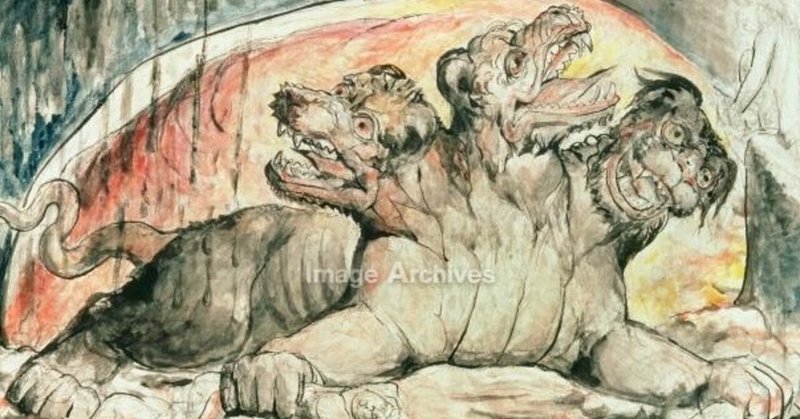
ジーン・ウルフ 『ケルベロス第五の首』 : 「難解」な作品、などではない。
書評:ジーン・ウルフ『ケルベロス第五の首』(国書刊行会)
本作は、しばしば「難解」だと評される作品である。著者であるジーン・ウルフもまた「難解」と評されることがよくある。
しかし、「わからなかった」と評する者を見たことがない。「難解」なのに、「わからない」人が見当たらないのは、いかにもおかしなことだが、それはこういうことだ。

「読書家」と言っても、当然のことながら、ピンからキリまでいる。しかしながら、どんな読書家でも、自身の読解力には、それなりの自負を持っている。
私がもう40年以上前に考案した格言に、
「読書家であれば、誰しも自分が賢いと思っているものである」
というのがある。
つまり、「難解な本」を読みこなすほどの人ばかりではなく、マンガばかり読んでいる人でも、小説ばかり読んでいる人でも、娯楽小説ばかり読んでいる人でも、やはり、自分はそこから、なにがしか「深いもの」を得ている「教養人」だと思っているものなのだ。それが、事実そうであろうとなかろうとだ。
だから、そういう読書家というのは、たかが「SF小説」ごときに、自分の「歯が立たない」という事実を認めたくはない。自分にその程度の「力(読解力)」も無いとは認めたくないから、「自分に力が無いのではなく、この本が並外れて難解なだけなのだ」とそう考えて、自身の「力量不足の現実」から、みずからの目を逸らそうとするのである。
そんなわけで、多くの読書家は、「わからない」作品を読んだら、その作品には触れないか、「わかったふり」をするものなのだ。「わからなかった」と正直にいう人の方が、よほど「非凡」なのだ。
そして、そんな「わかったふり」をする人の使う、常套句が、「難解」なのである。
言葉に敏感な人なら、この言葉が暗示しているのは、「私にはわからない」ということではなく、「一般には難しいとされるだろう作品だが、私にはおおよそのところは理解できた」ということだというのに、気づくだろう。
この「おおよそのところは理解できた」というのは、要は、完全に理解できたというわけではないから「わかりやすく説明することまではできない」が、「私の中」では「ニュアンスとしては」理解できている、という意味なのだ。つまり、「理解している」と言いつつ、その「理解」について、明確に説明することからは逃げているのである。
「なにしろ難解な作品なので、平易に説明することは難しいなあ」とかいった調子で、理解していると言いながら、決して説明はしない。実際には「できない」だけ、なのだが。
したがって、「難解な作品」だと評するばかりで、その理解を具体的に説明できないような評者は、すべて「見栄っ張りの嘘つき」だと断じていい。
単に「能力的に理解不能な作品」を読んだだけなのだが、理解できなかったという事実が屈辱的に感じられるから、つい見栄を張って「なかなか面白い作品なんだけど、なにしろ難解な作品ではあるから、一般ウケはしないんだろうね」などと「理解しているふり」をして、スカして見せているのである。
そんなわけで、本作『ケルベロス第五の首』について、私は、「わからなかった」と評することにする。
しかしながら、「なぜ、わからなかったのか?」についてなら説明できる。その点については、理解しているからである。
この「違い」がわからないような人は、「難解」であるとか「平易」であるとかいう以前に、まったく読解力のない思考停止した人でしかない。だから、そんな評者の言葉など、真にうけないのが、知性ある読者の態度だと、最初にそう助言しておきたい。
次のような言葉が、紀元前500年もの昔から存在する。
『子曰く、由よ、女に之を知るを誨えんか。之を知るは之を知ると為し、知らざるは知らずと為す、是 知るなり。
老先生の講義。「由君よ、君に〈知る〉とは何か、教えよう。知っていることは知っているとし、知らないことは正直に知らないとする。それが真に〈知る〉ということなのだ。』
加治伸行『論語 ビギナーズ・クラシックス 中国の古典』(P167~168)』
これについて、私は次のように解説した。
『「知ったかぶりをするな」ということだけではない。それは当然として、より肝心なのは、自分が「何を知らないのか。何を理解していないのか」を知らないと、決して「成長はできない」ということである。
「私は、自分が無知であるということを知っている」という「無知の知」は、ただ「無知であることを知っている」というだけでは、意味がない。それを「知っている」自分に満足してしまうからだ。
しかし、「具体的に、何を知らないのか」まで知っていれば、おのずと現状に満足することなく、学びを続けるはずなのだ。そうしないではいられないはずなのである。
したがって、狭い得意分野や専門分野に自足して満足しているような人は、「無知の知」がない「無知の人」だということなのである。』
つまり、自分が「わからない」という現実を直視するのではなく「完全にはわからない(が、おおよそのところは、何となくわかる)」などと考えたがる人は、当然のことながら、「無知の知」が無い「無知の人」であり、「進歩成長のない人」だと理解していいのである。

例えば、本作『ケルベロス第五の首』を読んで、「わからない」と感じたとしても、「知」のある人(知者)であるならば、自分の無能力を正当化するために「難解な作品だ」などと言ったりはせず、「なぜ、この作品が、私にはわからないのか?」「この作品のどこがどのように、私にはわからないのか?」といったふうに考えるだろう。それが「知」というものであり、「知者」の態度だからである。
当たり前の話なのだが、「すべてをわかる人」など、この世には存在しない。
もちろん、「わからないもの」のあることを「恥辱」だと感じるのは、まあが仕方ない。それがないと、向上心も生まれないからだ。
しかし、「わからないものがあるのは恥辱だ」と考えて、即座に「知ったかぶり」をしてしまうような人というのは、基本的に「馬鹿」でしかない。
なぜなら、少し考えればわかるとおり、「全能の神」ならぬ身の人間の中に、「すべてがわかる」者などいるはずがないというのは、分かりきった話だからで、そんなことにも気づかずに、脊髄反射的に誤魔化すなどというのは、頭が働かない証拠であり、「論理的に考える習慣がない」証拠に他ならないからである。
したがって、以下では、なぜ私には本作の「面白さ」が理解できなかったのか、それを説明しようと思う。
この説明は、本作がわからなかった人にとっては、決して無駄にはならない。それは、ここでの説明が「言い訳として役立つ」という意味ではなく、「己を知る」という意味で役立つのだ。己を正しく知る者、あるいは「知ろうとする者」こそが、まさに「知者」なのである。
○ ○ ○
本作『ケルベロス第五の首』は、最後まで読めばわかるとおり、最後まで読んで初めて「全体像」のつかめる作品である。したがって、読んでいる最中は「よくわからない」のが、当前なのだ。
そして「よくわからない」からこそ、読んでいる最中は「スッキリしない(理解できない)」ので、たいがいは「面白くない」と感じるし、そのために「難解な作品」だと、そう「はやとちり」しがちなのである。
だが、そうではない。前述のとおり、本作は、最後まで読んで初めて、その「全貌」がつかめる小説なのだから、最後まで読まない段階では「わからない」のは当然なのだ。
本作は、「SF小説」に分類される作品ではある。けれども、その造りは、大いに「本格ミステリ」的だ。しかも「叙述トリック」ものの本格ミステリである。一一これがます、本作を理解する上での、ポイントのひとつだ。
どういうことかというと、例えば、ある「叙述トリックもの」の本格ミステリでは、物語が「多面的」に描かれる。「被害者の視点」「犯人の視点」「刑事の視点」などが、ある一つの殺人事件をめぐって、交互に「描写」されたりする。
読者は、そうした「主観的かつ多様な視点」を総合して、「客観的な現実=真相」に至ろうとする。一一ところが、ここにこそ、作者による「トリック」が仕掛けられている。
例えば、「被害者と犯人(加害者)」は、じつは同一人物であった。一一どうしてそのようなことが可能なのかというと、じつは「被害者の視点」で描かれる「現実」は「過去」のものであり、「犯人の視点」で描かれる「現実」は「現在」のものであったから、両者は両立するということになる。つまり、時制をずらすことによって、「彼は被害者であり、かつ犯人だ」というのが可能になる。当然、その逆も可能である。つまり、「彼は、かつては加害者であったが、今は被害者である」というだけではなく、「彼は、かつては加害者であったからこそ、今では被害者の立場に立たされてしまった」というようなパターンである。
無論、これは一例に過ぎないのだが、「叙述ものの本格ミステリ」というのは、こういう「視点の詐術」というものがよく使われる。最初に「全体像」を見せずに「部分」を積み重ねることで、徐々に「真相=全体像」に至り得るかのように書かれているように見せかけて、実は、その途中に「トリック」が仕掛けられているというパターンだ。

本作『ケルベロス第五の首』も、基本的にはそうした「パズルのピース」を読者に少しずつ与えていって、最後には「全体像」がわかるようになる、というパターンの小説だ。
だが、本作が、前述の「叙述もの本格ミステリ」と違うのは、「終着点のイメージすら、まったく与えられていない」という点にある。
前述の「叙述もの本格ミステリ」であれば、まず作品の冒頭で「通り魔連続殺人事件」等の発生が描かれて、解明すべきは謎とは「誰がこの事件の犯人なのか?」だと示されている。その上で、物語展開の中で示される「犯人の視点」とは、登場人物のうちの誰の視点なのかと、読者は推理しながら読むことができる。読者は、読みの方向性を、あらかじめ示されているのである。
だから、途中で「全体観が持てない」のは当然(それが目的)なのだから、読者はそのことに不満やイライラを覚えることはないのだ。
ところが『ケルベロス第五の首』の場合は、そもそも「何を目指して読むべきなのか?」「作者は何が描きたいのか?」がまったく示されておらず、読者は「五里霧中」の中に放置されて、ただ、作者が断片的に投げ与えてくる「描写」を、その意図もわからないまま受け取り続けるしかない。だから「訳がわからない」し「スッキリしない」。
つまり、前述の「叙述ものの本格ミステリ」と『ケルベロス第五の首』との違いは、前者が大まかな「完成予想図」を示した上で、バラバラのピースを与えていくのに対し、後者の場合はそれを示さないまま、ピースを与えてくるだけだから、「目的地(完成図)」や、その方向性の見当すら、まったく見通せないので、ストレスを抱えなければならないのである。

したがって、本作を楽しく読める人というのは、そもそも「真相」なんてどうでもよくて、ジーン・ウルフの「文体」や「描写」自体を楽しめる人だということになる。
それを楽しみながら読んでいった末に、最後に「完成図」を見せられて、初めて「そうだったのか」と「そこでも楽しる」人が、ジーン・ウルフの良き読者だということになるだろう。
だが、こういう読者は、日本でいうところの「純文学」系文学の読者には少からずいたとしても、「SF小説」や「ミステリ小説」の読者には、決して多くはない。
SFやミステリというのは、基本的に、その「アイデア」を楽しむ文学ジャンルであって、「文体」や「描写の妙」というのは、「アイデア」を活かすための「副次的」ものだと考えられているからである。
だから、本作『ケルベロス第五の首』が、SF読者の理解を得にくい作品だというのは、いわば「当然」のことに過ぎない。要は、本作は、SFファンやミステリファンが求めているような小説ではないのである。
だから、本作を、当たり前の「SF小説」のつもりで読むと、「何がやりたいのか、わからない」し「何が面白いのか、わからない」ということになりがちなのだ。読者の求めていたものと、作者が描きたかったものとが、完全にくい違っているからである。
以上が、「『ケルベロス第五の首』が、難解だと勘違いされる」理由である。
○ ○ ○
次に解くべき謎は「なぜ、シーン・ウルフは、こんな(SFファンの期待を、わざわざ外したような)小説を書いたのか?」という点であろう。
その答は、彼が「ファンタジー作家」的な資質を、強く持っていた人だからである。
例えば、「Wikipedia」を見てみると、ジーン・ウルフは、次のように紹介されている。
『ジーン・ウルフ(Gene Rodman Wolfe、1931年5月7日 - 2019年4月14日)は、アメリカ合衆国のファンタジー作家、SF作家。』
この紹介を見て、「あれっ?」と思った人は正しい。
というのも、近年翻訳されているジーン・ウルフの作品は「ミステリ作品」が多いからだ。つまり、ジーン・ウルフは、
「アメリカ合衆国のファンタジー作家、SF作家、ミステリ作家。」
と紹介されて然るべき人なのだが、そうなっていないのは、きっと、この「Wikipedia」の記述が古いからであろう。
ジーン・ウルフは、日本においては、まず「ファンタジー作品」が紹介かれ、それからずっと遅れて、本作のような「SF作品」が紹介され、それからさらに遅れて、最近になって「ミステリ作品」が紹介されるようになった作家なのだが、「Wikipedia」の記述は、「SF小説」が紹介されたあたりで更新が止まっている、ということなのである。

ともあれ、そんなわけで、ジーン・ウルフは、典型的な「SF作家」ではなく、「ファンタジー作家」でもあれば「ミステリ作家」でもあり、そうした性格を兼ね備えていると言って良いだろう。
そして本作『ケルベロス第五の首』が、「叙述もの本格ミステリ」的な「構造」を持った作品であるというのは、先に説明したとおりである。
だが、それにもかかわらず、本作には、「本格ミステリ」のような「冒頭の謎を徐々に解明していく」といった「面白さ」が、完全に欠けている。
読者は、ただ「五里霧中」の世界に放り込まれて、作者に引き摺り回されるまま、まるで主体性などカケラもない「おのぼりさん」の如く、あっちを見たりこっちを見たりというかたちで、不連続的に「断片」を提示されるだけで、作品世界の「全体像」というのは、結局のところ「最後に作者から示される」まで待たなければならないように、書かれているのである。
一一では、なぜ作者ジーン・ウルフは、このような不親切な書き方をしたのだろうか?
それは、彼が本質的に「ファンタジー作家」であり、彼が求めており描きたいものとは、私たちの常識で理解されるようなものではなく、まったく「別の論理」で作動している、独立的な「別世界」だったからである。
「SF作家」や「ミステリ作家」ならば、普通は「私たちの常識で理解できるもの」を描こうとする。
とは言え、そのまんまでは「わかりやすすぎる」ので、「私たちの理解の、少し先の世界(の真相)」を描こうとする。それなら、「こちら側の論理」にまで回収しきれはしないまでも、「類推」ならば可能だからである。
つまり、「ミステリ小説」ならば「狂人の論理」、「SF小説」ならば「異星人の論理」などがそうだ。
それらは、完全には理解できなくても、「類推」において、おおよそのところは「想像し得る(察し得る)」のである。
ところが、「ファンタジー小説」、特にその王道だと言われる「ハイ・ファンタジー」では、しばしば、私たちの現実とはまったく異質の「世界原理」を想定して、その原理を前提とした「自己完結的に合理的な世界」を描こうとする。

「ミステリ小説」における「狂人の論理」であろうと、「SF小説」における「異星人の論理」であろうと、それらは基本的に「この宇宙の論理」の中での「異種」に過ぎない。
しかし、典型的な例で言うなら、J・R・R・トールキンの『指輪物語 ロード・オブ・ザ・リング』や、C・S・ルイスの『ナルニア国物語』のような「ハイ・ファンタジー」作品は、明らかに「この宇宙の原理・法則」とは、「別の原理・法則」の上に構築されている。


その世界では「魔法が使えるのはなぜか?」という「疑問」は成立しない。なぜなら、「魔法の存在」というのは、私たちの宇宙における「重力の存在」にあたる「自明の前提」であり、それは「あるからある」という「疑いえない事実」だからである。
他の例を挙げれば、「ドラゴンは、どうしてあの程度の翼で空を飛べるのか? どう見ても、物理法則に反している?」と問うのは、間違いである。なぜなら「ドラゴンの存在する(ファンタジーの)世界」の「物理法則」とは、私たちの「この宇宙の物理法則」とは「別物」だからだ。
そこで、起こってくるのが、そういう「別の論理」を、「面白い」と思えるか思えないかの「違い」である。
「なぜ、密室の中で殺人が行われ、犯人がいなくなったのか?」という「ミステリ小説の謎」は、「この宇宙の論理」が前提となっていて初めて「論理的に解明できる」ものである。そこに「魔法使い」が無前提に存在していたら、その謎はそもそも成立しないのだ(そして、これは「特殊設定ミステリ」でも同じことだ、前提条件が提示されていない作品は、本格(謎解き)ミステリにはなり得ない)。
これは「SF小説」でも同じことで、異星人との「ファースト・コンタクトもの」でよくあるように、「なぜ彼ら(異星人)は、あんな訳のわからない反応をしたのか?」という「疑問と、その謎解き」が成立するためには、人類と異星人の「文化」や「思考形式」がどんなに違っていようとも、根本的な「この世界の論理」としての「物理法則」などが同じでないかぎり、論理的に解ける訳がないし、類推することすら不可能なのである。
つまり、『ケルベロス第五の首』の「面白さ」が、多くの「SFファン」や「ミステリファン」に理解できないのは、「SFファン」や「ミステリファン」の多くは、作品に描かれた世界を、「この現実世界の論理」に還元することで「理解したい」という「当たり前の欲望」を持っているからである。
ところが「ハイ・ファンタジー」のファンというのは、しばしば「この世界以外の、別の世界」に強烈な憧れを持っている。「この世界」には飽き足らないものを感じているからこそ、「この世界」には還元し得ない、「別の世界」を求める。「この世界の論理」になど還元されてしまわない、完全に自立した「別の世界」を求めるのだ。
そして、ジーン・ウルフという人も、その本質部分で、そういう人だったということである。だから、一般的な「SFファン」や「ミステリファン」のように、「この世界の論理」で解けない(還元できない)世界になど、興味のない人には、ジーン・ウルフ的な「ファンタジーの世界」の魅力が「理解できない」ということになる。
「魔法やドラゴン」が、無条件に存在している「異世界」に遊ぶことに魅力を感じないようなタイプの「現実的な人間」には、『ケルベロス第五の首』の魅力がわからない。
それが「わからない」というのは、「頭が悪いから、わからない」のではなく、「求めるものの方向性が根本的に違う」から「わからない」のだ。
ここで例え話をしよう。
私は徹底した「無神論者」の「宗教批判者」である。
そんな私には、キリスト教が語るところの「イエスの死後3日目の復活と、肉体を持ったままの昇天」だとか「聖母マリアの処女懐胎」だとかいったものは、完全に「理解不能」だ。
そうしたものに「憧れる」人が大勢いるというのは理解できるけれども、それは「現実逃避」をしているからだと、そう理解しているだけで、「イエスの死後3日目の復活」や「聖母マリアの処女懐胎」が「あった」とか「あり得る」などとは、まったく思っておらず、思うこともできず、その意味で、そんなものを「あった」とか「あり得る」と「本気で思える人」の心というのは、漠然と「想像」は出来ても、「理解」は出来ないのである。

で、「ファンタジーの描く別世界」に本気で憧れることのできる人というのは、その「現実逃避」性において「宗教信仰者」と同じことなのだ。
その「世界」とは、「この世の論理で理解すべきもの」ではなく、「それをそのまま信じ、その世界に生きようとするもの」なのである。
それを「なぜ?」と問うてはならない。それは「そういうもの」なのであり「そうなのだ」と「信じなければ、逃避は成立しない」からである。
で、本書の「解説」で、訳者の柳下毅一郎が書いているとおり、ジーン・ウルフは「カソリック=カトリック」信者なのだ。
つまり「イエスの、死後3日目の復活」や「聖母マリアの処女懐胎」を歴史的事実として認めますと、己の信じる「神」の前で、そう「信仰告白」した人、「神」に誓った人であり、その点では、(前述のような「神話」をそのまま信じなくても良い)近代主義の「プロテスタント(新教)」である「英国国教会」から、「カトリック(旧教)」に、わざわざ「帰正」した、反近代主義者である、J・R・R・トールキンやC・S・ルイス、あるいは、G・K・チェスタートンらと同じく、ジーン・ウルフは、「神の世界=別の原理によって作動している別世界」を「信じている=信じたい」人なのである。つまり、私の言葉で言えば「現実逃避者としての、ファンタジーファン」なのだ。

したがって、柳下毅一郎が「解説」で書いている、
『 ジーン・ウルフはカソリック信者であり、その作品には深く宗教の影が落ちている。とはいえウルフはきわめて知的な人間なので(カソリック信仰自体も大人になってから神学書を学んで得たものである)、神も悪魔も単純な比喩ではない。「わたし」が悪魔だとすれば、それは人を堕落させるからではなく、彼が反進化的存在だからである。神は世界を創造した。だが、悪魔は何も創造しない。悪魔は創造する力を持たないので、神の創造物に干渉することしかできないのだ。「わたし」は人間的成長を拒み、あくまでも停滞しつづけることで悪魔的存在となるのである。悪魔は自分がなぜ神になれないのかがどうしてもわからず、いつまでも実験を繰りかえしつづける。模倣しかできないサント・アンヌの原住民(アボ)もまた、自分がなぜ人間になれないのかは決してわからぬままだろう。』(P328)
というのは、所詮、「信仰」の問題を、真剣に考えたことのない者の、その場かぎりの、知ったかぶりの「こけおどしのレトリック」に過ぎない。
「なら、あんたはカトリック(カソリック)の信仰を持つのか? 洗礼を受けるのか?」と問えば、柳下は決して、洗礼を受けるとは言わないだろう。
つまり、ここで柳下の言っていることは、所詮、この場かぎりの「お為ごかし」でしかない。また、万が一、柳下がすでに「カソリック」なのであれば、彼のここでの言い分は「カソリック信者の(手前味噌な)ファンタジー」に過ぎない、ということになるのである。
したがって、「信仰者」ではなく、「別の原理で作動する世界」を「本気で信じたい」などとは思っていない私たちの多くは、本作『ケルベロス第五の首』に描かれた「ファンタジーの世界」を、「そのまま」受け入れることはできない。それは原理的に「理解できないもの」だからだ。
したがって私たちは、この作品の「面白さ」が十分に「理解できない」。これは「理の当然」なのである。
(2023年12月27日)
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○(エンタメ)
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
