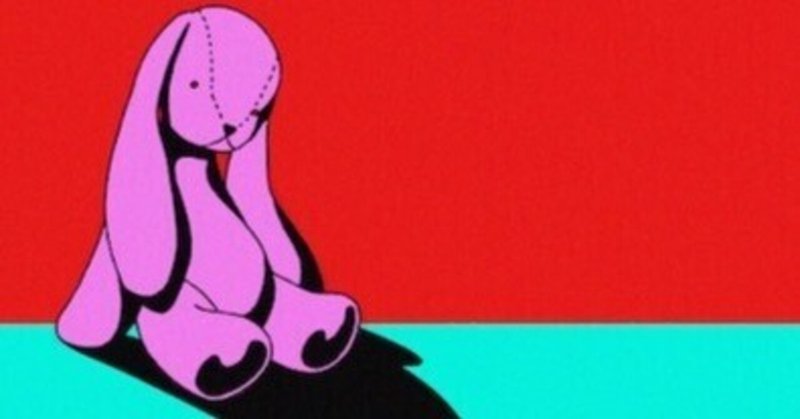
クリスチャン・タフドルップ監督 『胸騒ぎ』 : 日本人こそが見るべき映画
映画評:クリスチャン・タフドルップ監督『胸騒ぎ』(2022年、デンマーク・オランダ合作映画)
本作を紹介するネットニュースを読んで興味を持った。映画公開前のニュースだったから、ネタバレにならないように注意して書かれたものであり、どんな映画なのか、その正確なところはわからなかった。
だが、旅先で知り合った、デンマーク人夫婦とオランダ人夫婦の「文化的齟齬」か何かを扱ったホラー映画のようで、少なくとも超常現象だの怪物だのを扱った作品ではなく、繊細な心理ホラーのようだと、おおよそそんな見当をつけた。
そして「なら、一種のサイコホラーだろうな」とそう思って、本編を見たのである。

本作の「あらすじ」は、次のとおり。
『イタリアでの休暇中、デンマーク人夫婦のビャアンとルイーセ、娘のアウネスは、オランダ人夫婦のパトリックとカリン、その息子のアーベルと出会い、同世代の子どもを持つ者同士で意気投合する。
“お元気ですか?少し間があいてしまいましたが、我が家に遊びにきませんか?”
後日、パトリック夫婦からの招待状を受け取ったビャアンは、家族を連れて人里離れた彼らの家を訪れる。
オランダの田舎町。豊かな自然に囲まれたパトリックの家に到着し、再会を喜んだのも束の間、会話のなかで些細な誤解や違和感が生まれていき、それは段々と広がっていく。パトリックとカリンからの”おもてなし”に居心地の悪さと恐怖を覚えながらも、その好意をむげにできないビャアンとルイーセ。
善良な一家は、週末が終わるまでの辛抱だと自分たちに言い聞かせるが ——。』
(『胸騒ぎ』公式サイト・「STORY」より)
旅先で知り合ったオランダ人夫婦のパトリックとカリンに招かれ、デンマーク人夫婦のビャアンとルイーセが、娘のアウネスを連れて、彼らの家で週末を過ごしに、自家用車で出かける。両国は地続きであり、そう遠くもないからだ。

そして、到着したパトリック家で歓迎のもてなしを受けるのだが、いろいろと細かいところで、引っ掛かりを覚え始め、だんだん「こいつら(この夫婦)、何なんだ?」という違和感と共に、不快感が募ってゆく。
しかし、お客さんとして招かれ、歓迎を受けている立場なので、言いたいことは呑み込んで、笑ってその場をやり過ごそうとするのだが…。
パトリック夫婦に感じた「引っ掛かり」とは、大小いろいろとあるのだが、例えば次のようなものである。
(1)ルイーセは「ベジタリアン」で、当然のことながら、肉は食べない。そのことは、イタリアへの旅先で知り合った際に、パトリック夫婦にも話しており、そのことに対してパトリックは「素晴らしいことだ!」と盛大に褒めてくれてもいた。
ところが、パトリックの家に着いて、最初の歓迎の食事をパトリックが腕を振るってくれたのは良いのだが、オランダ料理だとかいう肉料理を出してきて、ルイーセに「美味しいから、一口食べてみろ」と嬉しそうにすすめてくる。ルイーセは当初、自分がベジタリアンであることをパトリックが忘れたのだと思い、「私はベジタリアンだから、申し訳ないけどいただけないわ」と断るのだが、パトリックは「何を言っているんだ。ちょっとくらい食べても平気だろう。せっかく君たちのために作ったんだ。絶対に美味いんだから食えよ。食ってくれ」と、ルイーセの困惑をよそに、喜んでもらえるものと信じきったかのような笑顔を浮かべて、フォークに刺したその肉料理を突きつけてくる。
困ったルイーセは、夫ビャアンに「困ったわ、どうしよう?」と目くばせするが、ビャアンは「仕方ないよ。好意なんだから、一口だけ食べてやれよ」と目くばせで促すので、ルイーセは嫌々ながらその肉料理を一口食べた。するとパトリックは「どうだ、上手いだろう?」と聞くので、しかたなしに笑みを浮かべて「ええ、とっても美味しいわ。でも、これだけで遠慮させてもらいますね」と、それ以上の無理強いを、やんわりと避けたのであった。
要は、パトリックは、悪い人ではなさそうなのだが、相手に対する思いやりや配慮に欠けて「無神経」な人物のようだった、のである。一一だが、こうした不快な齟齬は、それだけでは済まなかった。

(2)パトリックから「郷土料理を食わせる、とても美味い店があるので、そこで食事をしないか」と提案され、つきあうことにしたビャアン夫婦だったのだが、いざ出発する段になると、店に食事に行くのは大人の4人だけで、ビャアン夫婦の娘アウネスと、パトリック夫婦の息子アーベルは、家に残しておくと言う。それでルイーセは「子供たちだけを残していくわけにはいかない」と言うと、パトリックは「ベビーシッターを呼んであるから大丈夫だ」と言い、その言葉どおり、まもなく、肌の浅黒いアラブ系かと思われる30歳前後の男がやってきて、なるほど上手にアウネスの相手をしだしたので、子供たちは彼に任せ、パトリックの車で店に向かうことになった。
ところが、この「料理店」と言うよりは「居酒屋」に近い店は、メニューのレパートリーが少なく、もとよりビャアン夫婦はオランダ語が読めないので、何を注文して良いやら困っていると、パトリックが「俺に任せてくれ」と言うので、言われるままに料理の注文を彼に任せたのだが、どうということのない料理しか出てこなかった。
その上、パトリック夫妻の方は酒がどんどん進んで、そのうちBGM音楽に合わせて、夫婦で踊り出したのは良いのだが、ビャアン夫婦の存在など忘れたように、濃厚なキスを交わしたりしながらベタベタした様子で、すっかり二人だけの世界に入ってしまう。
さらに、食事が済んで勘定になると、会計伝票を見たパトリックは「ああ、えらい散財しちまったな」と言い、ビャアンに「申し訳ないけど、半分出してもらえないか?」と言うので、ビャアンが気を利かせて「ここは私の奢りということにさせてもらおう」と提案すると、なんとパトリックは「そうか、ありがとう! では、お言葉に甘えさせていただくよ」と、一銭も払わずにさっさと店を出てしまう。呆気にとられながらも、ビャアンはやむなく全額支払ったのだが、ビャアンが「ここは僕の奢りで」と言ったのは、もちろん儀礼的な「お約束」の一種であって、そう言えば、パトリックが「いやいや、そういうわけにはいかないよ」と、折半になるものと踏んでの、形ばかりの申し出だったのである。それがまさか「はいそうですか。ありがとう」なんてことになるとは、思いもよらなかったのだ。
(3)そして話はそれで済まなかった。その「居酒屋」には、パトリックの車、パトリックの運転で来たので、帰りも無論パトリックがハンドルを握ったわけだが、当然ながらこれは飲酒運転であり、しかも、ひどく酔っている。
それだけではない。酔って浮かれたパトリックは、カーステレオでにぎやかな音楽をガンガンかけ始めたので、ただでさえ、気分を害しているルイーセは、パトリックに「音量を下げてくれないか」と、後部座席から頼むのだが、それが聞こえているのかいないのか、まったくの無視である。
そこで、業を煮やしたビャアンが、声を荒げて「音を下げてくれ」と怒鳴ったところ、初めて、そのことに気づいたかのように、パトリック夫妻は「申し訳なかった。気が付かなかったもので」と言って音量を下げたのだが、しかし、その直後、パトリックは、その殊勝な態度こそが、酔ってふざけたお芝居であったかのように「なーんてな」とか言って笑いながら、また音量を大きくして、乱暴な運転をするので、もはやビャアン夫婦は黙って、パトリックの運転に身を委ねるしかなかったのである。
つまり、ここでも、パトリック夫婦のやっていることは、極めて「非常識で礼儀知らず」なのだが、ただそれは「酔っ払っているからだ」と考えることもできた。
実際、酔って羽目を外してしまう人などいくらでもいるから、「不快だが、まあ仕方ない。数日の我慢だ」と、ビャアン夫婦はそう思って我慢するしかなかったのである。
だが、こうしたことは、このこと以外にもいくつも続いたため、ついにルイーセは、翌早朝、まだパトリック夫妻が眠り込んでいる隙に、彼らに黙って、同家を立ち去ることを決断し、それを決行する。
(4)そんな決断をうながした原因の一つとは、例えば、イタリア旅行で食事を共にしながら話した際には、パトリックが「国境なき医師団」に参加した時の思い出話をしたので、医師なのかと尋ねると、彼はそうだとハッキリと答えていた。
それで、パトリック家を訪れてから、料理の手伝いを申し出たルイーセが、誤って包丁で指を切ってしまった際、ビャアンが「ここには医者がいるんだから、パトリックな任せれば大丈夫だ」と言うと、パトリックは「医者って誰かだ?」と真顔で尋ねるので、ビャアンが「前に君がそう言ったじゃないか」と言うと、パトリックは悪びれた様子もなく「ああ、あれは旅先でのちょっとした嘘だよ。今は仕事はしていない。無職だ」と答えて、ビャアン夫婦を唖然とさせたりしたのである。
そんなことが重なり、ルイーセは「あの夫婦にはもう我慢ならない。何をされるかわかったものではない」と思い、義理を欠いてでも、黙って帰宅することにしたのだ。
予定を早めて帰ると正直に言えば、いろいろと面倒なことなりそうだったので、黙ってさっさと帰ってしまい、そのまま縁を切ろうと考えたのである。
ところが、家族3人でパトリック家を立ち、だいぶしてから、娘のアウネスが、幼い頃から肌身離さず持ち歩いているウサギのぬいぐるみが無いと騒ぎだした。どうやら、パトリック家に置き忘れてきたようなのである。
当初夫妻は、黙って出てきたこともあって、むいぐるみを取りに戻る気などはなく、娘に「新しいのを買ってやるから、我慢しろ」と言い聞かせ、なんとか諦めさせたのだが、いつまでも涙を流している娘が哀れになったビャアンは、結局、車を戻してしまう。
そして、パトリック夫婦にみつかれば面倒な話になるのはわかっていたので、妻と娘は車の中で待たせて、ビュアンは一人でパトリック家の中へ、ぬいぐるみを探しに入っていった。
ところがしばらくして、アウネスが、後部座席の足元にぬいぐるみが落ちているのを見つける。置き忘れてきたのではなかったのだ。そこでルイーセは、娘を車に残して夫を呼び戻しにいくのだが、案の定、夫はパトリック夫妻につかまって、「どうして黙って出ていこうとしたんだ。理由を説明してくれ」と追求されていた。
だが、人の良いビャアンは、角が立たないよう曖昧に「いろいろとあって」というような「言い訳」に終止するのだが、パトリック夫妻は、理由を説明しろの一点張りで、いっこうに諦める様子がない。そこで、その様子を見ていたルイーセは、腹に据えかねていたあれやこれやを、ついにぶちまけてしまう。
それを聞かされたパトリック夫妻は、どうしたか?
彼らは「思いもよらないことを聞かされた」とでもいう様子で、すっかりしょんぼりとしてしまい「悪気はなかったんだ。だが、君たちにそんな不快な思いをさせてしまったのなら、それは私の責任であり、私がホストとして失格だったということだろう。本当に申し訳なかった。どうか許してほしい」と詫びるのである。

しかし、そう素直に詫びられてしなうと、言いたいことを言ってパトリック夫妻を非難したビャアン夫妻としては、今度は自分たちの方が「おとな気ないことをした」という気分になってしまい、そんな謝ってもらうようなことではないと、逆に宥めることになった。
するとパトリックは「もう一度、僕たちにチャンスをくれないか。きっと君たちに満足してもらえるようにすると請け合うから、もう一晩泊まっていってくれ」と熱心に乞われて、ビャアン夫婦は、この申し出を受けてしまうのである。
で、この後、どうなったのかは、おおよその見当はつくだろう。
要は「あの時、途中でひき返したりしなかったら。引き止められても、断って帰っていたら」と、そう後悔する結末を迎えることになるのだ。
【※ 以下で、本作の結末を紹介してネタをわりますので、未鑑賞の方はご注意ください。しかし、できれば、この先を読む前に、本作の鑑賞をお奨めします。本作は、間違いなく見る価値のある異色作だと、ここで保証させていただきます】
● ● ●
結局、パトリック家でもう一泊することになったビャアン一家であったが、やはり、パトリック夫妻の様子はどこか変で、しっくりこないところがある。
謝罪され許したのだから、あと1日は話を蒸し返すことはせず、気持ちを切り替えて楽しく過ごしたいと、明るくふるまうビャアン夫婦だったのだが、やはり、パトリック夫婦の言動には、看過できない部分が目についてしまうのだ。
(5)例えば、パトリックの、息子アーベルへの扱いが、傍目にも無視しがたいほど暴力的かつ冷淡で、おとなしいアーベルが可哀想でならない。
それでなくても、パトリックが言うには、アーベルは「先天性無舌症」だとかで話すことができないためか引っ込み思案で、いつもビクビクしているような様子だし、夜にはうなされることも多いのだ。
それでビャアンが「そんな言い方をしなくても」と、パトリックを窘めるのだが、パトリックは「これがうちの教育方針なんだ。口を出さないでくれ」と言い、まったく耳を貸す気のない様子なので、そうまで言われてしまうと、それ以上の口出しはできなくなってしまうのである。

一方、パトリックの妻のカリンは、そんな夫の息子への態度を、まるで気にした様子はなく、さらには、ルイーセに断りもせず、来客者の娘であるアウネスに対し、まるで自分の娘にでも言うように「テーブルにお皿を並べて」「それじゃあ、フォークのナイフが逆でしょ」などと、ビャアン夫婦の面前で、つけつけと命じたりする。
そのため、楽しくやろう、やれるはずだと思っていたルイーセも、またもや我慢ならなくなって「人の娘に、命令するようなことは止めてちょうだい」と声を荒げて叱責するのだが、カリンの反応は「あら、ごめんなさい」と、悪いことをしたとは少しも思っていないような様子で、かたちばかりの謝罪を返すだけなのであった。

その夜、夜中に目を覚ましたビャアンは、そのまま妻と娘の眠るベッドから起き出して、これまで入ったことのなかった別棟の小屋の様子を見に入り、その2階部屋に上がったところ、壁一面に写真が貼られていることに気づいた。
どうやらそれは、いずれも旅行記念の家族写真のようで、自分たち夫婦もイタリア旅行の際にパトリック夫妻と撮ったような、似たような家族写真が、びっしりと貼られているのだ。
「こんなに頻繁に旅行しては、記念写真を撮っているのか」と呆れながら、その写真を一枚一枚よく見ていくと、パトリックは、ある奇妙な事実に気づく。それは、パトリック夫妻と一緒に写っている子供が、写真によって違うのだ。男の子のものもあれば女の子のもあり、そのほとんどが別の子供たちなのだが、それがいずれも、まるで3人家族のように、寄り添いあって写っている。そして、さらによく見ると、旅先で知り合ったと思しき家族の写真に写っている子供が、別の写真ではパトリック夫妻の子供のような様子で3人で写っており、そんな家族写真がたくさんあるのだ。まるで、子供だけが、二組の夫婦間をスライドし、それがくり返されたかのように見えるのである。
ビャアンは、この写真の意味するところを理解できず、混乱しながらも恐怖を伴ったショックを受け、次の瞬間、直感的に「娘に危機が迫っている」と思い、パトリック夫妻のことをさらに探るべく、また別棟の小屋を中を覗いたところ、そこに置かれていた小型プールの中に、子供の死体がうつ伏せになって浮かんでいるのを発見するのである。
ビャアンは、慌てて妻と子供を起こし、二度目の「夜逃げ」を決行する。
写真が意味すること、そして子供の死体が何を意味するのかは、はっきりと理解できていたわけではなかったが、娘と自分たちの身に危険が迫っているということだけは直感できたので、今回もパトリック夫婦には黙って、同家から自家用車で逃げ出したのである。
ところが、しばらくすると、ビャアンは、自分たちの車を追尾してくる車の存在に気づく。ヘッドライトのせいで、車の形や運転手の姿まではわからないが、どう考えてもパトリックが追いかけてきたとしか思えず、ビャアンはその尾行車を撒くべく横道に入っていくのだが、その先で、ぬかるみにタイヤが取られて、身動きが取れなくなってしまう。
このままでは、パトリックたちに見つけられるのは時間の問題だと焦るビャアンだが、幸いにも、数百メートルほど離れた場所に家の灯が見えたので、そこへ助けを求めに行くことにした。妻と娘にはドアロックをして、何があっても絶対に外へは出ないようにと言い含め、彼方に見える山中の一軒家を目指して、ビャアンは走り出した。
ところで、この段階ではまだ、ビャアンは、今回再び夜逃げした理由を、妻には話していなかった。彼が知った事実を説明している暇など無かったのと、彼が漠然とながら感じている恐ろしい事実を妻や娘に伝えたところで、無用に怯えさせるだけだと考えていたからである。
ビャアンが、やっとの思いでたどり着いた一軒家は、しかし空き家であった。
灯火が点けられていたのは、家の外で、防犯的な意味合いで、敷地内を照らすためのものだったようだ。だからこそ、窓の明かりではなく、家そのものが遠くから見えたのである。
やむなく、車にとって返したビャアンだったが、すでに車内には、妻と娘の姿は無かった。二人がパトリック夫妻に拐われたものと思い絶望したビャアンは、月明かりの下で妻と娘の名を呼び「返事してきくれ!」と泣きながら叫ぶしかなかった。
ところが、そんなところへ1台の車のヘッドライトが近づいてきた。
パトリックらが戻ってきたのかと、身構えるビャアン。目を凝らせば、たしかにその車はパトリックのものであり、彼が運転をし、後部座席には、ルイーセとアウネスが乗っていた。
車が停まったので、あわてて駆け寄り、後部座席の妻に「どうしたんだ?」と尋ねると、妻はいたって落ち着いた様子で、パトリックの家に電話をして助けを求めたと言うのである。そして、運転席のパトリックも、ビャアン一家がまたしても「夜逃げ」したことについて問おうとはせず、ひとまず引き返すしかないと言うので、ビャアンも、いったんはパトリックの車で引き返すしかないと諦めたのであった。
ところが、走れども走れでもいっこうにパトリックの家に帰り着かない。異変に気づいたビャアンが「どこへ連れていく気だ。車を止めろ」と騒ぎ出すと、ついにパトリックとカリン夫妻はその本性をあらわし、ビャアンを殴りつけて黙らせると、そのまま運転を続け、やがて、山中のある場所に車を停めると、そこへ対向車のヘッドライトが近づいてきて、正面に停車する。そして、その車から降りてきたのは、先日のベビーシッターの男であった。
パトリック夫妻は、後部座席にいたビャアン夫妻から力づくで娘を奪い、しかもその娘の舌を、ハサミで切ってしまう。
その非情な暴力の前に、ビャアン夫婦はなすすべもなく娘を奪われ、娘は迎えの車で一人連れ去られてしまう。

一方、残されたビャアン夫妻は、パトリック夫妻の車で少し移動させられた後、夜が明け始めた、まだ極寒の山の中で車から降ろされ、パトリックから「そこで服をぜんぶ脱げ」を命じられる。
力づくで娘を奪われ、もはや抵抗の意志をすっかり挫かれてしまったビャアンとルイーセは、言われるがままに素っ裸になる。するとパトリックは、その採石場跡の巨大なくぽみの中へ降りていけと命令し、ビャアン夫婦が言われるままに、深さはせいぜい5メートルほどの、その巨大なくぼ地の底へと降りる。そして、その様子を見届けたパトリック夫妻は、くぼ地を見下ろす縁(へり)に立って、いきなり下の二人に目掛けて、子供の頭ほどもある石を投げつけはじめた。それが頭に当たったルイーセがまず倒れ、それを庇おうとしたビャアンにもすぐに石が当たって昏倒する。だが、パトリック夫妻は、二人の息の根を止めるつもりで執拗に石打ちを続け、ビャアン夫妻は、山中の採石場跡のくぼ地の底で、血まみれになった裸のまま、添い寝するように並んで、なすすべももなく死んでいくしかなかった。
そして後日、見知らぬ夫婦の運転する車の後部座席で、ウサギのぬいぐるみを抱いたアウネスが、まるでその夫婦の娘のようにして、暗い顔で座っている様子が映し出される。無論、黙ったままでだ。
○ ○ ○
つまり、この作品は、いちおうのところ「ホラー」は「ホラー」なのだが、いわゆる「ホラー映画」的な「超常現象」や「狂人(サイコ)」が描かれるわけではない。
描かれているのは、現実にも存在している「人身売買の犯罪者」たちで、彼らはその目的のためなら殺人も辞さないという、冷酷な「常習的凶悪犯」だった、だけなのである。
したがって、この作品が描いているのは、普通のホラー映画が描くような「非人間的なバケモノに対抗して、最後は、まともな主人公たちが、勝利をおさめる」とか「逃げ延びる」とかいったお話ではなく、「非情な犯罪者の欺瞞と暴力の前に、なす術もなく殺されてしまう、善良な普通の人」たちの姿なのだ。
本作が、昨今の洋画では極めて珍しい、『胸騒ぎ』というシンプルな日本語タイトルなのも、この映画を見終えてからなら「なるほど」と思わざるを得ないものだった。
ビャアン夫妻は、パトリック家を訪れて早々から、数々の「引っ掛かり」を覚え「嫌な感じ」を受けていた。
だからこそ、一度はルイーセが、もう我慢ならないと、黙ってパトリックの家を出ていくことを決意し、それを実行したのだが、愛着あるぬいぐるみを失って悲しむ娘が可哀想で、結局はパトリックたちの家へと引き返してしまった。
また、引き返したあと、案の定「どうして?」と執拗に問われて、ついに本音をぶちまけたところ、意外にもパトリック夫妻から素直に謝罪され、「もう一度チャンスをくれ」と乞われて、つい彼らに情けをかけて許してしまう。
一一その結果が、娘は舌を切られて売り飛ばされ、自分たちは虫ケラのように、無抵抗なまま殺されてしまうのである。
ビャアン夫婦の何が悪くて、こんな目に遭わなければならなかったのだろう?

無論、普通の意味では、ビャアン夫婦には、何の非も無かったどころか、きわめて常識的かつ紳士的な態度に終始したのだが、むしろそこを、パトリック夫妻という「犯罪者」につけ込まれたのである。
つまり、この作品が、問わず語りに語っているのは、「良識ある行動も結構だが、身の危険を感じた時などは、手遅れにならないうちに、理屈抜きで、何をおいても、とにかく逃げ出せ。それが生きるためには必要な知恵なのだ」ということであり、この忠告の裏にあるのは「私たちは、あまりにも文明化され過ぎてしまっており、生き残るための生存本能を鈍らせてしまっているのだが、そろそろそのことに気づくべきだ」と、おおむねそんな警告である。
そしてこれは、私がしばしば書いていることでもあれば、レビューにおいて実践していることでもある。
まず「私がしばしば書いていること」とは何なのかというと、要は「駄作は駄作だと言うべきである」ということだ。
この言葉は、言い換えれば「嫌なことは嫌、嫌いなものは嫌いだと」言えなければならない、ということだ。なぜなら、周囲や他人の顔色ばかりを気にして「良い人」ぶろうとばかりしていると、人はそうした「建前」に縛られてしまい、自身の正直な思いに忠実な行動を採れなくなってしまうからだ。しかしそれでは、結局は「後悔することになるぞ」ということなのである。
パトリックに「夜逃げ」した理由を追及された際、ビャアンは、その問いに「誠実」かつ「パトリック夫妻を傷つけないように」答えなければならないと、自己を過剰に縛ったがために、まるで「疚しい」ことでもしたかのように、口籠らざるを得なかった。
だが、そうではなく「居たくなくなったから(帰りたくなったから)帰るんだよ。その理由は、あなたが自分の胸に手を当てて考えろ!」と、そう率直な捨て台詞のひとつも言い放って、断固たる意志を示せていたならば、パトリック夫妻につけ入る隙を与えはしなかっただろう。
だが、ニ人は「謝罪する者を許さない」という態度がどうしても採れなかった。ビャアン夫婦の中には「反省する者には、寛容に赦しを与えるべきだ」という「世間の良識」があり、それに背いて「冷たい人・非情な人」とは思われたくはないという気持ちがあったから、つい許してしまった(ビュアンが「良い人であろうとすることに縛られている自分が、苦しくなることがある」と、本音を漏らすシーンもある)。
しかし、パトリック夫妻が、そう簡単に反省して変われるような人間なのかどうかくらいは、ビャアン夫妻はすでに実感的にわかっていたはずなのだ。だが、彼らは「常識的な体裁」に縛られて、「本能の警告」をみずから押さえ込んでしまったのである。
無論、私自身も含めて、いつでも好き勝手に、思ったとおりに物が言えたり、行動できたりするわけではない。
けれども、だからと言って、人に「悪く思われたり」「嫌われたり」するのが嫌だからと、他人の顔色ばかりをうかがって「自粛」したり、信用できない相手にさえ「迎合」するようなことを言っているうちに、人は「言っても良いこと」「言う権利のあること」「言うべきであること」さえも、「怖くて言えなくなってしまう」のである。
つまり、所詮は「ウサギ」でしかないあなたが、「トラ」が近づいてくるのに気づき、危険を感じながらも「でも、ここで私が、いきなり背中を向けて走って逃げ出したりしたら、トラさんはきっと気を悪くするに違いない。なぜなら、私の態度は、話したこともないトラさんのことを、危険だと決めつけてかかったも同然のものだからだ」と、そう考えてしまうのだ。
だから、ウサギのあなたは、そのトラと会釈でも交わして、自然にすれ違おうなどと思うのだが、無論これは「愚かなウサギ」の発想であり、トラにとっては「飛んで火に入る夏の虫」でしかないのである。

「言わないでおけば、ひとまず角は立たないし、そうして時間稼ぎをしているうちに、目の前の困難は、なんとなくうやむやになってしまうだろう」などと、ついつい私たちは、目の前の問題から目を逸らせてしまいがちだし、特にその傾向が「日本人」には強い。なにしろ、古来「和をもって尊しとなす」ことが、骨の髄まで染み込んでいるので、事を荒立てるのを何よりも恐れてしまい、対決すべき時にもその対決すべき難問から目を逸らして、現実逃避してしまうのである。
しかし、そうした甘ったるい対応で大禍なく済ませられるのは、あくまでも「悪意(害意)のない者」との関係に限られるのであって、相手が自覚的に、他人を「隙あらば、食ってやろう」と考えているような場合、おとなしくつき合っていれば、いずれそうした犯罪者の餌食になるしかない。
そして、それが嫌なら、相手と対決してその目的を挫くか、さもなければ、その相手から徹底的に逃げるかしかないのだ。
だが、多くの人は、自分の方が正しく相手の側に非があるのが明らかな場合でも、それが大きな問題だと思えなければ、事を荒立てることの方を恐れ、「触らぬ神に祟りなし」だと、事なかれ的に物事をうやむやにしようとしてしまいがちだ。
また、そうした「誤った状況認識」に加えて「実力を伴わない自尊心」のせいで、相手から逃げ出すということができなくなってしまう。
「誰からも悪く思われたくない(それは可能なことだ)」という調子の良い考えをいっときも捨てられず、そのため、相手を「嫌いだ」とか「信用できない」とか「恐い」といった「負の評価」を、言葉や態度で示すことが出来なくなっているので、そんな人は、チャンスがあっても、犯罪者から逃げることもできない。
「逃げる」というのは、相手に対する自身の「無力」を認めることだからこそ、それを認めたくはない「愚かなウサギ」は、危険な相手を目の前にしても、必死に平静を装おうとするばかりで、どうしても逃げることができないのだ。
「ここに止まってでも、なんとかすることもできるはずだ」などと、身の程知らずで無根拠な自己欺瞞に陥って、みすみす逃げる機会を逸してしまうのである。
一方、私が「レビューにおいて実践していること」とは何かというと、要は、レビューの読者である「お前らは、自分でそう思っているような賢い人間ではなく、実際には馬鹿ばっかりだ」という、過酷な現実の「突きつけ」作業である。
そんな無根拠な自己陶酔から、一刻も早く「目を覚ませ」と、私は読者の頬を叩いて回っているのだ。
私が、あれほど始終「これこれこういう理由で、どいつもこいつも馬鹿ばっかりだ」と書いているのだから、それに内心で腹を立てた人が相当数いるというのは、間違いのない事実であろう。「私は、あんたの言うような馬鹿じゃない」と、いちおうはそう思って、不快な思いをしているはずなのである。
ところが、私のこうした「剥きつけの批判(低評価)」に対して、正々堂々と「反対の論陣を張る者」は、ただの一人も出てこない。
たまに出てきても、それは「捨てアカウントの匿名者(ヘタレ)」ばかりなのである。
いったい彼らはなぜ、堂々と私に反論することができないのか?
それは無論、彼らは、私と論戦になれば、自分が負ける公算が高いと感じているからである。
だから、戦うことはせず、そのことによって、自分の「実力の無さ(弱さ・非力)」に直面することを避けて、「やってやれないこともないけど、そんな泥試合、やるだけ無駄だよ」などと自分に言い訳をし、自身を誤魔化すのである。
だからこそ、堂々と反論したりはしないのだ。自分の自己欺瞞の仮面が(公衆の面前で)私にひき剥がされるのが、何よりも怖いのだ。
しかし、犯罪者というものは、そういう人間の「弱さ」を敏感に察知して、そこにつけ込んでくる。悪魔はいつでも、人の弱みにつけ込んでくるものなのだ。
良心や倫理観の麻痺した、弱肉強食の野獣も同然である「犯罪者」たちは、だからこそ、「良識」を持たないその動物的直感によって、他人の弱みを見抜き、仮面の下の素顔を見抜いてしまう。
そして、さもその仮面を真に受けているかのような素振りで接近し、やがて仮面の内側まで、遠慮なく踏み込んできてしまうのである。
例えば「あなたは、本当に心の優しい、良い人だ」となど言われてしまうと、多くの人はそう言う相手を「冷たく遇らう」ことができなくなる。
「あなたは、筋を通す人だ」と言われれば、「明確な理由を示せなければ、嫌なことでも断れなくなる」といった具合だ。
こうした「凡人でしかない善人」たちは、猛獣を前にしてさえ、人間としての「体裁」に固執して、逃げ遅れてしまう。
例えば、「あなたは良識ある人間ですよね。ならば、テロリズムは何としても認められないはずですよね。あなた自身も日頃、そのようなことをおっしゃっているわけですし」などと言われて、「いや、御説ごもっともなんですがね、しかし、安倍晋三が殺された時には、ザマーミロと思ってしまいましたよ(笑)」などと臆面もなく答えられる人は、そう多くはないはずだ。
だが、形式論理の「建前」に捉われることなく、実感や直感に即して、良い意味で「豹変」できてこそ、真の「君子」なのである。
また「作家だって人間なんですよ。あなたのそれのような、容赦のないこき下ろしに遭えば、死にたくなる人も出てきて当然ですが、あなたはそれでも平気なんですか?」と言われれば、私は「死なれて平気ではないけれども、その作家に思い当たる節があって、それで死にたいと思って死ぬのなら、それは仕方のないことですね。それはその人の勝手ですから。そもそも貶されるのがそんなに嫌なら、作家なんぞやめちまえばいい。それで楽になれるよと、そう伝えてください」と、私ならそのくらいのことは言うのだが、これを言える人も多くはないはずだ。
なぜ、このように言えないのかといえば、それは多くの人が、自分の身の丈に合わないほど、自分を「人格高潔、性格円満、頭脳明晰、首尾一貫」な人間に「見せよう」とするからなのだ。
しかし、できないことを、やろうとするところに、無理が生じ「隙」が生じるので、犯罪者は、その隙を突いてくるのである。
もちろん、社会は「人格高潔、性格円満、頭脳明晰、首尾一貫」であることを求めてくるし、人は、可能な範囲において、それを目指すべきではあろう。
だが、それは「強制」でもなんでもなく、「一般的な理想」に過ぎないし、そうでなければならないという「義務」など無いのだが、しかし日本人の多くは、「同調圧力」に迎合して、それを目指すのが「当然」だと思い込んでしまう。
そして、そうなれば当然、「理想どおりには生きられない人間」には(ビュアンがそうであったように)「隙」が生じる。「理想と現実のギャップ」という、誰にも不可避な「隙」が、どんどんと広がっていくのだ。
本作『胸騒ぎ』に描かれるビャアンとルイーセもそうだ。
彼らは、常識的な意味で「きわめて良い人」なのだが、実はそれが「足枷」になってしまい、必要な行動をとることができず、みすみす犯罪者の餌食になってしまった。
当然のことながら、これと同じようなことは、現実においても、いくらでも転がっている。
「子供の人身売買」は、今の日本にもある犯罪だし、犯罪者の口車に乗せられ、信用した相手の手にかかってむざむざ殺されるというのは、「那須町夫婦焼損遺体事件」が記憶に新しい、現在も捜査中の事件だ。

また、いわゆる「良い人」がまんまと餌食になるという点では「頂き女子りりちゃん事件」も、つい最近の事例だ。
この事件の被害者が合計数千万円もの大金を、借金のために体を売らなければならないと訴えた「リリちゃん」こと渡邊真衣に対し、複数回にわたって「貢ぐ」に当たっては、必ずどこかの段階で「これはおかしい」「騙されているのではないか」という気づきの機会があったはずである。だが、そこで逃げ出せなかったのは、なぜか?
それは「疑っては可哀想だ」「私は彼女を信じると決めたんだ」「いまさら見捨てるなんてことできない」といった、いかにも「立派すぎる」自己正当化をしてしまったからであろう。自分が「愚かなカモ」だと認めることができず、そのために「逃げ遅れてしまった」のである。

そんなわけで、本作『胸騒ぎ』の、嫌な嫌なラストを、一人でも多くの「日本人」に、その目で見てほしい。
そして、「これは私の姿なんだ」という気づきを得てほしい。
あなたが、「相手の顔色」や「場の空気」に呑まれることもなく、必要とあらば、「嫌なものは嫌」「駄作は駄作」「あなたが死のうが生きようが、それは私の知ったことではないから、勝手にすればいい」と、そう言い切れる人間ではないのなら、本作を見て、その惨めな死に方を「疑似体験してみる」必要があろうし、それは非常に価値のある体験なのだ。
あなたは、裸の体に石を投げつけられて死に、ひと気のない山の中で、寂しく腐って消えていくのである。
なお、私が以前、下の映画レビューで書いたことも、結局は同じことなのだと言えよう。
だが、本作『胸騒ぎ』とは違い、その映画『妖怪の孫』の場合は、広く知られた現実問題を扱った「ドキュメンタリー映画」だという点が、なにより重要なことだったのである。
(2022年5月16日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
