
椎名麟三 『深夜の酒宴・美しい女』 : 転向作家の 「個人的な救い」
書評:椎名麟三『深夜の酒宴・美しい女』(講談社文芸文庫)
椎名麟三に興味を持ったのは、文芸評論家・井口時男の著書『悪文の初志』で、椎名が興味ぶかく扱われていたからであり、椎名がキリスト教信徒であることを知ったからでもある。したがって、椎名麟三を読むのは、これが初めてだ。
ひとまず、手に入りやすい講談社文芸文庫の2冊、本書と『神の道化師・媒酌人』を入手したが、どうやら本書収録作の方が代表作とされているようなので、こちらを先に読んで椎名の雰囲気をつかみ、その上で、「キリスト教批判者」として椎名に興味を持った私にとって、本命となるであろう『神の道化師・媒酌人』を読もうと、そう考えた。

『焼け残った運河沿いの倉庫を改造したアパートに蠢く住民達。瀕死の喘息患者、栄養失調の少年、売春婦の救いのない生態を虚無的な乾いた文体で描き、「重い」「堪える」の流行語と共に作家椎名麟三の登場を鮮烈に印象づけた「深夜の酒宴」。
電車の運転の仕事を熱愛する平凡な男が現実の重さに躓きつつ生き抜く様を特異なユーモアで描く「美しい女」(芸術選奨)。
戦後の社会にカリスマ的光芒を放った椎名文学の代表作2篇。』
(本書帯文と、カバー背面の内容紹介文)
本書に収められているのは、長めの短編「深夜の酒宴」と、長編「美しい女」である。
「深夜の酒宴」は、椎名がキリスト教と出会う以前の作品であり、戦前の「転向体験」が色濃い、たいへん暗い作品である。
『 かつて若き大坪昇(※ 椎名麟三の本名)を死によって威嚇した国家は、まもなく国民全体を死に向けて押し出す戦争を開始した。敗戦は、死の脅迫からの解放を意味したはずだが、「深夜の酒宴」の世界にはいまだ死の気配が瀰漫している。死は具体的な飢えとなって貧乏人にまとわりつく。実際、作中では二度、葬儀とも呼べぬみすぼらしい葬儀が行われる。だが、死は根本的には観念である。この世界が暗く閉ざされているのは、語り手たる「僕」の世界認識が暗く閉ざされているからだ。「僕は憂愁という観念なのである。」「憂愁」の背後には、 転向した共産党員であり、友人を運動に引きずり込んで死なせてしまった罪を叔父に責められつづけている「僕」の過去が隠れている。』
(P335〜336、井口時男「解説」より)
椎名の父は、元警察官であった。両親の夫婦仲は悪く、椎名の母は自殺未遂を起こしており、その直後に父親は警察を辞して『鉱業会社の庶務課長』(P346「年譜」より)に転じている。
やがて父母は別居することとなり、母が子供たち3人を連れて出て、父の援助で生活することになる。このころ母は『当時流行の、後藤静香の雑誌「希望」を愛読、修養団の婦人部支部長になった』(前同)。
その後、父親が相場に手を出して破産し、その援助が途絶える。学業成績優秀だった昇(椎名麟三)は、父の約束不履行に対する談判に出かけるも相手にされず、そのまま家出をして、果物屋の小僧や見習いコックなどの仕事を転々とする中で、社会主義に接近していく。18歳時に、母の自殺未遂をきっかけに、今の「山陽電車」に入社し、そこで労働運動に参加。2年後には日本共産党に入党している。
このように見てくると、ここまでで既に、「深夜の酒宴」や「美しい女」に登場するもののあらかたを経験していると言えるだろう。つまり「警察」「自殺(未遂)」「社会主義運動」「貧乏」「電鉄会社勤務」といったところだ。
この段階ではまだ「キリスト教」は登場していないけれども、しかしその「前身」となるのが、母親の『当時流行の、後藤静香の雑誌「希望」を愛読、修養団の婦人部支部長になった』という部分ではないだろうか。つまり「理想主義的な観念への傾倒」ということである。
本書解説者の井口時男は、椎名麟三という人を象徴するような言葉を、解説「「ほんとうにほんとう」ということ」の冒頭で、次のように紹介している。
『 椎名麟三は『私の聖書物語』の中でおかしな「実験」をすすめている。あなたが恋人でも家族でも、誰か愛する人を持っているなら、部屋で一人きりになったときに、自分はその人を「ほんとうに」愛しているだろうか、「ほんとうにほんとうに」愛しているのだろうか、と自分自身に問いつめてみたまえ、というのである。「だんだんほんとうには愛していない気がして来るから妙である。反応のひどいひとは、ふかい空虚におそわれて、そのひとへの愛を失ってしまうことさえ起こる。」』(P331)
まあ、普通に考えれば、そういうことになる。
というのも、人間は「相対的な存在」であって「ほんとうにほんとうに」と突き詰めていけば、自分を見失ってしまうのは、むしろ当然だからだ。
「ほんとうにほんとうに」の先にあるのは「絶対」であり、人間は決して「絶対」を捉えることができないのだから、自信をなくすのも当然のことなのである。
で、なぜこの奇妙な「問い」が出てくるのかというと、それは椎名に、痛切な「転向体験」があったからである。
「深夜の酒宴」の語り手の主人公である「僕」と、椎名自身の経験とが、どれだけ重なるものなのかはわからないけれども、少なくとも椎名が、自身の体験を象徴的に描き出したのが「僕」の体験であろうというのは、まず間違いないところだ。そうでなければ、書く意味がない。
この「僕」は、「治安維持法」によって違法化されていた「共産党」員として、つまり「赤」として警察に逮捕され、その厳しい取り調べ(拷問を伴ったものであったろうが、ここではそう明記されていない)のなかで、自分は「仲間の命のために、自分の命を捨てることができるだろうか」と自身を問い詰めたときに、「それはできない」「生きたい」という思いを否定できず、ついに転向を受け入れてしまった、というような心内語を語っている。
「僕」は、自らが信じた「社会主義の理想」や、その「大切な同志」のために死ぬことの出来ない、不徹底な人間であることを知って絶望し、身の程を知って転向したと、大筋このような自己認識なのである。
だから、「深夜の酒宴」に描かれる敗残の「僕」は、生への希望を完全に失った、しかし、自ら死を選ぶことさえできない人間、生ける屍の如き人間として描かれ、彼を取り巻く世界も、生きるに値しない絶望的な世界のように、「僕」の主観を通して描かれている。
一一「深夜の酒宴」とは、そんな絶望感を描いた作品なのである。
それでも、死ねない椎名は、生きてゆかざるを得なかったので、そうした状況を乗り越えるための思想を欲して、実存思想系の思想家の著作を読むも、それで救われることはなかった。なぜなら、そうした思想は、人間の「実存」を突き詰める思想であり、要は「ほんとうにほんとう」を問う思想だったからである。
椎名にとっては、その方向性は、すでに「行き止まり」でしかなかったからだ。
ところがその後、椎名はドストエフスキーと出会い、そこに「希望」を見出すことになり、同時に「文学」を志すことになる。

ドストエフスキーの何が、椎名に「救い」をもたらしたのかといえば、それはそこに、「突き詰められない人間でも、生きている価値はある」ということが語られていたからである。
たとえば(ここは私の推測だが)『カラマーゾフの兄弟』における、長兄ドミトリー・カラマーゾフが、そういった人物だろうし、椎名はそうした人物像に、自身を見出したのではないか。
自身は、イワン・カラマーゾフのような「突き詰める人間」には決してなれない「不徹底な人間」だが、ドミトリーであってもかまわないのだという「救い」を、ドストエフスキーの中に見出したのではないだろうか。
そして、ドストエフスキーの根底に、すべてを受け入れるものとしての「キリスト教」の思想を見たのではないか。だから後に、椎名麟三は、キリスト教に帰依することになるのだろう。これは、いわば必然的な成り行きだったのである。
『この地上にあっては、「愛」も「自由」も「幸福」も相対的で不十分な偽物でしかありえない。しかし、「ほんとうにほんとう」のものとしての「美しい女」は、地上の偽物性や相対性を裁き糾弾するのではない。むしろそれは、まがい物たらざるをえない地上の存在の卑小さや滑稽さを許容し、ゆるめ、やわらげてくれるものだ。裁き糾弾するのは旧約の神だが、ゆるめ、やわらげてくれるのはキリストの「ユーモア」である。』
(P343・井口時男「解説」より)
だが、ここで気をつけなくてはならないのは、椎名麟三の見ている「キリスト教」は、自身に都合の良い「キリスト教の一面」でしかない、という「事実」である。
本書収録の2篇の中では、「キリスト教」という言葉は出てこず、ましてや「カトリック・プロテスタント」という区別には、一切ふれられていない。ただ、井口の「解説と年譜」の中で、これらの言葉が使われているだけなのだ。
つまり、椎名麟三の考える「すべてを受け入れる」ものとは、現実の「キリスト教会」ではなく、「物語(フィクション)」としての「イエス・キリスト」でしかない。だからこそ、同じ「キリスト教」であっても、絶対「正統主義」を掲げる「カトリック教会」とは、どう見ても折り合いがつかない。
当然、椎名が洗礼を受けたのが、「プロテスタント」(の一教派の)教会だったというのは、理の当然だったのだ。
個々の信徒と「神」の間で、実質的な「仲保者」としてはたらく「神の体たる教会」は、絶対に必要なものであり、「教会」を抜きにしてキリスト教信仰はない、というのが「カトリック」の信仰なのだが、その「カトリック教会」の支配から独立した「プロテスタント」の場合は、個々の信徒は「神」と直接つながるものであり、「神」は、「教会」にいるのではなく、自分の「心の中」にいる存在だと考えられ、「神と私は、一対一の関係」なのである。すなわち「近代神学」だ。
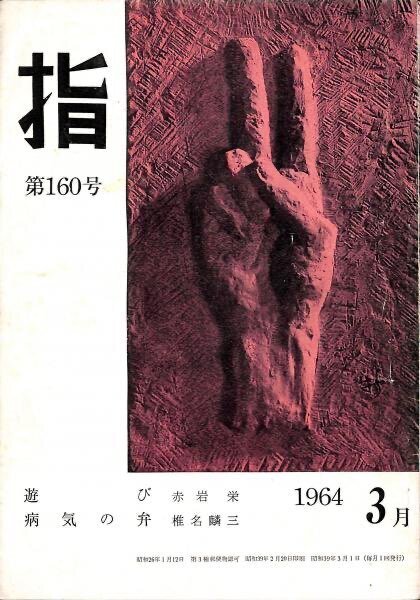
だから、椎名のキリスト教は、どうあっても「プロテスタント」でなければならなかっただろうし、事実、「美しい女」で描かれる、主人公の中に住む「物事の判断基準としての、(幻の)美しい女」は、椎名がいうところの「ユーモア」を持つ「笑う女」なのである。
その笑い方は、いうなれば「ほんとうに、困った人ね」と、微笑んで許してくれ、受け入れてくれる、「神」的なイメージなのだ。
だから、「美しい女」の主人公であり、電鉄会社に勤める「木村末男」は、次のように主張する。
(1)『 私は、全く不名誉な話だが、一度も本当の自分であったことはない。私は、高等小学を卒業後、そのころ市になったK町の青年学校へ通い、それからこの私鉄に車掌として入ったのだが、車掌として勤務していても、何か自分ではないことをしているという気がするのだった。ことに駅名称呼などで、車内で声高らかに次の駅名を叫んでいるとき、自分が鶏でいまときをつくっているのだ、というような気がするのだった。そしてこの私の精神的な特徴は、そのような意識が私にやってきたとき、一度は神妙にがっかりするのだが、すぐにがっかりしている自分が、ひどく面白く感じられて来るという奇妙なものだった。』(P79)
ここで重要なのは、末男が『一度も本当の自分』(ここでは、漢字表記の「本当」)であったことがないことに気づき『一度は神妙にがっかりするのだが、すぐにがっかりしている自分が、ひどく面白く感じられて来るという奇妙』さだ。
つまり、末男の中にも「本当の自分」になりたいという気持ちはあるのだが、しかし、それは「ほんとう」ではないのだと気づいて、人間の(自分の)愚かさが『ひどく面白く感じられて来るという奇妙な』余裕が生まれてくる、という事実である。
(2)『 私のおかしな真面目さは、仲間から多少軽蔑され呆れられてもいたが、私の仲間との間に決定的な溝をつくるものではなかった。むしろ私は、概して仲間とはうまく行っていたと断言してはばからない。仲間の間には、仕事上のつまらないことから、ひどく感情的になり、たがいに生れない前から仇敵であったように憎み合っているものもいた。だが、私に対しては、どんな行きちがいが起っても、ほんとうに腹を立てる者もほんとうに憎む者もいなかったからだ。私のおかしさに腹を立てている者がいることはいたが、同じ私のおかしさが、彼の腹立ちをゆるめているようだった。』(P82〜83)
これはたぶん、他作品である「神の道化師」にも通づることなのだろうが、要は「本当の人間」らしく「徹して」生きられない自分(末男)は、「ほんとうのほんとう」たる「神」を象徴する「美しい女」に従って生きているから、「本当の人間」という「観念」を生きようとしている人たちには、「不真面目」とか「体制順応的」とか「何を考えているのかわからない」とか「変なやつ」ということになってしまい、時に敵視されることもあるものの、しかし末男が、そうした「本当の人間」的な立場に対し、違った立場の「本当の人間」として対するのではないために、両者は次元を違えて本質的にすれ違ってしまい、まともに敵対することはない、ということなのであろう。

(3)『 私は、その彼女に、まだたたかいの終わったのではないこと、むしろそれははじまったばかりであることを考えて、ときには暗い気持になることさえあった。といって、私は、暗い気持になっても、それになり切ることはしなかった。つまり、はなはだ不徹底な人間であろうとしたのだった。何故なら、不徹底も私の数ある美徳のなかの一つだと思っているからである。』(P232)
『はなはだ不徹底な人間であろうとしたのだった。何故なら、不徹底も私の数ある美徳のなかの一つだと思っているからである。』ということの意味は、彼が、「徹底的」なものとは、「本当の人間」という誤った「観念」から生まれてくる「傲慢」だと感じ、嫌っているからである。
つまり「(神に対して)不完全な人間」という身の程を知っている彼は、「謙遜」な人間であり、すなわちそれが「美徳」だということなのである。
(4)『 私は、自分を反動だ、とは思っていない。私は、ただ相も変わらず単純で無邪気なだけなのだ。ときには、その無邪気さが残酷に見えようとそうなのである。だから私を時代や社会へ結びつけているのは、あのイデオロギイという難しいものではない。労働なのだ。物へじかに手をふれ、物を動かしたり変えたりすることだ。だから私が、電車に関係をもっているかぎり、私がどんな人間であろうと、ちゃんとした立派な社会性をもっているのである。ただ、この私が、反動とまではいわれなくても、保守的だといわれているとすれば、私に、五年先か、たかだか十年先しか見えないからだろう。そして事実、私は、それ以上のことを考えることをお断り申し上げるのだ。だからひとが、一生不幸だとか、いつまでも不幸だなどというとき、私は、情けなくなって、当惑してしまうのである。ことにほんとうの労働者だとか、ほんとうの人間の歴史だとか聞くと、私の心のなかに生きているあのほんとうの美しい女だ、おかしそうに笑い出すのだ。そして私は、その彼女の笑い声が好きなのだ。』(P255〜256)
これは、「徹底的」であることの「観念性」への批判である。
椎名麟三にあっては『イデオロギイ』に代表される「観念性」は、身の程をわきまえぬ「傲慢」なのだ。
人間とは、そういう「観念を弄ぶ」身の程知らずであってはならない。そうではなく『物へじかに手をふれ、物を動かしたり変えたりすること』としての『労働』に典型される「形而下の建設的作業」こそが、人間の身の程に合ったものであって、『イデオロギイ』に代表される「徹底を求める観念」という翼を持ってして、人は空を飛ぶことなどできない。人間は「地に足を付けて生きる」のが正しいのだ。一一と、そういう主張である。
そんな末男だからこそ、他人からは『反動』だと見られてしまうことも、当然ある。
「末男」は、「理想を語り、理想を目指す」ということはしないし、「理想に燃えている人たち」に対する態度は、少なくとも、そうした人たちからは「冷淡」であり「(腹の中での)冷笑的」であるとさえ見えてしまう。
「権力」と闘うこともなければ、「資本家」と闘うことせず、ただ命じられたままに「羊のごとく従順」に、仕事に精を出すだけの「末男」は、「社会改革者」たちの目から見れば、実のところ「現状追認主義」者であり「長いものには巻かれて生きる」だけの「保守」であり、「反動」的ですらある、ということになってしまうのである。
「理想」を目指す「社会改革者」たちは、当然のことながら、先を見越して「現在」を改革しようとする。
「今さえ良ければ、それいい」などという「近視眼」は愚かであり、忌むべきものだ。だからこそ、彼らは、輝く「未来」を建設するために、今を闘うのであり、だから『ほんとうの労働者だとか、ほんとうの人間の歴史だとか』いった、「理想像」という「観念」を、重視する。
だが、末男にすれば、それは身の程をわきまえない「傲慢」であり、人間の困った「業」だとしか感じられない。
彼の中の、「神」としての「美しい女」は、そんな「肩をいからせた勇ましさ」など歓迎しない。「まあ、それも仕方がないわね」と受け入れてはくれるだろうが、少なくとも「好意的に微笑」んではくれないと、末男は、そして椎名麟三は、そう感じ、そう主張しているのである。
○ ○ ○
私自身、「マルクス葬送派」を名乗った笠井潔の「観念批判論」に、大きな影響を影響を受けた人間だから、椎名麟三の「イデオロギイ」批判が、わからないではない。人間は「イデオロギイ」に代表される「観念」に、憑かれるべきではない、ということだ。
それをすると、人は身の程を知らぬ「自我肥大=自己神化」の果てに、人倫を踏み外してしまう恐れが低くないのである。まさにそれが、ドストエフスキーの描いた、『悪霊』に憑かれる、という事態であり、笠井潔の描く「連合赤軍の総括殺人(山岳ベース事件)」なのだ。

だから、私もしばしば、要は「バランス感覚」であり、良い意味での「適当」であり「良い加減」でなければならない、と主張する。
けれども、私の場合は、だからといって、「徹底的」であることを否定しないし、「不徹底」を良しとはしない。
では、どうするのかというと、「徹底的」であることを求めながら、しかし「退くときは退く」「諦めるときは諦める」「できないことはできないと認める」といった「切り替え」を推奨するのである。
椎名のように、頭から「徹底は、悪だ」とするのではなく、「徹底を求めて、徹底にとらわれない柔軟さを持つ」というような、「リアリズム」である。
したがって、私のこうした立場こそが「不徹底」であるという指摘は、まったく正しい。ただし、私の「不徹底」は、木村末男の「積極的不徹底」でもなければ、自己の「転向」に発する反動形成としての「徹底嫌悪」でもない。
そんな、積極的な「徹底性」批判ではなく、「徹底できれば、それに越したことはないじゃないか。ただし、徹底すれば何でも良いというわけではないし、そもそも人間は完璧ではあり得ないのだから、できる範囲で徹底を目指せばいいんだよ」とい、ある意味では、椎名よりも「ゆるい」立場なのである。
つまり、私は、椎名麟三の「不徹底主義」を、批判する。
それは所詮、自己正当化の果ての、「逃げ口上」に過ぎないと。
実際のところ、当たり前に「徹底的」たらんとする人たちの「努力」を、人間の、身の程を知らぬ「愚かさ」として、腹の中では無意識に「嘲笑」している「木村末男」は、あるいは、「神」の権威に安住する椎名麟三は、「保守反動」であると言っても、決して間違いではない。
私は以前、「保守主義の父」と呼ばれる、イギリスの政治思想家エドマンド・バークを批判した際に、次のように書いた。
『バークの強みとは、彼の「人間通」にあったのだと言えよう。
「人間」というものに、過剰な期待を寄せない「リアリスト」という側面に、彼の強みはあったのだ。
しかし、「人間通の現実主義(リアリズム)」というのは、「思想」としては、あまり意味をなさないものである。なぜなら、それは基本的に「現状追認」でしかなく、「理想」を持たず、おのずと「積極的な改善の意志」を持たないからだ。
「思想」というものの存在価値は、現状では「欠点だらけの、人間という生物」を、いかに高めるか、改善するか、という問題について、その可能性と方向性を指し示す点にある。それが必ず成功するとは保証できないけれど、この方向なら、すこしは人間も進歩でき、より「多くの人の幸福」を実現できるのではないか、という「助言」としての力を持つのが、優れた「思想」なのだ。
だから、初手から「人間なんてこんなものだから、現状維持をすればいいのだ」というような考え方は、実際のところ「思想」の名に値しないのである。』
また、私は「左翼」というものの本質を、次のように書いたこともある。
『つまり、ここで私が強調したいのは「左翼の根底にあるのは、弱者への同情と、それを放置する権力への怒り」だということである。「左翼の本質」とは「同情と怒り」なのだ。
では、それに対しての「保守」はどうなのか。
彼らに欠けているのは、まさに「弱者に対する同情と、弱者を放置する権力に対する怒り」である。
だからこそ、彼らが「保守」するのは「既得権益(既成権力)」になってしまう。「既得権益」を守るためには、左翼的な新勢力に妥協しての「変化や微調整」も避けられないだろうが、しかし、それは「弱者(救済)」を意識してのものではなく、あくまでも、社会の主流である自分たちの「既得権益体制」を崩壊させないための「妥協」でしかないのだ。
彼ら「保守」主義者には、「革命でも起きないことには救われない、大勢の弱者(階層)」の存在が、ほとんど見えていないし、そもそも興味が薄いのである。
(そして、一方の「左翼」の場合は、かなりのリスクを犯してでも、大きな「社会的外科手術」を行わないかぎり、金輪際、救われないことのない人たち〈=社会的階層〉の姿が、切実なものとして見えているからこそ、時に「革命」を叫んだりもするのだ。「それ以外に、彼らを救うどんな手立てがあるのだ」と。)』
つまり、どういうことかというと、椎名麟三の「キリスト教に依拠した、人間の身の程を知るという、敬虔主義」は、自己の「転向」を正当化するための「観念」でしかない、ということだ。
椎名は、そうした個人的な「救済観念」にすがることによって、「深夜の酒宴」で描かれたような「救われない庶民」を、描かなくなった。
「美しい女」で描かれるのは、木村末男の同僚であれ、妻であれ、彼らは「庶民=人間」であるにも関わらず、「観念的な高望み」つまりは「神になろうとして」、いわば自業自得で不幸になる人たちであって、正しいのは「末男の方である」ということになってしまっている。
この小説からは、「故なく虐げられた人々」の姿が、ご都合主義的に消されてしまっているのだ。
引用(4)の部分で語られた、「木村末男」の『無邪気』な『残酷』さとは、そうした「虐げられた弱者」を忘れていられる、徹底した「呑気さ」なのである。
したがって、私は「キリスト教作家」である椎名麟三を、いかにもそれらしく「糊塗された保守反動」であると評価する。

もちろん、いつも言うように「私だって完璧ではない」つまり「全能(の神)ではない」のだから、私の見解が「間違っている」という根拠をはっきりと示してもらえるのなら、いつでもこの評価を撤回しよう。
そうした意味で私は、「徹底的」であると同時に「退くべきときは退く」人間なのである。
(2023年7月22日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
