
片岡一竹 『疾風怒涛精神分析入門』 : ラカン的〈自己分析〉
書評:片岡一竹『疾風怒涛精神分析入門 ジャック・ラカン的生き方のススメ』(誠信書房)
非常に面白かった。何が面白かったかというと、本書で紹介されている「ラカン的な精神分析」とは、「私がこれまで、自分でやってきたことを、精緻に理論化したものでしかないじゃないか」と思えた点である。
「現代思想」とか、そっちからジャック・ラカンに興味を持った人は、おのずとラカンの精神分析学理論を、正しく理解する必要があるのだろうが、私の場合は、そうではない。
私の場合は、ただでさえ「難しい」と評判のラカンを正しく理解しようとか、正しく理解できるなどとは、初手から思っていない。では、何を目的に読むのかというと、
(1)おおよその雰囲気がつかめれば良い。
(2)まるごとの理解じゃなくても、なにか私なりに「使える」部分が見つかれば良い。
と言ったところだろうか。
「思想哲学をやっている人」の多くは、まずラカンの理論を教科書的に正しく理解し、その用語を正確に使えるようにならなければ、いう感じでやっているのだろう。だから、私みたいに「おおよその雰囲気がつかめれば良い」なんてわけにはいかない。ラカンの精神分析が実践できるようにはなれなくても(つまり、実践的な理解までは届かなくても)、ひとまず恥をかかない程度に、ラカンを理論的に「正確」に援用できることを目指すのだろう。
だが、私なんかは、少々の誤解があったところで、ことさら「ラカンの名前や用語を持ち出す」わけではないのだから、実に気楽なものなのである。
で、ラカンの入門書として評判の良いらしい本書を読んでみたのだが、前記のとおり、ラカン的な精神分析を難解で縁遠い理論としてではなく、ごく身近なものと感じられたのが愉快だった。これなら、ラカン理論の正確な理解にまで進まなくても、これだけで十分に読んだ価値があったと、そう満足できたのである。
では、具体的にどのあたりが愉快だったのか

○ ○ ○
まず、著者は「ラカンの精神分析」というものの「独自性」を、強調している。
何と比較しての「独自性」かというと、「精神医学」および「心理学」とである。
言われてみれば、たしかに「精神分析」、「精神医学」、「心理学」の3つについて、その違いを、事あらためて考えたことなどなかった。
たしかに字面からしても、これらのものは、微妙にその意味するところとカテゴリーに違いがあるのはわかる。だが、この3つは、それぞれに重なり合いながら、「人間の心という現象に向き合うもの」という点で、共通の地盤に立っているのだろう一一くらいの感じで、あまり深くは考えなかったのである。
ところが、本書著者によると、「精神分析」の中でも、特に「ラカンの精神分析」は、「精神医学」や「心理学」とは、ハッキリと違った、特異な立場に立っているという。そして、それが「ラカンの精神分析」への理解を難しくさせているというのである。
どういうことかというと、一一ここからは、私が理解したことを書くだけだから、ラカンについて正確に知りたい人は、どうか本書に直接当たっていただきたい、と断った上でいうと、一一「ラカンの精神分析」は、精神の「異常を正す(治す)」ことを目的としない、ということなのだ。
言い換えれば、「精神医学」や「心理学」は、精神あるいは心の「異常」を治療することで「正常」に復させることを最終目的としてなされる学問なのである。だが、「ラカンの精神分析」は、そうではない。その目的が違うのだ。
これは、驚くべきことではないだろうか?
少なくとも、私は大いに驚いた。
「精神医学」というのは、その名のとおりで「精神(心)の病についての医療科学」であり、その最終目的は「病の治療」だろう。つまり「病んだ(非正常な)心を、健康(正常)な状態に修復する」ことを目的にしているはずだ。同様に、「心理学」も、「病んだ(非正常な)心を、健康(正常)な状態に修復する」ことを目的として「心の構造を研究解明する学問」であろう。だからこそ、「精神医学」の実践として「精神医療」があり、「(臨床)心理学」の実践として「心理臨床」がある。
しかし、「ラカンの精神分析」(以下「精神分析」と略す)は、「異常を正す(正常にする)」という目的を持つものではないから、「精神医学」や「心理学」とは、本質的に「違う」のだという。
では、実践として行われている「精神分析」とは、何を目的として、為されているのだろうか?
実際、精神分析の場合は、「患者」ではなく「クライアント(相談者)」と呼ぶそうなのだが、その「クライアント」と面談して、話を聞いたり、質問したりして、何やら「カウンセリングみたいなこと(精神分析では「セッション」と呼ぶ)」をやっているが、あれは「病んだ心を癒して、正常に帰す」ということを目的として行われているのではないのか?
「カウンセリング」というのは、おおよそそんなものではないのか? 心に溜まっている「悪いもの」を吐き出させることで、不調を取り除く(治癒する)という、だいたいそんなものではないのか?
だとすれば、「精神分析」というのも、似たような手法で、「クライアント」の心の病いの原因を、解体したり取り除いたりするということではないのか?
ならばそれは、やはり「精神医療」や「心理臨床」と同様、「病んだ心を癒して、正常に復する」ことを目的とした、治療行為の一種ではないのか?
「そうではない。精神分析は、治療行為ではない」と、本書著者は言うのだ。
そして「その点こそが、ラカンの精神分析の特異性だ」と言うのである。
ええーっ? 精神分析は、「治療」を目的としたものではないのか?
では、「クライアント(相談者)」は、精神分析家(「精神分析医」ではないことになるのか?)のもとに、何をしてもらいに訪れるのだろう? 何らかの精神的な苦痛としての「悩み」を解決してしてもらうためではないのか?
まあ、私と同様、普通の人は、こうした疑問を持つのではないだろうか。
では、そろそろ、本書著者の説明する「ラカンの精神分析」の特異性について、私の理解したところをご説明しよう。
「ラカンの精神分析」の特異性は、「精神(心)」の捉え方にある。
まず、「心(精神)」には、「精神医学」や「心理学」がその理論的前提としている、「正常(状態)」というものが「存在しない」、と考えるのだ。「正常など存在しない」と考えるから「正常な状態に戻す(修復する)」という発想にはならない。
では、どう考えるのかというと、人の「心」というのは、「意識と無意識の、常時葛藤状態」である、と考えるのだ。
したがって、すべての人が、大なり小なり、常時「意識されない、無意識の作用による葛藤」を抱えているのだが、その葛藤が大きくなりすぎると、生活に支障をきたすので、そのバランスを取るためになされるのが「ラカンの精神分析」だ、と言うのである。
つまり、「精神分析」を受けたからといって、決して「パーフェクト」にはならない。
人間の心とは、もともと葛藤を抱えた「不安定で不定形のもの(動態)」なのだから、確固とした「本来の完全形」などは存在しない。だから、そんな存在しないものになど、たどり着きようがない、ということなのだ。
そのため、「精神分析」とは、「病の治癒=治療」ではなく、「個性を形成する、意識と無意識の妥協点を探る」営為だ、ということになるのである。
もともと、人間とは、その素質や生育環境など様々な要素によって、「個性的な歪みを持った(それぞれに不完全な)存在」であり、万人共通の「理想的人格(精神構造)」などというものは存在しない。したがって、個々の「歪み(個性)」の範囲内で、そのバランスを取り、「良くも悪くも、あまり無理なく、自分らしく生きられる妥協点」を模索するのが、「精神分析」だというのである。
しかもだ、「精神分析」の面白いところは、分析家がクライアントの話の中から、無意識に抑圧している「問題点(病巣)」を見つけ出して、「これは、これこれが原因で生まれた抑圧だから、あなたはそれを自覚して受け入れれば、それで問題解決だ!」みたいな、「名探偵」ごとき「謎解きによる事件解決」は、してくれない点である。
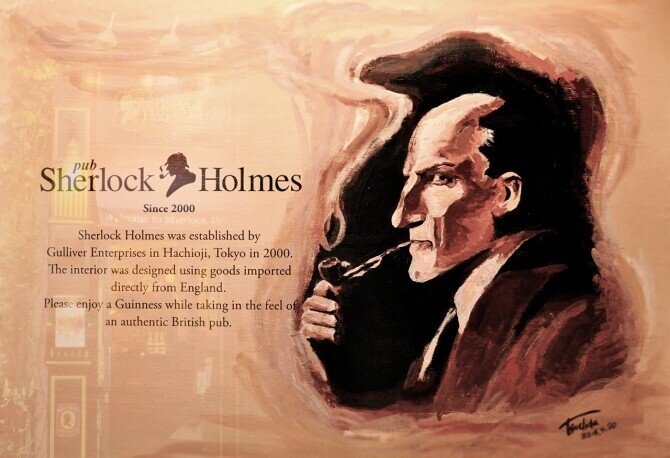
なぜかというと、抑圧されて無意識化しているものとは、他人が(外から)どうにかできるようなものではないからで、それを「何とかする」のは、クライアント本人でなければならないからである。
つまり、クライアントは、分析家に話を聞いてもらう中で、自身が抑圧しているものの存在に自分で気づき、それへの対応を、自分で見出さなくてはならない。
言い換えれば、分析家の仕事とは、その「お手伝いをすること」だけなのである。
だが、この「(上手な)お手伝い」というのがないと、人はなかなか、自分の抑圧しているものには気づけない。なにしろ、自分で抑圧しているものだからだ。
したがって、分析家がやるのは、延々と「クライアントに(自由連想的に)話させる」ということであり、時に「合いの手」を入れて、話の方向性を「ズラす」といったことである。
つまり、分析家がしてくれることといったら、「うん」とは「へえ」とか「ほう」とかいったことくらいで、ごくたまに「それはどういうこと?」と少し積極的な「合いの手」を入れるくらいなのだ。
これは何をしているのかというと、その人が「無意識」に抑圧しているものを引き出すための「緒(糸口)」を探しているのである。
クライアントは、分析家から「とにかく思いついたことを、思いついたままに、ぜんぶはそのまま話してください。恥ずかしい話も、例えば犯罪行為でも、すべて思いついたままに。私は、そのことであなたを責めたりしないし、秘密は絶対に厳守します」みたいな感じで、クライアントに自由連想による「語り」を要求する(ようだ)。

で、クライアントは、自分が楽になるために来ているのだから、この難しい要求に、可能なかぎり応えようとするのだが、しかし、「恥ずかしい」とか「これを話すとヤバイ」といったようなことは、クライアント自身の意識できていることだから、これを話すことは、しんどくはあっても、できないことではない。
しかし、「無意識」に抑圧していることは、クライアント自身が意識できないのだから、隠すも隠さないもなく、話しようがないのである。
では、分析家は、どうするのか?
それは、自由連想での話を聞きながら、クライアント自身も気づいていない「不自然」な部分(話の流れ)に気づいて、そっちへと話の流れを差し向けるのである。なぜなら、クライアントは、無意識に「それ」を避けて話そうとするからだ。
クライアントにして見れば、分析家が、なぜそんな(つまらない、どうでもいい)ところを引っかかったのかはわからないが、とにかくそっち方向で話せと促されたので、そのようにする。
これは、クライアントが「抑圧」しているものの方向へ流れが変えられ、「抑圧されたもの」に少し近づいた、ということだ。
クライアントは、別に「隠しているつもり」はないから、求められた方向に話を進めるのだが、しかし「無意識」の方では、「意識」の気づかない動揺が走り、警戒警報が鳴っている(もちろん、擬人化比喩です)。しかしまた、クライアントの意識は、そんなことには気づかずに、平気で自由連想による話を続けるから、うっかり「触れてはならない部分=抑圧された部分」に関わることを、ポロリと話してしまう。
そこで、その「異質な言葉」に気づいて、分析家は「その言葉は、どうして出てきたのですか?」などと質問すると、うまくいけばだが、クライアントは、それまで自覚のなかった「抑圧していたもの」に、ハッと気づき、その呪縛の存在に気づくということになるのだ。
つまり、分析医は、クライアントに自由連想で話をさせ、それを延々と聞きながら、その「流れ」の中に「不自然=異質」なもの(言葉)を見つけて、そこでそれまでの「無意識的に抑圧された話の流れ」を「切る」のが仕事なのだ。
クライアント自身は気づかないそれに気づいて、「抑圧」の隠された方向へと水を向けることで、やがてクライアントは、自力で「抑圧」に気づき、それを自覚することで、それとの妥協点を自分で見つけて、バランスを取る。
一一こうしたことを目指すのが「ラカンの精神分析」であり、こういうやり方だからこそ、「精神分析」には、数年から十数年といった長い時間が必要となるのである。
で、以上書いたようなことは、本書に書かれていることに、私の「理解」に基づく「肉付け」と「ディテールアップ」がなされている。要は、「盛られて」おり、このままのことが本書に書かれているわけではないのだと、ご理解いただきたい。一一「私は、こう読んだ」のであり、それが「面白かった」という説明である。
○ ○ ○
で、こうした「精神分析」のどこが、最初に書いた「私がこれまで、自分でやってきたことを、精緻に理論化したものでしかないじゃないか」という話になるのかというと、私にとっての「読書と文章書き」は、こうした「精神分析」に「近い」ということに気づいた、という話なのだ。
「本を読む」というのは、「他者」の話を聞きながら、それに対して「色々と連想すること」であると言えるだろう。「ああ、それは、私が考えていたことと同じだ」とか「それは不思議だ」「へえ、なるほど」「そこはどうなのよ?」とか。
これは一見したところ「分析家」の立場にあるように聞こえるかもしれないが、ここで私が言いたいのは、読書とは、「自分の考え」を意識的に語る(主張する)ことではなく、「他者」による「合いの手」に対する受動的「呼び出し」反応だ、ということである。
「本」を読み「他者」と触れることで、私の意識は、その「輪郭」をなす鎧を緩める。そうでなくては、「読書」をしても、何も身につかないのだから、これは当然のことだろう(その意味で、知っていることを確認するばかりの読書では、安心はあっても成長はない)。
そして、読書による「他者」との接触により、輪郭の緩んだ私は、その「他者」が、私にどこまで影響を与えたのかが、今ひとつよくわからないまま、このように文章を書く。
すると、それまで思いもよらなかった「発想」や「連想」が、私の中から出てきてハッキリとした形を成し、それまで自分では気づいていなかった部分が意識化されることで、自身が「抑圧」してきたものの一端に触れることができる、というわけである。
ここまで読んで、「なんだか無理矢理っぽいな」と感じた人もいるだろう。
だが、私の「文章書き」は、基本的に「タブー破り」が目指されている。具体的に言えば「人の書かないことを書く」ために、可能なかぎり「型にはまった書き方」を避け、可能なかぎり「自由」に書く。つまり「自由連想」的なのだ。
だからこそ、私のレビューでは、例えば「プリキュアを論じるのに、柄谷行人が登場する」とか「石牟礼道子を批判するのに〈てへぺろ〉という言葉が使われる」といった「常識破り」が、頻繁に行われるのだ。
また、さらには、本筋とは直接関係のない、連想的に出てきた「個人的な話」や「ちょっと恥ずかしい話」なども、それが「型破りによる本質提示」に役立つと思えば、それを書く。
私はプロの物書きではないから、読者に分かりづらくなろうと、ウケなかろうと、そんなことは大きな問題ではなく、あくまでも目指されるのは「私にしか書けないこと(他の人には書けないこと)」であり「当たり前を超え出る」ことであるから、そうしたものを目指して書いていると、おのずと、自身の「無意識の抑圧」と向き合い、それを揺さぶることにもなるのである。
つまり、私にとっては「読むことと書くこと」が、自分自身に対する「精神分析」になっていたのではないか、と思うのだ。
そのことにより、自分が「本当はどんな人間であるのか」を知り、それとの妥協点を見出すという作業が、「読書と文章書き」の中で行われている。
例えば、私の「大衆憎悪」とか「未来への悲観」などという「好ましくない点」も、それらをやみくもに否定抑圧するのではなく、「読書と文章書き」の中で、相対的に適切な場所を見つけ、そこに位置づけることにより、それらとの妥協点を見出すことができて、「まあ、自分はこんな人間なんだし、その範囲で、結構よくやっているじゃないか」と、自己肯定することもできるようになる。
したがって、「他人」と比べてどうとか、「抽象的な理想像」と比べて自分はどうだとかいった凡庸な悩みは、結局のところ、自分の「特異性」を正しく自覚していないから出てくる、虚妄なのではないだろうか。
それを自覚しておれば、それが良いも悪いもなく、「私」という存在の大前提であり、あくまでもその「個性=特異性」と、よりよく折り合いをつけることしか問題にすることができない、とそう気づくのではないか。
そのことにより、「自己否定的」つまり、過剰に「自己抑圧的」にはならないで済み、精神のバランスを取れるのではないか、と考えるのだ。
そして、こういうことを、常に、あまり意識しないでやってきた人間だからこそ、私は「自己肯定感」が高いのではないかと思うのだ。
○ ○ ○
以上は、「ラカンの精神分析」とはどういうものかという本書著者の説明を、私の場合に引きつけて説明したものであり、ラカンの独特な「思想(精神の構造論)」の説明にまでは踏み込んでいない。ラカン思想の、凡庸な素人解説などしたくはない。ここまで書いてきたことは、本書の前半部分なのである。
もちろん、本書の後半も「なるほど、ラカンは、心というものをそのように捉えており、だからそれに対応するための方法論を構築したのか」と納得でき、その意味で「理論的にも面白い」と言えるのだが、私にとっての面白さは、やはり、本書の前半部分にあった。一一「ああ、私がしてきたことは、これだったのか」のかと気づかされた点で、本書は私にとって、とても励ましになる本だったのである。
一般的な言い方をすれば、本書は「面白い」とか「分かりやすい」といったことになるだろう。だが、それで終わった人は、きっと大切な何かを読み落として、ラカンをわかった気になっているだけなのだと思う。
私は、本書を読んだくらいで「ラカンがわかった」とは思わないが、また少し「私自身がわかった」という点で、本書は、そして「ラカンの精神分析」は、面白い(共感できる)と思えたのである。
(2022年10月1日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
