
國分功一郎 ・ 千葉雅也 『言語が消滅する前に 「人間らしさ」をいかに取り戻すか?』 : ゾンビからミイラへ ・ 〈言葉〉を失った者たち
書評:國分功一郎・千葉雅也『言語が消滅する前に 「人間らしさ」をいかに取り戻すか?』(幻冬舎新書)
「言葉」が失われはじめている。一一これは、ものを考える習慣のある人間には、もはや自明な現状認識であり、本書著者(対談者)の國分と千葉は、大学で哲学を教えながら、近年こうした危機意識につのらせている。
例えば、私が最近、レビューで採り上げた、ヴィトゲンシュタインの研究者である古田徹也の『いつもの言葉を哲学する』も、言葉が粗雑に扱われて、誤った形式化(形骸化)を経て、その意味を失いつつある現状に対する危機意識によって、書かれたものだと言って良いだろう。
私は、この古田書のレビューにおいて、最近の「炎上」事案として話題になった「書評家・豊崎由美による、TikTokerけんご批判」問題を取り上げて、ミステリ作家の綾辻行人と知念実希人を批判した。
知念実希人の方は、見るからに「ネトウヨ」丸出しで、「ネトウヨ」が共感できるくらいにお粗末な作家だから、ここで論ずる価値もないのだが、長年売れっ子ミステリ作家の看板を張ってきた綾辻行人の場合は、知念などより数段上手に「大衆迎合」的でもあれば「時局迎合」的でもあって、言うなれば「俗情との結託」によって人気を保ってきた人らしく、言っていることは、一見「穏当」なのだが、だからこそ、その「無自覚」なまでの「思考停止=言語消失」は、根深い問題を孕んでいると言わざるを得ない。
平たく言えば、綾辻行人ファンや知念実希人ファンに代表される「普通の読者」には、「綾辻行人的問題」が、まったく見えないのである。
だから、ここでは國分功一郎と千葉雅也の問題意識に沿って、綾辻行人が体現している「言葉の喪失=思考停止=ぴえん化」の問題について、再論してみたいと思う。
○ ○ ○
國分功一郎が本書でも中心的に扱うのは、彼の代表作と言っても良い『中動態の世界 意志と責任の考古学』で扱った「中動態」の問題である。
「中動態」とは、文法用語で、
『インド・ヨーロッパ語族の態のひとつ。能動態とは人称語尾によって区別される。中動態と受動態は形態の上で区別されないことが多い。中動態がよく残っている言語にサンスクリット、古代ギリシア語、アナトリア語派などがある。
中動相・中間態などとも呼ぶ。サンスクリット文法では反射態(reflexive)と呼ぶことが多い。』(Wikipedia「中動態」)
といったもので、今は「能動態と受動態」の二極に吸収されて失われたに等しい、中間的な文法形式だと言えよう。
大雑把に言えば、國分は前記『中動態の世界 意志と責任の考古学』において、この現代では失われたに等しい「中動態」的なあり方を再考することで、より正確な世界認識が回復できるのではないか、との問題提起をしている。
「する=能動態」「された=受動態」という二極の「どちらか」ではなく、あり方としての、その中間形式である。
わかりやすい例で言うと、本書で國分は「教える」「教そわる」に対して、「勉強している」を対置してみせる。
「勉強」というのは、対談相手である千葉雅也の『勉強の哲学』を受けてのものだが、「教える」「教わる」は、いずれにしろ「すでに斯くある」状態だが、そうではなく、未確定で現在進行形である「勉強している」という「中動態」的なあり方の中にこそ、ものを考える人間の基本的なあり方としての「自律」があるのではないか、という問題提起なのだ。

一方に、何でも知っている「先生」がいて、もう一方に、まだほとんど空っぽな「学生」がいて、そこには「教える」側と「教わる」側の二極しかない、というのが「能動態と受動態」的な二極世界。
しかし、本当の発展性というのは、この中間の「勉強している」にあり、先生の方は「教える」こと(「教える」ために「勉強しつづける」も含めて)の中で「勉強」し、生徒の方は「教わる」ことの中で「勉強」する。つまり両者ともに「勉強している」という「中動態」的な過程の中に生きているのであり、そこでの彼らは、二極的関係性の中で「完結し硬直して、限定されて」はいないのである。
つまり、千葉雅也の言う「勉強の哲学」とは、決定的な解答(受動的完結)を回避して、それからそれへと学び続け、考え続けることの中に見出されるものとしての「生きた哲学」を、提案しているのだと言えるだろう。
対談者二人の問題意識は、このように「言葉」が硬直せずに、どんどん深められていく、豊かになっていく「生きた言葉」であることを目指しているのだが、残念ながら、今の日本における言葉の現状は、これの真逆を行くものでしかない。
綾辻行人は、「書評家・豊崎由美による、TikTokerけんご批判」問題について、
『小説を読んだ。面白かった。それをみんなに伝えたい。TikTokで紹介した。興味を持って多くの若い人が読んでくれた。……出版界の損得の問題とは別に、これってとても素敵なことだと思うのですね。(2021-12-11 19:01:22)』
『若いころに読んで面白かった本は一生、心に残るものです。大人になってたくさんの本を読んで「物知り」になってからの読書とは、まるで鮮度が違う貴重な体験でしょ。そのきっかけが、同じ若い読者の視線で語られたTikTokの動画であることの、どこがいけないのかしら。……などと。(2021-12-11 19:08:19)』
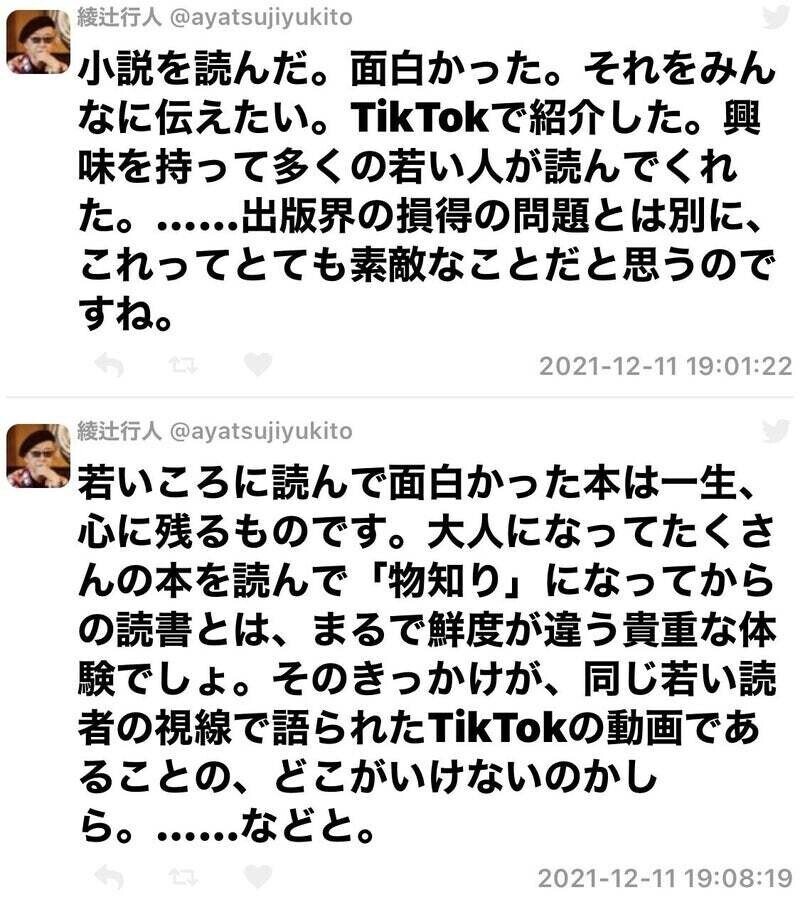
と、「名指し」を避けながら、豊崎を批判するツイートをした。
そして私は、この「いかにも綾辻行人らしい身振り」に嫌悪を感じて、前記のレビューで、次のように批判した。
『まさしく「などと」いう、いかにも「何も考えていないポピュリスト」らしいツイートをしている。
『大人になってたくさんの本を読んで「物知り」になっ』たおかげで「より深い読書の喜びを知った人」にコンプレックスでもあるらしい「子供のまま=非・幼形成熟」の綾辻は、豊崎の「文学の今」をめぐる危機意識が、まったく理解できないのだ。
これは、綾辻行人という小説家自身が、単純に「読めない読者」の一人である、ということに他ならない。
つまり、綾辻としては「面白いものを面白いと言って、何が悪いの?」ということなのだが、この人は「面白いとは、どういうことなのか?」「面白い作品とは、どういうものなのか?」といったことを、ろくに「考えたことがない」のである。
綾辻行人が「面白い」と思う作品を「つまらない」と思う読者もいるし、逆に綾辻行人が読もうともしない本を読んで、豊崎由美が「面白い」という場合なども当然想定され、そのような場合の「意味」も、当然吟味されてしかるべきなのだが、「向こう三軒両隣」に視野の限定された綾辻は、おのずと「面白いものは面白いでしょ」止まりなのである。
そして「売れっ子作家には、そうした自己中心的に呑気な横着さが許される」と、無自覚にも、そう思い込んでいるのだ。だから、適切に「他者」を想定できないのである(例えば、裕福なオリンピック参加選手が、オリンピック開催でコロナ死する人のことを気にしないのと同じである)』
私がここで、綾辻行人の言葉の、何を問題にしているのかと言えば、綾辻がすっかり「真理を悟っている=意味が確定している」つもりになっている点である。
綾辻はここで『出版界の損得の問題とは別に、これってとても素敵なことだと思うのですね。』と、いかにも自分が「金銭的に無欲」であり、「若い読者の喜び」をもっぱら重視しているかのように語っており、事実、本人は、そのつもりなのだろう。
自身の経験として、若い頃に読んで大感動したミステリ作品を、「大人の読者」から「あんなパズル小説が楽しめるのは、若いうちだけだよ」などと心ないことを言われたのを根に持って、意地でも「若い頃」のようであることに「無邪気に」固執した結果、綾辻は『大人になってたくさんの本を読んで「物知り」』になることを拒絶しておれば、それで「大人」にならずに済み、それで自分はいつまでも「鮮度」の高い、みずみずしい感性を保った「若者」でいられているつもり、なのである。
だが、それが幼稚な勘違いであることなど、少し「ものを考える人間」には、自明な話であろう。その自明な話がわからないのは、綾辻行人が「ものを考えることを拒絶した人間」であり、そのことで「若いままでいられる」と勘違いした、グロテスクな「フリークス」の一人だからである。

豊崎由美が「けんご批判」で問題にしたのは、「文学業界の金銭的損得問題」などではなく「文学的価値の存続=知性の存続」の問題であることは、「読める読者」には自明なことだろう。
だが、前記レビューで私が「読めない読者の一人」と呼んだ綾辻行人には、この程度のことすら読み取れずに「大人の考えることなんて、どうせ銭儲けのことくらいでしょ」と、いささか薄気味の悪い「若者ぶり」で『出版界の損得の問題』だと決めつけているのである。
こうした「決めつけ」は、『大人になってたくさんの本を読んで「物知り」になってからの読書とは、まるで鮮度が違う貴重な体験でしょ。』という言い草の、わざわざ括弧でくくって見せた「物知り」という言葉に見え透いている。
要は、綾辻は、「物知り」になることは「大人」になることであり、「大人になること」は「みずみずしい感性を失う」ことだと、そう考えているのだ。
だが、言うまでもなく「何もしなければ、そのままでいられる=余計なことを知らなければ、子供のままでいられる」というのは、幼稚極まりない発想だ。
綾辻と親しいミステリ作家の竹本健治は、実名ミステリ『ウロボロスの基礎論』の中で、そこに登場させた綾辻行人について、作中人物である小野不由美(綾辻の妻)に、
『先程、かつてのように無邪気に書けなくなったと言いましたが、それでもやはり無邪気さというのは綾辻くんの作風の大きな特質だと思いますね。それについては彼自身も、無邪気でありたいという言葉を何度か表明していたようですが。いや、それは作風に限らず、彼のキャラクターそのものからにじみ出るものでしょう。綾辻君はデビュー後たちまち絶大な人気を得て、後続部隊のための大きな道を拓き、結果として新本格ムーブメントを大成功に導いたわけですが、彼があそこまで人びとに熱く受け入れられた秘密の一端は、そこにこそあると思うんです。いや、それは単に彼の無邪気さが好感を持たれたということではないですね。彼のキャラクターは人びとが潜在的に抱いていた童子幻想、つまり、特異な能力を持ったあどけない子供が突然どこからともなく現れて、世の中をがらりと変えてくれるという願望に、ぴったりはまりこんだのではないかと思うんですよ。』(新書版、P658〜659)
と語らせていたし、別のところでは「ネオテニー(幼形成熟)」という言葉も使っていたが、実際に、ある時期「無邪気でありたい」と語っていた綾辻は、こうした言葉を「願望充足的」に真に受けてしまい、自分は「子供心を忘れない、特別な人間」だと思い込んでしまったのではないか。自分だけは、このままで「老けない」と、無邪気に信じ込んだのである。一一無論、外見は別にしてだ。
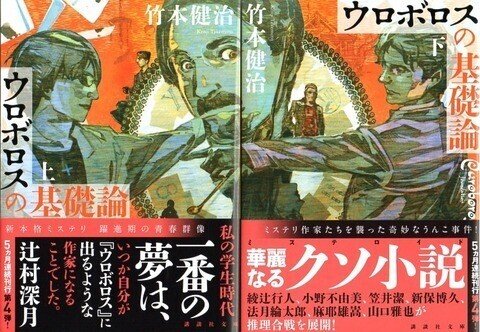
しかし、「何もしなければ、そのままでいられる」というほど、現実は甘くない。
綾辻行人を、前記のように(作中で)評した竹本健治でさえ、しばしば「自分はすでに、『匣の中の失楽』を書いた頃の自分ではない」という趣旨のことを語り、「人間の細胞は、6年ほどですべて入れ替わる」という学説を紹介したりもしている。つまり『行く川の流れは絶えずしてしかも元の水にあらず』(鴨長明『方丈記』)いうわけである。
言うまでもないことなのだが、人間(万物)は「そのまま」でいようとしても、そうではいられないし、「見かけを保つ」だけでも大変な努力が必要だというのは、美容の問題ひとつとっても、明らかな事実だろう。しかし、この程度のことが、「童子」のつもりの綾辻行人にはわからないのだ。
そしてこの問題は、無論「頭の中」についても同じである。
「みずみずしい感性」というものは、放っておいて保てるものではない、というのは、当たり前の話だ。
綾辻行人の場合、自分は「特別」だとでも思っているから、「物知り」なだけで「本質的な知性・みずみずしい感受性に欠ける大人」になんかならない、とでも自惚れているのだろうが、当たり前の人間にとって「みずみずしい感性」というのは、自分を磨き鍛え高める中で、やっとのこと、実現できるか出来ないかといった、困難事なのである。
『 自分の感受性ぐらい 茨木のり子
ぱさぱさに乾いてゆく心を
ひとのせいにはするな
みずから水やりを怠っておいて
気難しくなってきたのを
友人のせいにはするな
しなやかさを失ったのはどちらなのか
苛立つのを
近親のせいにするな
なにもかも下手だったのはわたくし
初心消えかかるのを
暮らしのせいにはするな
そもそもが ひよわな志にすぎなかった
駄目なことの一切を
時代のせいにはするな
わずかに光る尊厳の放棄
自分の感受性ぐらい
自分で守れ
ばかものよ 』
この詩を引用すると、「読めない読者」からは、「気難し」いのも「苛立つ」のも、おまえの方ではないかと言われそうだが、茨木のり子がこの歌で語っているのは、気難しくなるなとか苛立つな、ということではない。
茨木が言いたいのは「自ずと老い枯れていく感性を、みずみずしく保つには、自分の努力しかない」ということなのだ。だからこそ、茨木は「老い枯れていくままに流されがちな、怠惰な自分」に「苛立ち」、自分を叱咤しているのである。
ともあれ、「みずみずしくある」というのは、「変わらないように、何もしないでいる」ということではない。
そうではなく「自分への水やりを絶やさない=努力し続ける」ということなのである。そして、この「自己における現在進行形」こそが「中動態」であり「勉強の哲学」なのだ。
○ ○ ○
常に学び、自分への水やりを絶やさない不断の努力があってこそ、人は艶やかな花を咲かし続けることできるのであって、「一切の変化を拒絶して、そのままに止ろうとする」不自然な努力とは、レーニンや金日成「防腐処理された遺体」のようなものでしかない。そんなものは「すでに死んでいる」し、少しも「美しくはない」のである。一一それでも、盲信的な「賛嘆者」は、一定数いるにしてもだ。
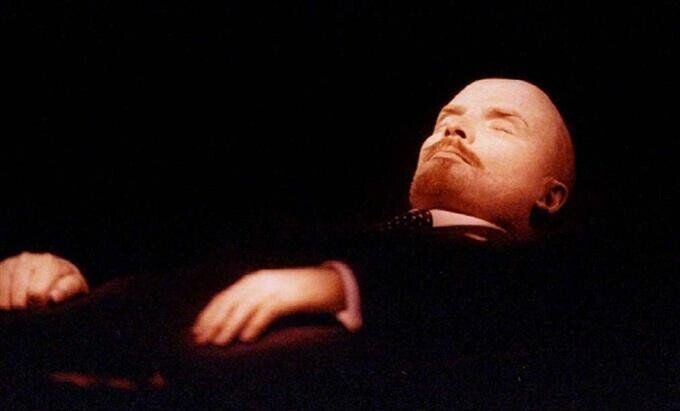
(レーニン廟に安置されている、防腐処理された遺体)
「言葉が失われる」とは、すなわち「大脳新皮質の機能停止」であり「ゾンビ」化だと言っても良いだろう。
私は、前記のレビューの最後を、次のように書いた。
『『いつもの言葉を哲学する』という場合に、この「いつもの言葉」が、おおかた「ロクでもないもの」にしかなっていない現状(例えば「エンタメ読書界の現状」)に、私たちは生きている。だからこそ、そんな「無内容かつロクでもない言葉」の奔流に、無自覚に巻き込まれて、感染しないように、「哲学する=言葉を吟味する」しかないのであろう。
すでに周囲は、ゾンビに囲まれているとしてもだ。
少なくとも私個人は、金輪際「脳の活動が止まったゾンビ」になど、なりたくない。
だから「哲学」するのである。』
「書評家・豊崎由美による、TikTokerけんご批判」の問題は、「物知らず」の綾辻行人やその読者には、想像もつかないことだろうが、古田徹也の『いつもの言葉を哲学する』の問題意識とも、國分功一郎の『中動態の世界』の意識とも、千葉雅也の『勉強の哲学』の問題意識とも、そして私の危機意識とも、その根を同じくするものなのだ。
私たちの世界から「言葉=水」が枯れかけているのであり、ゾンビたちはやがてミイラとなって、動くことさえ出来なくなってしまうかもしれないのである。
(2022年1月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
