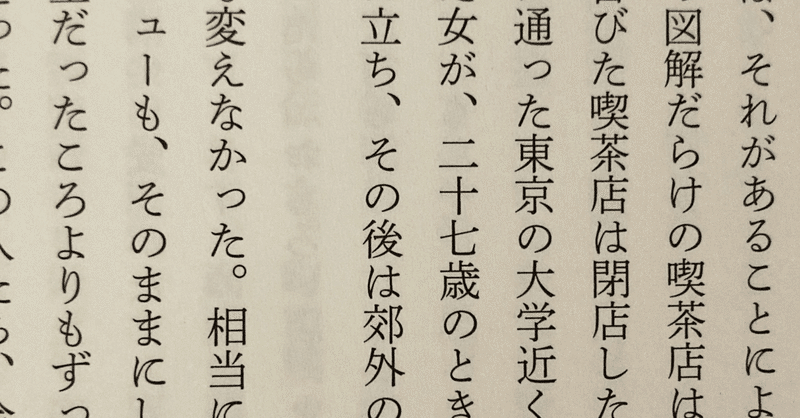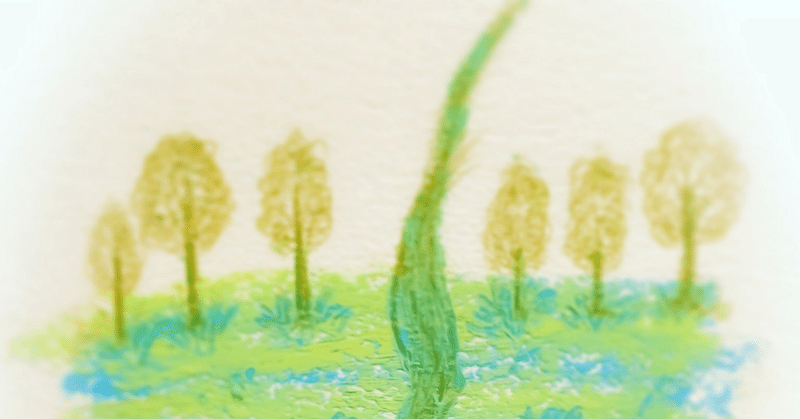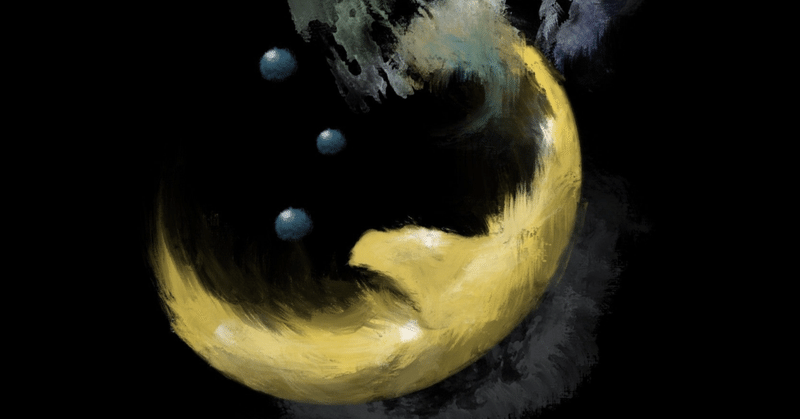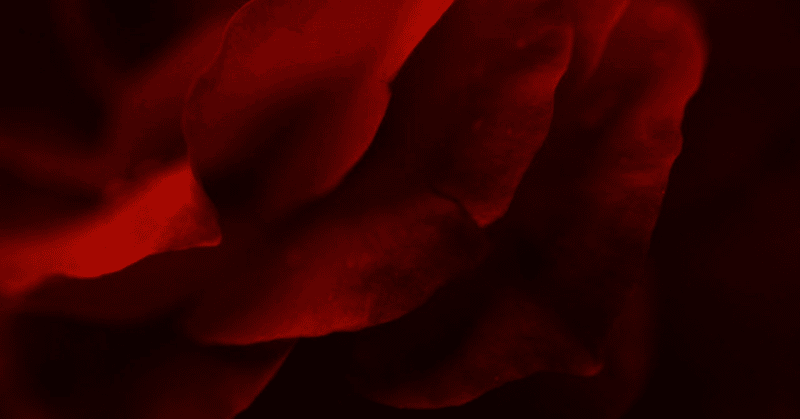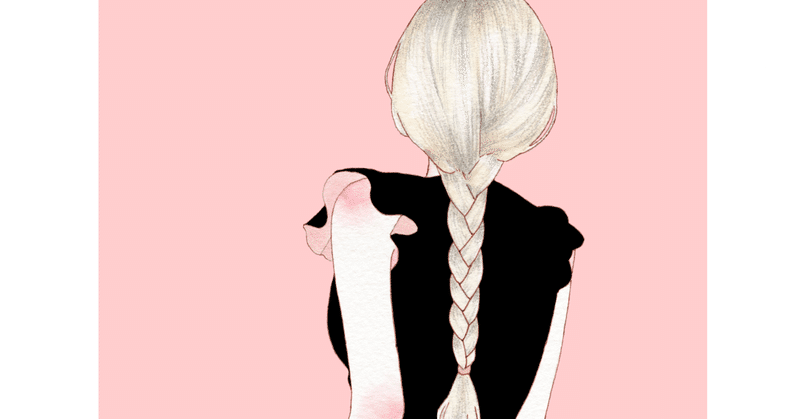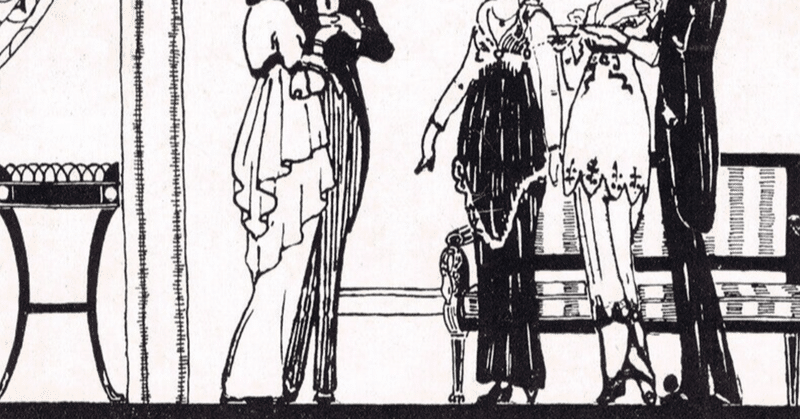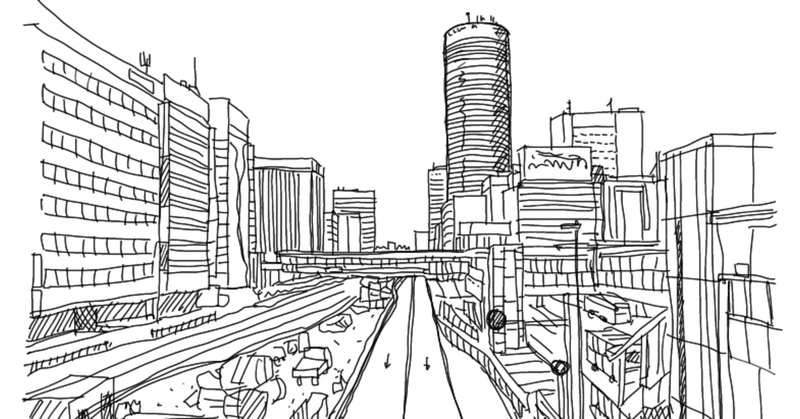記事一覧
『夏草の記憶』 トマス・H・クック
痛ましく残酷な、青春の愛の物語である。
南部の田舎町で、地元の医師として敬愛されているベン。しかし、穏やかな中年医師の顔からはうかがい知れない深い闇を、その心は抱えている。
妻にも親友ルークにも告げることのできない、ベンの胸に秘めた大きな重荷は、青春時代に起きたある出来事に関するものだ。
ベンがハイスクールの2年生の時、北部の大都会ボルティモアから、一人の転校生がやって来た。
浅黒い肌と黒い巻
『アトランティスのこころ』 スティーヴン・キング
1960年から現代までのアメリカを、いくつかの人生に乗せて描いた長編大作。読書の高揚感をかき立てる、上下巻組の大型本だ。
物語の幕開けは1960年、コネティカット州郊外の住宅地。11歳の少年ボビーは、母親と二人でつましく暮らしている。
ボビーには毎日つるんで遊ぶ気の合う友人がいて、恋人になりそうな女の子もいる。目下の関心事は、どうしても欲しい自転車を購入するために、お金を貯めること。
そしてもう
『階段を下りる女』 ベルンハルト・シュリンク
美しい女性の登場するラブストーリーと思いきや、消化不良になりそうな難易度の高い内容だった。ストーリー自体はシンプルなのだが。
語り手の「ぼく」は、フランクフルトで駆け出しの弁護士だった頃、忘れられない恋をした。
発端は奇妙な依頼だった。
依頼主はシュヴィントという画家。彼はグントラッハという金持ちの注文で、グントラッハの妻イレーネをモデルにした絵を描いたのだが、その後イレーネと恋仲になり駆け落ち