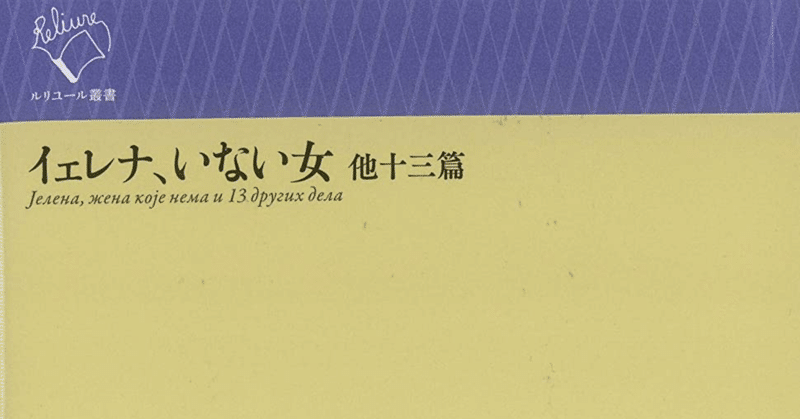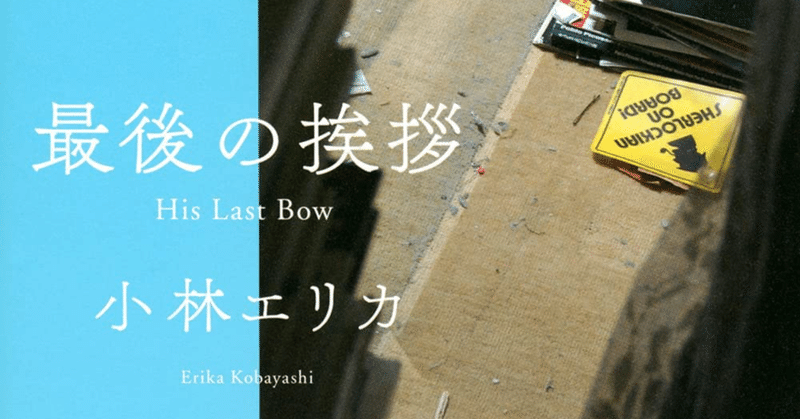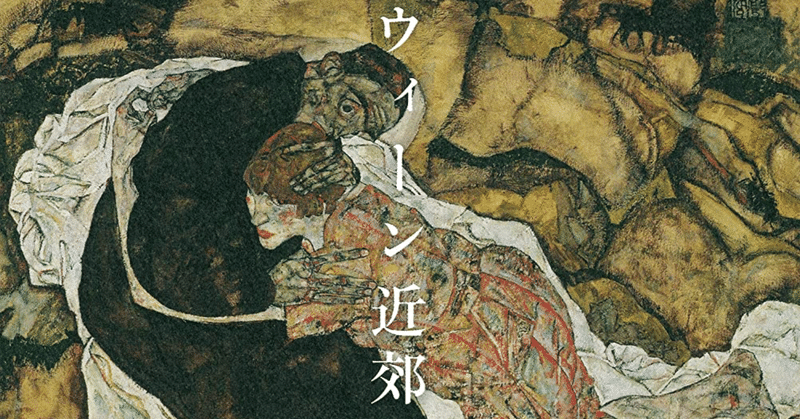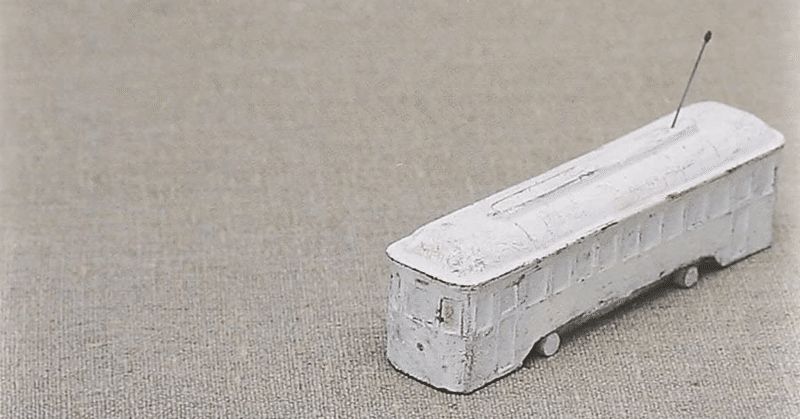記事一覧
孤独な観察者の流浪 アンネマリー・シュヴァルツェンバッハ『雨に打たれて』(書肆侃侃房)
文学の潮流から距離を置き、みずからの主題と対峙して創作に身を置いた海外の女性作家たち。彼女たちの作品は、近年日本でもめざましい(再)評価が進んでいる。シルヴィア・プラスやルシア・ベルリンは記憶にも新しい。そしてここに、日本の読者がまだ見ぬドイツ語文学の知られざる女性作家が、およそ一世紀もの時をへて紹介されるに至った。
スイスで生まれ、親ナチスの両親から離れて、異国を旅しながら三十余年の生涯に遺
架橋としての翻訳 イボ・アンドリッチ『イェレナ、いない女 他十三篇』(幻戯書房)
ボスニアに生まれ、東欧諸国を渡り育ち、ユーゴスラビアの最期を見届けることなくこの世を去った作家イボ・アンドリッチ。本書は現在のところ史上唯一となるセルビア・クロアチア語によるノーベル文学賞作家の作品を精選、訳者のひとりである山崎佳代子氏による詳細な解題を付した決定版と言うべき選集である。
移動する国境線、並存する信仰、人種や文化の不和から生じる紛争、それらを繋ぐ希望の象徴としての〈橋〉。名高き