
高橋和巳 『邪宗門』 : 〈失われた文学〉の象徴
書評:高橋和巳『邪宗門』(河出文庫・朝日文芸文庫・講談社文庫・新潮文庫)
やっと、高橋和巳を読むことができた。
中でも、この『邪宗門』は、「宗教」に批判的興味を持つ者としては、どうしたって気になる作品だから、これまでの20年間に三度ほど文庫本を買っているのだが、それを、やっと読むことができたのだ。
今回、私が読んだのは、最初に買った「講談社文庫版」で、後で買った河出文庫の方を積ん読の山に埋もれさせてしまい、逆に、昔買っておいたのが、たまたま出てきたのである。
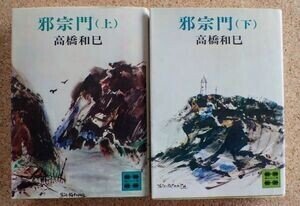
本書は分厚い文庫本で上下巻の長編だが、上巻を読んだ段階で思ったのは、意外にも「読みやすい」「明晰」「登場人物のキャラが立っている」といったことであり、「純文学作品だから、きっと読みにくいだろう」と構えていたのが、見事に裏切られてしまった。
ただ、あまりにも達者すぎて「こんなに読みやすく、面白くて、いいのだろうか?」という、一抹の疑問も感じないではなかった。

ところが、下巻に入ると、物語は徐々に暗い方向へと傾いていく、上巻で親近感を覚えた登場人物たちが、どんどんと追い詰められて生き、一人また一人と、不幸な最期を遂げていく。読者もそれに応じて、どんどんと胃が重くなるような気分にとらわれていくことになる。
そして、最後に「救い」があるのかと言えば、そんなものは無い。一一本書は、読者をジリジリと追い詰めていくような、その情け容赦の無さにおいて、まさしく「純文学」だったのだ。
○ ○ ○
本作は、戦前の天皇制・国家神道国家による、「大本教」への弾圧事件を、その主たるモデルとした作品であるが、描かれるのは、決して「大本教事件」そのものではないし、大本教だけをモデルにしているわけではない。
本書で描かれる「ひのもと救霊会」は、戦前の教派神道や新興宗教のいくつかをモデルとして、高橋和巳が「政治的現実と宗教」というテーマを思考実験的に扱うために、意識的に作り上げた「宗教」である。したがって、「ひのもと救霊会」と「大本教」を混同してはいけないと、まず最初に断っておこう。
講談社文庫版の解説者である真継伸彦も書いているとおり、「ひのもと救霊会」は、大本教だけではなく、天理教、ひとの道教団、生長の家といった、教派神道や新興宗教を研究した上で、この物語を成立させるために、論理的に作られたものなのだ。
本作の「ひのもと救霊会」と「大本教」は、どちらも戦前に国家権力からの大弾圧を受けて、いちじるしく教勢を衰えさせたという点では同じだが、戦後の展開が違う。

現実の「大本教」の方は、国家権力による徹底的な弾圧とその後の戦争によって、結局は教勢を盛り返すことができず、戦前の強烈な個性を失ったまま、マイナーな新興宗教のいち教団として延命したが、本作の中の「ひのもと救霊会」の方は、戦後に教勢を盛り返しただけではなく、もともと持っていた「世直し」思想を復活させて、戦後の日本においても、虐げられた庶民の側に立ち、資本家や権力者たちと対峙する。そしてそれがために、結局は進駐軍まで敵に回すことになって、武力抗争の果てに壊滅するという、壮絶な最期が描かれる。
つまり、高橋和巳が描きたかったのは、どんな新宗教でも最初は持っていたはずの「世直し」の思想が、戦前戦中の弾圧の中で挫折し失われて、戦後は無難な「迎合的平和主義」へと頽落していったのに対し、「もしも、戦後においても、世直しの思想を失わない宗教教団があったとして、それを貫いたらどうなるだろう」という「思考実験」であったのだ。
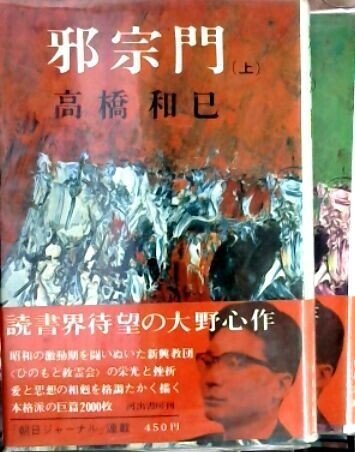
で、高橋の場合、その「結論」だけは最初から決まっていた。要は「壊滅」である。本気で「世直し」を考えて、それを実行に移せば、国家権力によって叩き潰されるという「結果」は、初めから分かっていた。
では、高橋は、何を「実験」しようとしたのか。
それは、「結果」がどうなるのかではなく、そうした理想を貫こうとした人々が、どのように考えどのように行動し、どのようなところへ行き着くのか、という「人間」の問題である。つまり、単純な「政治的勝ち負け」の問題ではなかった。
高橋和巳にとって重要なことは、「政治的勝ち負け」ではなく、「信念を貫く理想主義が、現実的な敗北の中でどのように生き得るか」という問題だったのである。
そして、こうした「信念を貫く理想主義が、現実的な敗北の中でどのように生き得るか」という問題は、高橋和巳にとっては、決して、単なる「思考実験」でもなければ「抽象議論」でもなかった。
と言うのも、彼は、中国文学の研究者として大学に籍を置きながらも、時の左翼学生運動の側に立ち、その結果、筋を通すために、教授職を辞したような人だったからである。

つまり、高橋和巳という人は、「それはそれ、これはこれ」の人ではなかった。
「大学教授」という「知識人」として「身分の安定した職業人」の立場にあって、本当の意味で「弱者の側」に立つことはできないと、当たり前に考え得た人、そして、そんな困難な選択をあえて選び得た、ごく少数の人の一人だったのだ。
本作『邪宗門』の主人公である「千葉潔」は、最後まで「信仰」の持てない、そして「救いはない」と考えるニヒリストでありながら、しかし「ひのもと救霊会」の側に立ち、最後は「教主」となって、自殺的な「世直し」抗争を指導してその戦いに敗れ、餓死による自死を選ぶ人として描かれている。
つまりこれは、高橋が「知識人」の限界を認識し、庶民がその「日常性」を越えるためには、どうしても「宗教」が必要だという認識を持ちつつ、自分が現実に、この世を真っ当なものにしようと行動したとしたら、どのようなことになるのかを、真剣に突き詰めた作品だったのだと言えるだろう。
今の「資本主義リアリズム」の世の中では、完全に消え失せてしまった「真面目な理想主義」が、この作品では暗い暗い光芒を放っているのである。
もちろん、真継伸彦も指摘しているとおり、この小説にも「限界」というものはある。
と言うのも、作者がこのように「きわめて知的であり、論理的であり、真面目な人」であるがゆえに、リアルな土俗的「宗教人」を描けなかった、という点である。

私は最初に、この小説について「登場人物のキャラが立っている」と書いたが、それは、この作品で描かれる「教祖」や「教主」といった人たちが、現実のそうした人たちのように、良くも悪くも捉えどころのない部分を持った人たちではなく、明晰に整理された「典型的人物」として描かれていたからなのだ。だから、わかりやすいし、キャラも立っていた。
しかし、そういう人たちは、本物の「宗教人」ではなく、高橋和巳の理解し得る範囲での「理想的な宗教人」だったのである。
したがって、そういう人たちの中に、自身をモデルとした主人公を配置して、宗教的理想主義としての「世直し」思想の行方を、我が事として「思考実験」したとしても、それは本当の意味での「宗教の可能性」を「思考実験」し得たことにはならないだろう。そうした意味で、この小説には限界がある。
しかしまた、「現実の宗教」の方も、それ以前に「志を失って、時代と世間に迎合する」ことしかできなかったのだから、高橋和巳に思考実験に、不平を鳴らす資格などない。
現実の方は、抽象化された宗教よりも、もっと情けないものだったのである。
このようなわけで、本作『邪宗門』は、「宗教」に可能性を見つつ、その限界をも洞察していた「知識人」の、どん詰まりの思考を、極限まで突き詰めた作品だと言えるだろう。だから、暗いし、救いとなる希望も、解答もない。
だが、だからといって、無価値ではない。
なぜなら、文学とは「有効性」を目的としたものではなく、人間の可能性を突き詰めるためのものだからである。

○ ○ ○
さて、ここで一つだけ蛇足しておかないといけないのは、本作が描く「ひのもと救霊会」の悲劇的な武力闘争が、著者・高橋和巳の時代とは違って、現在の私たちには、どうしたって、あの「オウム真理教」事件を連想させずにはおかない、という点だ。
つまり、安易な読者は「結局のところ、宗教的理想主義とは、反社会的な狂気へと至る道でしかあり得ない」といった半可通を、賢しらに語るかもしれない。
けれども、本作で描かれる、主人公・千葉潔の指導による、半ば自殺的な「世直し」闘争は、オウム真理教のそれのように「抽象的」なものでも「妄想的」なものでもない。

千葉潔が、戦前戦後の日本に見ていた「不平等や弱者に対する搾取」は、きわめて現実的なものであり、当時の庶民の誰もが認める事実だった。ただ、それを(今と同様に)誰もが「諦めて」もいたのである。「国家」や「進駐軍」には逆らえないと。
それに対して、千葉潔は、「宗教」が本来的に持っていた性格であり使命としての「世直し」を、その実現の困難を百も承知で、しかし捨てるわけにはいかない「宗教の最重要部分」と考え、その可能性の命ずるところに従って「行動した」のだ。
だが、「オウム真理教」の持っていた世界観は、そうした「リアルな社会的現実」に基づくものではなく、抽象的で「被害妄想的」なものであり、その意味で、きわめて「知的エリート的」なものでもあったと言えるだろう。
「オウム真理教」の場合は、「虐げられた弱者」のために戦ったのではなく、「不当に虐げられた、自分たち選ばれた者(エリート)」のために戦ったに過ぎず、そこに「理想」はなかった。
そこにあったのは「優れた者が、凡庸な人々から崇められ、良い目を見るのは当然だ」という「新自由主義的な、資本主義リアリズム」に毒された価値観でしかなく、高橋和巳が戦前の新興宗教に見、この作品に描いた「虐げられた庶民」のための「世直し」とは、似ても似つかぬものだったのである。
○ ○ ○
戦前、志ある「宗教」は、国家権力によって徹底的に叩きのめされた。その上で、さらに戦後の「資本主義リアリズム」に毒されて、ただ要領よく延命する術を覚えた。それは「宗教」を「商品」化することであったとも言えよう。
「宗教」が「人」を変え「世の中」を変えるのではなく、「宗教」の方が「人」びとの要請や「世の中」の要請に従って、自らを「売れる商品」へと変えていったのである。
そして、これは何も「宗教」に限った話ではない。
すべてのものが、基本的にはこの線で「商品化」されていった。一一無論「文学」もである。
そして、読者は、本作にも描かれているとおり、自らを、従順に「物化」つまり「商品化」していった。
いまどきの「承認される私」とは、端的に「商品価値のある私」でしかなく、「商品である前に私」であるなどという「私」は、もはや認識し得なくなってしまったのだ。
高橋和巳が、今も読まれなければならない所以とは、こうした「失われた部分」にあると言うべきなのではないだろうか。
(2022年6月10日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
