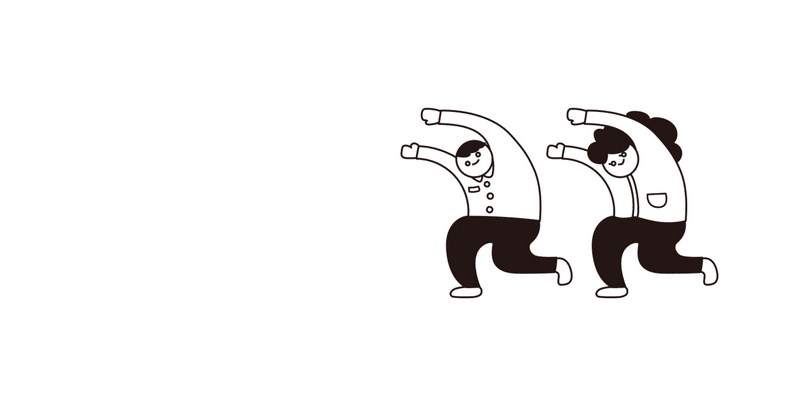
歌うように話し、踊るように歩いて、歌詞と共に恋に落ちる
キューバ。
そこは一年中暖かく、ビーチと自然に囲まれたカリブ海の真珠と呼ばれている。
僕が最も行ってみたいと思う国だ。
そこにこんなことわざがあるように、街中ではいたる所から陽気な音楽が聞こえ、ラム酒を飲み、葉巻をふかせ、昼夜問わずサルサやルンバを踊る人びとがいる。
どこからどう考えても最高だ。
それだけでものびのびとした国民性が伺える。
僕はラテンの音楽が好きだ。
ラテン音楽は大抵、底抜けに明るい。
底抜け。
これも僕の好きな言葉だ。
底抜けに明るい音楽であればあるほど、どこかの一瞬、一節でドス黒い闇が垣間見えることがある。
そこには「救い」が見える。
演奏している人がその音楽によって救われてきたこと。
その音楽を作った人が救われたいと願ったこと。
その想いの強さが、そのままエネルギーの大きさとなってぶつかってくる。
そして僕自身もその魂に触れて救われる。
僕らの住む街とは真逆も、真逆の国だ。
東京の満員電車に詰められた黒いスーツの男は、誰かを恨むように眉間に皺を寄せていた。
5分前に駅ですれ違った、無遠慮に肩をぶつけてきた名も知らぬ誰かに復讐したがっている。
ようにも見える。
スーツの男だけではない。
それぞれの制服を着て、それぞれの恨みを抱えて、「忙殺」の二文字が車内に充満していた。
そして、そんな陰気を跳ね返すだけの意志の強さもハングリーさも持ち合わせていない僕は、当然のようにその波にのまれた。
東京で夢を見た15歳の少年は、さらに15年の月日をかけて精神障害の手帳を取り、気付けば資本主義の最下層にいる。
誰もが、自分より弱い人間を探してるように思える。
誰もが、神経をとがらせてこちらをのぞいている。
見下して良い人間なんだとわかると安心し、心から笑う。
そんな人の目が恐ろしくてたまらない。
なぜなら、僕自身が人をそういう目で見ているからだ。
だから僕は人よりも劣っているところを必死に隠す。
嘘がバレることが怖いように、劣っていることが明らかになって、笑われるのが本当に怖い。
その目で、俺を見るな。
これ以上俺を観察するな。
僕は妄想する。
どうせ何者にもなれなかった人生、こことは真逆の場所へ行ってみたらどうなるだろう。
こんな心配の、いらない場所へ。
息の詰まらない場所へ。
心地よい音楽が癒してくれるところへ。
笑いの絶えないところへ。
もし、移り住んだなら僕はどう変わるだろう。
キューバは世界に5か国しかない社会主義国のうちの一つであり、異彩を放っている背景がそこにある。
「君はウェイターね。君は穴を掘って、それから君は車を作りなさい。」
国民の70%は国家公務員で、政府に仕事を決められる。
給料は皆一律で月収2000円ほど。
皆揃って、金がないが、税金もない。
医療費も、大学までの教育費もタダ。
月に1度、全国民に食料の配給もある。(少ないけど)
食べ物がとうとうなくなったときは、自営業などでお金に余裕がある人が家に食事に呼んであげたり、お裾分けをしたりして生きていくらしい。
「困ったら誰かが助けてくれる」
を地でいく国だ。
バスで泣いている赤ん坊は皆であやし、勉強のできない子どもには、できる子どもたちが教えてあげるのが、「普通」だ。
ずっと貧しかった国で、奪うのではなく分け与えて暮らしていった歴史から、そういう価値観になっていったのだろう。
中南米のイメージとは裏腹に、犯罪率は低く、学力は高く先進国並みだという。
僕に今一番必要なのはこういう、うっとうしいほどの横のつながりだ。
なんて尊い当たり前なのだろうか、と資本主義の敗者は思う。
人と関わる、人間らしい人生だ。
僕は人の目が怖い。
見下された目で、笑われたくない。
…果たしてキューバの地で、誰が僕を見下すだろうか?
満員電車もなければWi-Fiもほとんど通っていない。
道端で陽気にサルサを踊り、リアルに突撃隣の晩ごはんするような人々が?
考えただけで、ぽこんと気の抜けるような音がする。
ボンゴの乾いた皮を叩いた時のように。
実際には就労ビザを取ることは難いし、キューバ人と結婚する以外に日本人がキューバ永住することは現実的な話ではない。
どうにもならないことは、どうにもならない。
トランプ政権以降、経済制裁は復活した。
友好国のロシアも侵攻に夢中で経済支援がなくなった。
最近では1年で人口の3%が亡命しているほど、物不足は深刻になっている。
僕は今、明るい側面しか見ていない。
でも、モノが余りあるこの国に生まれた僕らにとって、「そんな暮らしがある」ことが救いで、「そんな人たちがいること」が救いなのだ。
多くの若者が亡命するのは、家族と親戚に仕送りをする為だ。
奪うことをせず、分け与えることを是とするキューバ人を調べれば調べるほど、やっぱり人間ってこうだよなと思えてくる。
「人々は自分の味方なのだ」と思えること以上に強くなれることはない。
その安心の土台の上でこそ人は健康に生きていける。
本当は、僕はいつもバカやって、笑える友達が欲しかっただけだった。
朝、街に出ていつもの新宿の駅前を散歩していると、制服に身を包んだ人々が、窮屈そうな顔をしてスマートフォンをにらみつけて歩いている。
皆、孤独にならぬよう必死になって戦っているのだ。
頭の中がキューバ漬けになっている僕は、それだけで優越感を感じた。
どうやら分け与えるような器の大きい人間にはまだなれそうにもない。
こちらは、別のアカウントで書いた2023年3月のnoteコンテスト「どこでも住めるとしたら」についての記事を再編集したものです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
