
樋口毅宏 『中野正彦の昭和九十二年』 : 〈偽史〉の精神誌
書評:樋口毅宏『中野正彦の昭和九十二年』(イースト・プレス)
いよいよ、噂の「回収」本、『中野正彦の昭和九十二年』である。
「いよいよ」というのは、私はこの作品を読むために、それまではその存在さえ知らなかった「樋口毅宏」という作家の著作を、4冊も読んできたようなものだからだ。
その4冊とは、読んだ順に『民宿雪国』『タモリ論』『さらば雑司ヶ谷』『雑司ヶ谷R.I.P.』。
『中野正彦の昭和九十二年』を読み終えた今、「長編エッセイ」である『タモリ論』を含めて、私の読んだ樋口作品の中で、最も面白かったのは、残念ながら、最初に読んだ『民宿雪国』であった。
その理由は、この5冊の中では、それが「最も抑制が利いていた」作品だったからである。
それとは逆に、「最も抑制が利いていなかった」のは『雑司ヶ谷R.I.P.』で、たしかに力作ではあるものの、作家・樋口毅宏の「問題点」をも、ハッキリと表面化させていた作品であった。
では、樋口毅宏の「問題点」とは、いったい何なのか。
一一それは、「諧謔」や「自虐」や「批評性」に見せかけた、「現実逃避による自己特恵(甘やかし)」とでも呼ぶべきものである。
その点で、本書『中野正彦の昭和九十二年』も、まったく同様の作品であり、同様の「弱さ」を持っている。
そうした、作者の、自身に対する「甘さ」や「弱さ」が、そのまま「作品の弱さ」になってもいるのだ。
だが、難しいのは、そうした「甘さ」や「弱さ」が、そのまま「似た者読者(党派的読者)」をも甘やかせる、作者固有の「魅力」にもなっている点であろう。
したがって、樋口毅宏の魅力とは、どこまでも暴走していく「自己韜晦」の迫力であり、自他にわたる「厳格で公正な批評性」などではあり得ない。
樋口毅宏作品の魅力とは、言うなれば「過度の飲酒によってハイになった状態で、仲間と一緒に車をぶっ飛ばす」ような「快感」とでも言えようか。
無論、当人らは、その状況に酔っているから楽しいのではあろうが、しかしそこでは、その結果について思考することを拒絶しているという点で、自らを無責任に「甘やかしている」と言えるのだ。
例えば「横道から、子供が飛び出してきたらどうするのか?」なんていう、面倒なことは考えない。
そんな質問をされたら、「轢き殺せばいいじゃないか(笑)」と、酔いの勢いのままに、威勢よく答えることもできるのだが、実際にそうなってしまうと、彼らはただ、青ざめることしか知らないであろう。
そうした「本質的な問題」に比べれば、本書が「回収」されてしまったことなど、大した問題ではない。
もちろん、一般的な「言論・出版の自由」の問題としてなら「重大な問題」だと言えるだろうが、それについては「いまさら」今回の件で言挙げしなければならないことなのか、という感じが否定できない。そういう問題を提起したいのであれば、もっと「責任の持てる書き方」があったはずだからだ。
つまり、本書には、そうした「高尚な問題」とはレベルの違った部分で、大きな「問題点」つまり「弱点」があったということであり、その「弱点」こそが、作者・樋口毅宏自身の「弱さ」に由来する、「狂騒的で無責任な、傍若無人さ」ということなのだ。
○ ○ ○
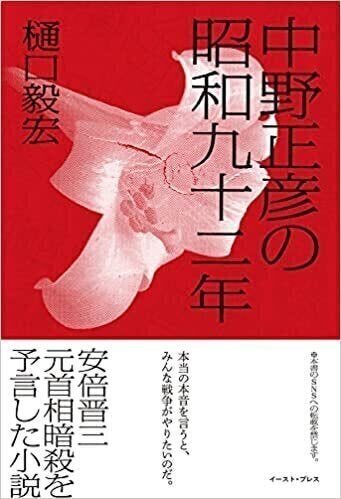
本作『中野正彦の昭和九十二年』は、「右翼テロリスト青年」である主人公「中野正彦」の、「一人称」で語られる「主観」物語である。
したがって、その主観的な「語り」は、常に「主人公の自己正当化」に満ちたものであり、その部分は、明らかに作者によって「意図された表現(主人公の性格的難点)」であるからこそ、著者である樋口毅宏の意図が、主人公の立場(平たく言えば「ネット右翼(ネトウヨ)」的な立場)に対して「批判的」なものだというのは、明白な事実であろう。
つまり、本作は「ネトウヨの薄っぺらい理屈」を逆手に取ることで、「ネトウヨ」的なものを「批判」する作品であって、決して「語り手(主人公)」の立場に立ってそれを正当化するために書かれたものではない、「批評的な作品」だと言えるのである。
本作の主人公が、単なる「ネトウヨ」ではなく、作品冒頭で「沖縄の反政府的な市民運動家のリーダー」を暗殺する「右翼テロリスト」として描かれているのは、実際のところ、物語にダイナミズムを持たせるためのものでしかなく、本作が、実際に批判しているのは、「右翼テロリズム」的なものと言うよりは、やはり「ネトウヨ」的なものだというのは、一読すれば明らかなことだ。
しかし、本作で真に問題となるのは、そうした「ネトウヨ批判」的な部分ではない。
そうしたものだけなら、本作は、ごくありふれた「ネトウヨ批判本の小説版」ということでしかないのだが、実際には、本作は、「ネトウヨ批判」であると同時に、それを口実(アリバイ)にして、「ネトウヨ側=安倍晋三支持派」と「反ネトウヨ側=反安倍晋三派」とを問わずに、ぜんぶひっくるめて「こき下ろした」作品になっている点だ(だからこそ、この物語のラストは、救いのない終末的な世界像となっている)。
もちろん、本書の語り手である主人公・中野正彦は「ネトウヨ側=安倍晋三支持派」なのだから、彼が「反ネトウヨ側=反安倍晋三派」をこき下ろすこと自体は当然なのだが、しかし、本作の問題点は、主人公「中野正彦」を「隠れ蓑(アリバイ)」にし、彼の口を借りて、作者が「無責任な言いたい放題」を書いた作品にしかなっていない、という点なのだ。
作者・樋口毅宏は、なるほど「ネトウヨ」的なものが大嫌いであり、それに対して批判的だというのは、事実ではあろう。
しかし、だとしても、その樋口が、「反安倍晋三的なもの」、言い換えれば「左翼リベラル的なもの」に、心底共感的なのかは、かなりあやしい。

無論、樋口毅宏が、「安倍晋三的なもの」に批判的なのと同時に、「左翼リベラル的なもの」についても批判的であったとしても、そのこと自体はなんら責められるべきことではないし、むしろ大いに結構なことでさえある。
言い換えれば、批判者としての作者は「どちらか(の党派に属しているの)でなければならない」などということはなく、その意味で、二者択一的に「旗幟を鮮明にする(どっちの味方なのかを明らかにする)」必要など、まったくない。
むしろ、自分は「どっちも嫌いだ」と両睨みで批判するというのは、どちらか一方の「党派」に組みしての批判などよりも、よほど健全な「批評」だと言えるからである。
しかし、樋口の場合は、主人公・中野正彦の「一人称」で書くことで、逆接的に「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」を批判するのは良いとしても、その「逆説的な手法」であり「形式」を「アリバイ」として、「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」までも、「責任回避しながら批判」いる点が、問題なのだ。
「見てのとおり、私(樋口毅宏)は、ネトウヨ的なもの(=安倍晋三的なもの)を批判しているのだから、反ネトウヨ的なもの(=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの)を、批判するわけがないんですよ。そうした見方(読解)は、作者と作中人物を混同した、誤読です」ということで、「左翼リベラル批判」についての「責任」から「逃げ」てしまっているのである。
当然のことながら、「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」を批判しているからと言って、著者が心から「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」の側に属しているという「保証」など、どこにもない。
「両方を批判する」という立場は、当然あり得るものなのだし、それがまともにできていたとすれば、それは「党派的な批判」などより、よほど優れて本質的な批評性だといえるのだが、しかし、そうした「右も左も、バカ野郎ばかりだ」という批判は、自らを「孤立無援な立場」に置く「よほどの覚悟と能力」がなければ、到底なし得ないものだ。
だが、本作『中野正彦の昭和九十二年』において、作者・樋口毅宏に、それがなし得ているかと言えば、もちろん、そんなことなど、なし得てはいない。
樋口毅宏が本作でやっていることとは、「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」への批判と、それをアリバイとした「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」への批判も含めた「総体批判」であり、にもかかわらず、その困難事の「責任」を引き受けることなく、自身を「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの」の側に擬して「逃げ場」を確保したうえで、双方を「批判」することにより、自身の絶対的な「賢さ(狡猾さ)」に、内心で自己満足している、といったことだけなのである。
○ ○ ○
ちなみに、遅まきながら、本書の「あらすじ」紹介的なものを、ここで引用紹介しておこう。
『 安倍晋三元首相暗殺を予言した小説
想像しうる最悪の未来。
「本当の本音を言うと、みんな戦争がやりたいのだ」
安倍晋三元首相を「お父さま」と慕う中野正彦ーー
過激で偏った思想を持った革命家気取りのテロリストが、
一発逆転、国家転覆を目論む。
「水道橋博士のメルマ旬報」連載時から物議を醸し、
大手出版社が刊行を躊躇った未完の小説が、大幅加筆のうえ完成。
※本書のSNSへの転載を禁じます。
※実在する人物、団体、出来事とは一切関係ありません。
高江ヘリパッド建設、日当二万円、放射脳、金正男暗殺、森友学園、共謀罪、特定秘密保護法、サタンの母、國民の創生、在日特権、慰安婦像、南京大虐殺、テロの経済学、山口二矢、よど号ハイジャック、朝鮮人虐殺、自己責任、内乱罪、非国民、核シェルター、金正恩、Jアラート、憲法改正、美しい日本の憲法をつくる国民の会、三島由紀夫、奔馬、加計学園、マスゴミ、原発再稼働、売国奴、少年B、朝鮮人虐殺、安重根、純日本人、忠臣蔵、ドナルド・トランプ、3・11、中野、大久保。』
(Amazonの『中野正彦の昭和九十二年』紹介ページより)
この「出版社側=作者側」の紹介文にも明らかなとおり、本作は、いかにも「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」の側に立って書かれているように見えるが、実際には「それだけではない」。
問題は、「それだけではない」部分については、誤魔化されており、責任を取る気がない、という点なのだ。
本書の「法的な問題点」については、弁護士の飯田亮真が、インタビュー「『中野正彦の昭和九十二年』の内容は差別なのか。回収された小説を読んだ弁護士「封印すべきではない」」で語っているから、その点については、素人である私が、あれこれ言う必要はないだろう。
だが、このインタビューで、飯田弁護士も、
『「作中の人物が差別的な言動をしている」ということと「この作品自体が差別的であるかどうか」は分けて考える必要があると主張。作者は明らかに、差別的な言動をする登場人物を「否定的に描いている」として、作品全体の文脈から考えたときに「この作品が差別的な内容である」とは言えないという見解を示した。
また、作中の描写が名誉毀損に当たるかどうかは「現実の社会においてその人の社会的評価を下げる表現」かどうかが重要となると指摘。この小説の場合には個人的な見解と断った上で、「現実の社会においても、そのモデルになった人の名誉が毀損されるということにはならないと私は思います』
といった具合に語っているとおりで、「本作の問題点」について、本作を批判している側も、擁護する側も、共に本作にかかわる論点が「差別表現か否か」「名誉毀損に当たるか」といった、「良識的」あるいは「法的」な側面でしか見ていない点で、「この作品における批判が、果たしてフェアなものであったか否か」という根本的な倫理問題には、まったく届いていない点である。
だからこそ、作者・樋口毅宏の主張する「作者に差別の意図が無かったことは、私の日頃のツイートなどを見てもらえば明らかなはずだ」といった、低レベルの「言い訳」も可能となっている。
しかし、本作『中野正彦の昭和九十二年』の真の問題点は、作者・樋口毅宏の「意図が奈辺にあったのか?」とか「日頃の発言はどうであったのか?」とか言ったことではなく、「この作品が、どういう作品なのか?」ということなのだ。
その意味では、作者の「日頃の発言」などというものは、作品を正当化する理由には、まったくならない。
「裁判」ともなれば、それも「アリバイ」のひとつにはなろうが、「文学」においては、作者が日頃、いかにご立派な発言をしていようと、問題は作品の「実際の出来(作り・中身・完成度)」であって、「いつも立派なことを語っている人の作品だから、作品も立派な意図を持ったものに決まっている」などという、「幼稚に短絡的な話」にはならない。
言うまでもなく、匿名ではない著名人による、Twitterなどでの「日頃の発言」というのは、当人がその「実存在」を晒し、それを賭けて行うものだからこそ、「無難なきれいごと」になりやすい。
一方、作品、特に「小説」などの「フィクション作品」の場合、「作中で語られる思想と、作者自身の思想とは別物である」というタテマエがあるからこそ、それを「アリバイ」にして、「日頃は語れない本音」を垂れ流すことも、容易に可能なのだ。
例えば、本作『中野正彦の昭和九十二年』だけではなく、『さらば雑司ヶ谷』『雑司ヶ谷R.I.P.』でも、主人公が「変態プレイ」に喜悦の声をあげるシーンが、いささか偏執的に描かれるのだが、これは、作劇上「必ずしも必要なもの」ではない。
特に「肛門をいたぶられる変態プレイ」という特徴的な描写は、作者の隠された願望の表出だと読んでも、なんら不都合ではないし、そもそも「変態プレイ」自体は「趣味」の範疇だから、別に何も「悪いことではない」のである。

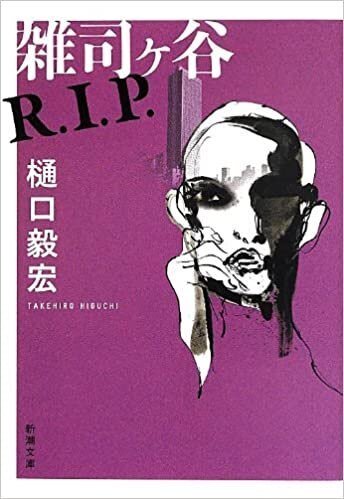
しかし、作者が「日頃の発言」で「いや、僕は、肛門を虐められる変態プレイが、たまらなく好きなんですよ。強い男に肛門を蹂躙されてヒイヒイ言わされるとか、逆に、若くて可愛い女の子に、肛門をいじられて、この変態ブタさんなんて言われるのはたまらなくて、じつは、妻には内緒で、時々そういう店に通っています」なんてことは、金輪際、言わないはずだ。
つまり「日頃の発言」には、多分に「自衛的なきれいごと」が含まれている一方で、「作品」である「小説(フィクション)」には、「これはフィクションであり、実在する人物、団体、出来事とは一切関係ありません。無論、作者の本音を語ったものだとは限りません」という「予防線」においてこそ、「本音」が露出することも、決して珍しくはないのである。
そんなわけで、「文芸批評」における「テキスト読解」でなすべきことは、「リベラルな作者の作品だから、リベラルな内容の作品に決まっている」とか「ネット右翼の作品だから、ネット右翼的な内容の作品に決まっている」といった「幼稚な決めつけ」や「思い込みのよる判断」などではあり得ない。
あくまでも、「作品」に即して「作品の語るところ」を剔抉するのが、「文芸評論」の使命なのだ。
そして、そういう観点からすれば、前記のインタビューで飯田弁護士が、本作『中野正彦の昭和九十二年』を読んだ「印象」として、次のように語っているのは、まったく正しいと言わなければならない。
『この小説は、中野正彦という架空の人物が2017年2月から12月にかけて書いた日記という体裁を取っている。デリバリーピザ店でアルバイトをしている中野が、実際のニュース記事を引用しながら、世の中に毒づく日々が前半は延々と続く。中野は安倍晋三首相(当時)を「お父様」と呼んで盲信する一方、在日朝鮮・韓国人への敵意を隠さない。民族・国籍差別的な表現、女性蔑視、実在する芸能人やジャーナリストらに対する罵詈雑言のオンパレードだ。
吐き気を催すような文章が延々と続く一方で、本筋のストーリーは遅々として進まない。読んでいて非常に苦痛だった。仕事でなければ途中で断念していたのは間違いないだろう。帯には「安倍晋三元首相暗殺を予言した小説」と書かれているのだが、実際にそうした話が出てくるのは終盤になってから。全体の3分の2が過ぎた辺りからだった。
この安倍首相暗殺計画が浮上してからは、それまでとは異なり、怒濤のストーリー展開と凄惨な描写が続く。ただ、安倍首相を盲信していた主人公がなぜいとも簡単に暗殺に乗り出すのか、心の動きは全く描かれない。そのまま小説は終わり、作品の世界から放り出されたような気分になった。』
ここで、注目すべきは『安倍首相を盲信していた主人公がなぜいとも簡単に暗殺に乗り出すのか、心の動きは全く描かれない。』という指摘だ。
なぜ、「右翼テロリスト」である主人公の『心の動き』が、満足に描かれなかったのか?
それは、作者が「あいつらは、何も考えてないし、考える頭もない。ただ、信じたいものを信じて、救われたいだけの馬鹿なのだ」と思っているからである。
私は、作者・樋口毅宏のこうした「ネトウヨ」観を、必ずしも否定批判するものではない。むしろ、まったく賛成だと言っても良いのだが、しかしその程度の「事実」なら、何もこれほどまでに長い小説として書く必要はなく、短いエッセイや、それこそ「ツイート」で十分なのだ。
だが、それにもかかわらず、これほどの「長編小説」にしなければならなかったのは、そうした「形式」でなければ語れないことまで、作者は本作に盛り込んでいた、という事実を示唆している。
つまり、それが、「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」批判では収まらない、「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」への批判であった、ということなのだ。
作者・樋口毅宏は、「日頃の発言」として「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」批判をすることはできたし、事実、してもきた。
しかしそれは「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」の側に属し、そちらからは「庇ってもらえる」という安心感なりがあっての「党派的な批判」であって、決して「私一人による批判」などではない。
それはちょうど、元外交官であった「佐藤優」が、体制批判側と体制側の双方に「二股」をかけて、どちらに転んでも生き延びられるよう保身をはかる「コウモリ男」であるのと同様のことで、樋口の場合は「反体制側=反安倍晋三=反ネトウヨ」であると、殊更に「旗幟を鮮明にする」ことによって、安心して「どちらもこき下ろせる(嘲弄できる)立場」を手に入れたのである。
樋口が「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」を批判をするのは「当然」として、まさか「反ネトウヨ的なもの=反安倍晋三的なもの=左翼リベラル的なもの」まで批判するとは「考えにくくする」ために、樋口は、あえて「ネトウヨ的なもの=安倍晋三的なもの」への批判を、前面に押し出して強調し、そのことで、本来ならば困難な「両睨みの批判」を、韜晦的で自己満足的なかたちではあれ、可能にした。
そして、だからこそ、樋口毅宏の小説には「吐き気を催させる」ようなものがあり、たぶん少なからぬ読者の読後感として、作者を信用しきれない「不快な何か」が残るのだ。
○ ○ ○
したがって、本作『中野正彦の昭和九十二年』が、表面的に「反体制側=反安倍晋三=反ネトウヨ」であることをして、作者・樋口毅宏の「悪意」や「姑息さ」を直視できない「反体制側=反安倍晋三=反ネトウヨ」派の読者というのは、「政治的な党派性」に毒されて「客観性」を見失った「読めない読者」であると断じていいだろう。
「あの樋口さんに限って、そんなことをするわけがない」などという発想は、読者自身の「党派的な自己正当化」でしかなく、「味方の有名人」を過剰に高く評価したがる、「権威主義」に出たものでしかない。
敵であろうと味方であろうと、ダメなものはダメ、駄作は駄作だという、孤立無援の立場を引き受ける覚悟がなければ、「客観的な評価」という「批評の使命」など、担えるわけがないのである。
○ ○ ○
したがって、本作『中野正彦の昭和九十二年』を客観的に評価するならば、たしかに本作は「あいつらは、本当に頭悪いな」と「ネトウヨを叩く痛快さ」を与えてくれる「エンタメ小説」にはなっているけれども、「人間を描く」という文学的な側面においては、「類型的なネトウヨ像」しか描いていない、その意味で「人間が描けていない」、ただの「通俗」作品だということになろう。
しかしまた、作者が、期せずして本書で「描いてしまったもの」とは、作者自身の「姑息さ」であり、また、それを見抜くことのできない「お友達」の、「党派性に曇った目」に他ならないのである。

(2023年3月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
