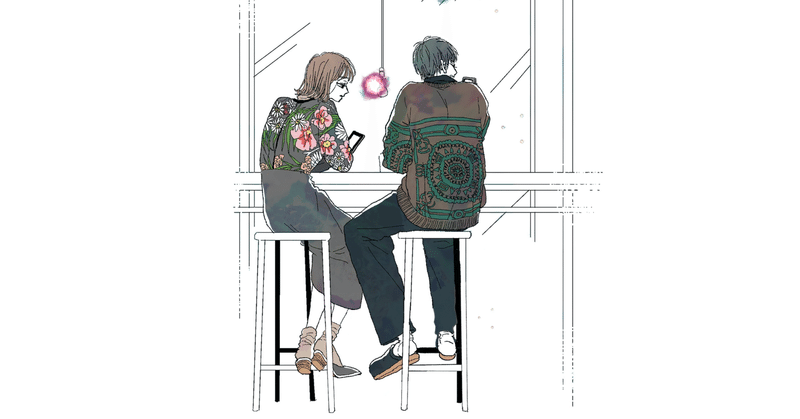
コーヒーと太宰治と夏目漱石
ある晴れた冬の日に、私はとある喫茶店にいた。
丸太で外装を覆われた、温かみのある暖色がメインの小綺麗な喫茶店。ホットココアでも飲みたくなるような、やんわりとしたお店だ。
なぜ私がここにいるのか。
それは、マッチングアプリで知り合った男の子に会うためだ。大学生になってあまりいい出会いが無くて、周りにバレやしないかとおどおどしながら始めた。
今日で三人目。
髪は凄く短くて、おっとりしている見た目。近所で猫と戯れてそうな雰囲気。
まぁマッチングアプリなんて自分の写真は皆もりもりに盛っているし、多少の演出が絶対に入っていると思うから、そこまで期待はしないけれど……ちょっと楽しみ。
何往復かやりとりをしたら、「会って話そうよ!」と直ぐに誘われた。
この軽い感じ、相当な手練れか純粋無垢かどっちか。でも、マッチングアプリ勢の時点で前者なのだろう。うーん、マッチングアプリって難しいものだ。
なぜ始めたのか?
それは、出会いを求めるためだけにバイトを始めたりサークルに入ったりするのは少し気が引けたからだ。
男の子は好きだからいろいろ遊びたいけれど、面倒くさいのも少し気が引ける。
手軽に出会えるものがせっかくあるなら、やらない手はない。
出会いを求めるためだけにやるには、アルバイトやサークル活動はその後にやらなければいけないことがあまりにも多すぎる。
一度コミュニティーに入ってしまうと、抜け出すことがなかなか難しい。
私の外見は、別に全員が振り向くような美人ではないと思うけれど、悪くもないと思うし、実際友達と遊んでいるときの写真を少しだけ加工したものをプロフィールに使えば、案外簡単に男の子とマッチングできた。
男の子からいいねが来ると、ちょっと自分を認められた気になって、気分がいい。私はちゃんとかわいいのだと、そう思える。
私は母とはあまり仲が良くない。しかし、高校生のときに割にしっかりと化粧の仕方だけは素直に聞いて覚えたから、顔の図画工作は得意な方だ———素材もいいと思うし。
インスタグラムを使っていい美容師さんや化粧品などは常にチェックしている。
※
喫茶店に早めに着いた私は、温かいココアを注文した。
こういう約束事は、割と早めに来るのが私の癖だ。相手を待っているときのドキドキ感が、結構好きなのだ。
あと、早めに来た方が気持ちが落ち着くから取り乱したりせずに済む。
これも作戦の内。
十分ぐらいして、喫茶店の入り口の鈴が鳴った。
彼が入って来た。
「外、雪凄いね」
彼は穏やかな声でそう言った。
一度電話で話したことがあるけれど、思っていたよりも声が低くて、落ち着き払った雰囲気がある。
手先で何かが光った。
銀色のシンプルな指場を右手の人差し指に付けている。
———手が、綺麗だな。
そう思った。
※
「雅美ちゃんはさ、暇なときいっつも何してるの?」
彼は着ていたコートをハンガーにかけて席に着くなり聞いてきた。
「うーん、いつもは大体ドラマを見てるかな」
「へぇ、どんなドラマなの?」
「韓国ドラマ」
「あ、めっちゃドロドロするやつだ」
彼は爽やかに笑う。
「そうなのよ。でも、ドロドロするやつばっかりじゃないよ」
「え、そうなの?」
「そうそう。意外とちゃんとしたものもあるんだから」
「王宮系の時代物は見たりしないの?」
「あぁ、たまに見るけど、そこまでは多くないかな」
「へぇ、じゃあ恋愛系のドラマが好きなんだ」
「そうだね」
「俺も韓国系じゃないけど、結構見るよ。恋愛系のドラマ」
「どういうのを見るの?」
「地上波であってるやつかな。なんか、なよなよした男見てるとむずむずしちゃう」
「大貴くんは積極的なタイプなんだ」
「うん、割とそうだね。好きだって思ったら直ぐに言っちゃう」
「へぇ、それじゃあ女の子側は嬉しいね」
「そんな単純じゃないでしょう。早めに言われると面白くないって、昔言われたことあるもん」「まぁ、そう思う子もいるよね」
「雅美ちゃんはどうなの? 好きな男の子が出来たら直ぐ言っちゃう?」
「うーん、私は結構怖がりだから言うの遅くなっちゃう。というか、そもそもあんまり言わないかな」
「そうなんだ。じゃあ、男側が頑張るしかないね」
「そうだね」
大貴くんは私が通っている大学からは少し遠くて、県の中でも両端にある学校にそれぞれ通っているから、あまり頻繁に会うことは出来ない人だった。
でも、メッセージでやり取りをしていても、ちゃんと頻繁に返事が返ってくるし、話の引き出しが多くてやり取りしていて楽しかった。
だから、一度実際に会ってみたいと思っていたのだ。
あまりタイプじゃない人と多く出かけても時間の無駄だと思ってしまうから、会う人はそこまで多くはない。けれど、大貴君はちょっと会ってみたかった。
「雅美ちゃんさ、やりとりしてたときのイメージとちょっと違った」
「どういうこと?」
「思ったこととかはズバッと言いそう」
———何を言っているの?
「あと、あんまり人を信用してなさそう」
「どうしてそう思ったの」
「いや、何となく話していてそう感じただけ」
※
男の子は一見凄く単純そうに見える。でも時折、何を考えているのか分からないときがある。純粋無垢そうな目の奥にとても冷たい光を宿しているときがあるのだ。
男の子って、何なんだろうなぁ。
未だに分からない。
※
「俺はさ、ずっと古典にハマってるんだよね」
一応礼儀として彼のことも聞いてみるとこう言ってきた。
「え、古典? 古典って何の?」
「古典文学」
「古典文学?」
「そうそう。太宰治とか坂口安吾とか」
「太宰治は聞いたことがあるよ」
「まぁ、正確には太宰ぐらいの時代は古典文学じゃなくて近現代文学って言うんだけどね」
「そうなの?」
「そうそう。古典文学って、江戸時代の物語とかその辺のもっと昔のものを指すんだよ」
「へぇ、知らなかった」
「まぁ大抵の人には正確な定義何て関係ないから『古典』って言っちゃってるんだけどね。雅美ちゃんは小説とか読む?」
「うん。結構読むよ。私インドア派だから」
「へぇ、想像通りなような、そうでないような」
「どういう意味よ」私は少し笑った。
「ちなみにさ、どうして古典を読もうと思ったの?」
「親が国語の先生でさ、変わり者だから家に昔からあったんだよ。それで高校生ぐらいのときから暇なときに読んでたらハマっちゃった」
「国語の先生って全員古典の本を持ってるものなの?」
「雅美ちゃん、主語を大きくするのは良くないよ。俺の親が変わり者なだけさ」
「そうなんだ」
「雅美ちゃんはさ、暗い話好き?」
「暗い話?」
「そう。ホラー系の怖い話じゃなくて、人間関係とかの怖い話」
「私は好きじゃないかな」
「そっかぁ」
「大貴君は好きなの?」
「うん、俺は凄く好き。暗いものに嘘はないから」
彼は澄ました顔でテーブルにあった水を飲み、少しため息をついた。
やっぱり、彼は手が綺麗だ。
※
私の好みは、可愛い男の子だ。
友達の中には体毛の濃ゆい、人類の進化過程の初期段階みたいな見た目をした男がタイプだという人がいるが、正直意味が分からない。
人の好みを否定することは憚られるけれども、それにしても体毛が濃ゆいのは気持ちが悪くないか?
男臭いのが好きだという変わった性癖を持っている人もいるけれど、臭いのはどんな種類のものであれ、私は絶対に嫌。
体に触れたときにザラザラしてるなんて、絶対に嫌。
ずっと好みの男の子を見つけては小突いてみてを繰り返しているが、あまり好みに百パーセント当てはまる男の子は今のところ見つけられていない。
私は常に彼氏が途切れないタイプだけれど、「どうして?」と聞かれることが多い。理由は単純だ。付き合っている人がいても、仲の良い人が多いからだ。
何か喧嘩をしたり別れ話が切り出される頃には、もう次の候補になりそうな人がいることが多い。メンヘラするのは良くないと思うけれど、実際何らかの形で関係を持っている人がいないと、ふとしたときに孤独感で頭がおかしくなってしまいそうになることがあるから、私は常に彼氏を途切れさせないようにしている。
女の子は孤独感にやたら弱い生き物だ。寂しい、と言う感情が最も女の子を苦しめる。女の子には満たしても満たしてもまだ溢れてくる無限の欲求があるのだ。
※
「大貴君さ、彼女いたことある?」
「あるよ。雅美ちゃんは? 彼氏何人いたの?」
「私は二人よ」
「結構多いね。俺は四人」
「大貴君も多いじゃん」二人で少し笑った。
「大貴君の彼女大変そう」
「え、どうして」興味津々そうに聞いてくる。
「だって、大貴君変わり者だから」
「親の遺伝だね。でも、興味湧いてきたでしょ?」
意地悪いことを言う。
一度デートしたり二人で会ってくれたりしたのであれば、必ず少なくない気があることになる。女は生理的に受け付けない男には、ごみを見るような眼をして見てくるし、そこら辺のサイコパスより冷たくなる。
だから、そうでないのであれば多少の強引さで引っ張ってあげるべきだ。
※
その後結局、彼についていってしまった。
LINEを交換して帰って来たけれど、それほどやり取りをすることは無く、私は捨てられたのだと悟った。
少し傷ついた。彼は久しぶりに好きになれそうな人だったから。
信じるものは裏切られ利用され捨てられる。
悲しい世の中だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
