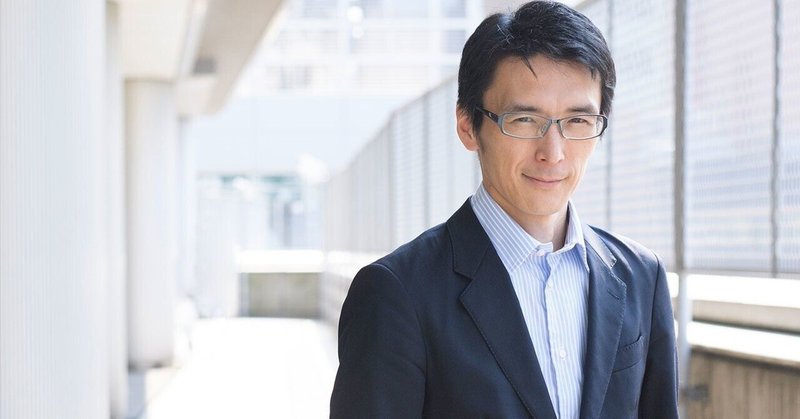
國分功一郎 『目的への抵抗』 : 「優等生であることからの逃走」論
書評:國分功一郎『目的への抵抗』(新潮新書)
本書は、2本の「講義録」をまとめたものである。
一方は、コロナ禍まっ盛りの頃(2020年10月2日)に、著者が務める東京大学のオンライン講義として、高校生にも開かれたかたちで行われたものであり、もう一方は、同大学の「学期末特別講話」(2022年8月1日)として、対面で行われたものだ。
後者が「学期末特別講話」と名づけられたのは、学期中に行われる通常の「講義」ではなく、それがなされ、学期末考査が終わった後、通常であれば休みに入るのだが、その前に、「単位」とは関係のない、言うなれば、「遊び」的に参加自由なものとして行われた講義だったからである。
そんなわけで、本書で語られるのは、タイトルに「目的への抵抗」とあるように、「目的」というものに盲目的に縛られるのではなく、それから可能なかぎり「自由」であろうとすることの意味であり、その重要性である。
それが、「学期末講話」の後半でも語られる「遊び」だとか「ゲームのためのゲーム」という表現につながっていく。
「目的」に還元されない、それ自体に価値を有する「生」であることとは、具体的にどのようなことなのか。
そのひとつの形式が、「遊び」や「ゲームのためのゲーム」という形で表現されるし、ヴァルター・ベンヤミンの表現で言うなら、目的に還元されない『純粋な手段』。ジョルジョ・アガンベンの言葉なら『目的なき手段』ということになる。
そしてこれを、私の言葉に言い換えれば、「やりたいからやる」「言いたいことを言う」「好きなものは好きだ(嫌なものは嫌だ)」ということになり、それは、そうしたスタンスに立った「アマチュアリズム(素人主義)」であり「ディレッタンティズム(趣味人主義)」であるとも言えるだろう。

つまり、本書で語られているのは、私としては、なんら「難解」なものではなかったのだが、しかし、これが一般的な読者にとってもそうであったかというと、必ずしもそうではなかったようだ。
例えば、Amazonカスタマーレビューを見てみると、本書に対する批判的なレビューが寄せられており、かつ、それを支持する「参考になった」票が、目立って数多く寄せられている。
これはもしかすると、人気哲学(研究)者ではあるものの、住民運動に参加したりした著者に対し、けっこう多くの「アンチ」たちが存在していて、そういう人たちが否定的な「組織票」を投じたという、よくある(目的論的な)現象なのかもしれない。
だが、本書は講義記録として、少なくとも表面的には「読みやすい」ものであり、私などには、とても「わかりやすい」ものであった。
そんな本書に対する「否定的な意見」が少なくないというのは、もしかすると、本書で語られる言葉が、「一般的」なものとして「読みやすく」、それでいて「理解しにくい」ものだったから、ではないだろうか。
つまり、「哲学趣味」のオタクたちの「権威主義」を、必ずしも満足させてくれない「平易な形式」を採っている上に、その内容が、本質的には「権威主義」を否定するものだったからではなかったか。
どういうことかというと、「権威主義」というのは、おおむね「世間で広く認められ高く評価されているもの」に認められた「権威」への依存であって、「世間で認められてはいないが、その中身のおいて価値があるもの」に権威を認めようとはしないもの、である。
言い換えれば、「権威主義者」というのは、対象の世間的権威(この場合は、哲学という学問)に寄生依存することで、自分も「世間的に認められる(承認されたい)」という、「目的」を持っている人たちなのだ。
ところが、著者・國分功一郎が本書で語っていることとは、まさにそういう「権威主義」などを含む「目的」至上主義への批判だ。
「目的」に従属してばかりいると、その「目的」達成のための、効率的な「手段」までも正当化してしまうために、例えば、ハンナ・アーレントが危惧した「ホロコースト=ユダヤ人問題の最終解決」的なものを呼び寄せてしまうかもしれないよ、という話なのである。

したがって、私たちは、何らかの「目的」のために哲学するのではなく、むしろ「哲学のための哲学」にこそ踏みとどまるべきなのだ、そうでなければ、哲学は「政治の道具としての哲学」といったものに「目的還元」され(頽落させられ)てしまい、本来の哲学とは違った、何か歪んだものになってしまうよ、という警告を、本書は発しているのである。
そんな訳だから、本書を「哲学オタク」が読んだら、「なに言ってるのか、全然わからない」ということになる。
なにしろ、本書で語られているのは、「哲学オタク的な哲学」を否定することなのだから、それは理解できなくて当然。そんなものを理解したら、これまでの「哲学オタク」としての全生涯を否定するにも等しいことになってしまうから、「哲学オタク」が「拒絶反応」を起こしてしまうというのは、むしろ理の当然だったのである。
○ ○ ○
以上の「解説」を読めば、本書に引用されている、アガンベンやアーレントの次のような言葉も、決して「難解ではない」はずだが、いかがだろうか?
(1)
『「生存以外にいかなる価値ももたない社会とはいったい何なのか?」
(ジョルジョ・アガンベン『私たちはどこにいるのか?一一政治としてのエピデミック』』(P14)
(2)
『「目的とはまさに手段を正当化するものであり、それが目的の定義に他ならない」
(ハンナ・アレント『人間の条件』』(P126)
(3)
『 行為は、自由であろうとすれば、一方では動機づけから、しかも他方では予言可能な結果としての意図された目標からも自由でなければならない。行為の一つ一つの局面において動機づけや目的が重要な要因でないというわけではない。それらは行為の個々の局面を規定する要因であるが、こうした要因を超越しうるかぎりでのみ行為は自由なのである(アーレント「自由とは何か」『過去と未来の間一一政治思想への8試論』引田隆也+齋藤純一訳、みすず書房、一九九四年、二〇四ページ[傍点はは引用者]』
(P174〜175、※ 某点部分は、ゴシックに代えた)
(1)は、アガンベンが、コロナ禍で世界的に「緊急事態宣言による行動制限」がなされている真っ最中に発表して、世間からも哲学者の多くからも総スカンを食らい「炎上」した文章の、テーマ部分である。
要は「いくらコロナが流行っているからといって、易々と超法規的な行動制限なんてものを受け入れていて良いのか。生き延びることよりも大切なこと(自由)があるだろう。まったく今の世界は狂っているよ」と、おおむねそういう意味である。

で、世間の「良識的(常識的)な人々」は、アガンベンが「現実の見えていない哲学バカ」だと非難したわけなのだが、國分はここで、アガンベンが言わんとしたところを、おおむね次のように解説している。
「これは、状況依存的な目的に易々とながされてしまう世間に対して、『ちょっと待て、これはもっとよく考えてみるべき、問題含みの事態だぞ』とアガンベンは、世間的な目的合理性から距離をおいた、哲学の言葉を語っているのだ」と。
例えば、ナチスが「ホロコースト=ユダヤ人問題の最終的解決」を選んだのは、「目的合理性」のためであった。
「なんだかんだ言ったって、歴史的な難問であるユダヤ人問題を、本気で解決するつもりなら、ユダヤ人を皆殺しにして抹殺するしかないんだよ。もちろん、乱暴な方法だというのはわかっているけれど、では、他にどんな方法で、本質的な解決がはかれると言うんだ? これまでも、綺麗事の範囲であれこれやってきたけれど、結局はみんな失敗したじゃないか。だから我々は、人類の未来のために、あえて自らの手を汚し、汚名を着ることになってでも、本気で解決しようというんだよ」一一というのが、「ナチスの目的合理性」だったのだ。

しかし、「哲学」はそんなときにも「それは間違っている。仮に、ユダヤ人の存在が西欧社会の不安定要因であったとしても、これまでのいかなる解決方法が失敗してきたとしても、やっぱりナチスのユダヤ人絶滅計画などというのは、人間の在り方として、本質的に誤っている」と、そう言うべきであり、それが「哲学の使命なのだ」ということである。
無論、こうした場合、ナチスの側に立つ人は「そんなに反対をするのなら、対案を出せ」と「ネトウヨ」みたいなことを言うだろうが、哲学者はそこで怯んではならず、堂々と「対案など無いし、それは哲学者の仕事ではない。具体的方策を考えるのは、あなたがた政治家の仕事だよ。哲学者の仕事とは、間違っていることは間違っている、と言うことだ。仮に、それが〝必要なもの〟に見えたとしても、おかしいことはおかしい言い、嫌なことは嫌だと言うことこそが、哲学者の使命なのだ」と、こう反論しなければならない、という話なのだ。
(2)については、上の(1)についての説明で、おおむねご理解いただけよう。
要は、「目的」なんてものは、本質的に「手段を正当化するための、大義名分でしかない」のだ、ということである。
言い換えれば、「手段」から独立した「正しい目的」なんてものは無い。「目的」とは、いつだって「(採りたい)手段」とワンセットになっているものなんだ、ということである。
だから、「目的」だけを見て「目的は正しいのだけれど、手段がちょっとね」みたいな見方は、本質を外しており、現実を見ていない、という意味だ。
(3)については、本書著者による「傍点部分(※ ここではゴシック表記部分)」が、少しわかりにくいだろうから説明しておこう。
『行為の一つ一つの局面において動機づけや目的が重要な要因でないというわけではない。それらは行為の個々の局面を規定する要因である』
この、一見「目的主義」を擁護するかのような言い方が意味しているのは、われわれの行動は、いつでも必ず「目的」を伴わざるを得ないものであり、そのこと自体は、否定することのできない「現実」だ、という意味である。
例えば、「(目的を持たない)遊びのための遊び」をするためには「(目的を持たない)遊びのための遊び」するという「目的」を持たなければならない。私たちは、完全に「無目的」行動することなどできないようにできている、ということだ。
だから、「ユダヤ人問題の解決」という「目的」を持つこと自体が間違っているのではない。「地球温暖化阻止」という「目的」を持つこと自体が、問題なのではないのだ。
『こうした要因を超越しうるかぎりでのみ行為は自由なのである』
というのは、つまり「目的」を持つこと自体は致し方のないことだけれど、それに「縛られてしまう」ことが問題なのだ、ということである。
例えば、「ユダヤ人問題の解決」という目的を持つこと自体は致し方のないことだが、その「結果」に固執した結果として、「皆殺し」という「手段」を正当化してはならない、とか、「地球温暖化阻止」という目的を立てるのは必要なことであろうが、だからと言って「人類を半分に減らしましょう。ひとまず60歳以上の年寄りは、お荷物だから皆殺しにしましょう。残念だが、目的達成のためには、これくらいのことをしなきゃ」というような、「目的」に縛られた行為は間違っている、ということだ。
「目的」という「要因」に完全に縛られてしまうと、そこでの人間はもはや「自由」を持たない。言い換えれば、「目的」を超越することにおいてのみ、人間は「自由」であると言えるのだ、という意味である。
例えば「いくら、人類を半分にしないと全生物が滅ぶとしても、そんな方法は認められないし、そんな選択などしたくない」と言える立場に立つことこそが「自由」ということだ、という意味なのである(「ライザップ」風に言うと、安易に「結果にコミットしない」ということだ)。

つまり、私たちはしばしば、「目的」に呪縛されてしまい、誤った「手段」を選択してしまいがちだが、哲学というのは、そういう「目的合理性」から自由であるための、本質的「思考術」なのだ。
だからこそ、アガンベンの『生存以外にいかなる価値ももたない社会とはいったい何なのか?』という問題提起は、優れて「哲学的」なものであり、そのために「反世俗的」であったからこそ炎上してしまった、ということである。したがって、無論「これでいいのだ」。
誰もが「世俗的」に「合理的」であったればこそ、多くのドイツ人は「ホロコースト」を「やむを得ない手段」として、黙認選択してしまったのである。
だから、私たちは、仮に「対案」を示すことができなくても、「おかしいと思うことはおかしいと言えなければならない」。それは誰のためでもなく「自分の自由」のためなのである。
仮に、それで人類が滅んだとしても、「正しく生きた」ことは「誤った手段選択において延命する」ことよりも、「私自身において正しい」ということだ。
もちろん、アーレントが言うように、私たちは「生存のための目的」から自由になることはできない。しかし、アガンベンも言うとおり、ただ生き残れば良いというものでもないのである。
じつに平たい言い方になってしまうけれども、私たちは「中身は別にして、とにかく長生きするために生きている」というわけではない。
私たちは、「より良く生きる」ために生きているのであり、それは同時に「より良く生きる」ためには「より良く死ぬ」ことだって、決して否定してはならない、ということであろう。
例えば、目の前のいる「無実の人」を殺さなければ、自分が死ななければならないとした場合、自分の死を選ぶことの方が、よほど「正しい」のであり、何より「自由」な選択である、ということなのである。
だが、多くの人たちは「目的」に呪縛されている。「世間ウケの良い選択」を、正しいものと思い込んでいる。だから、本書がわかりにくいのだ。
だが、そういう世俗的な「優等生」の成れの果てが、アドルフ・アイヒマン(凡庸な悪)であるということを、私たちは決して忘れてはならないのである。

(2023年6月2日)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
