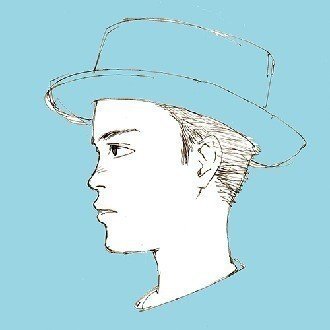#ショートストーリー
N氏とO氏、ホームにて【掌編小説】
夜。地下鉄のプラットフォーム。
時刻は午後の十一時をまわっていて、ひと気がない。
スーツを着た四十代のサラリーマンN氏とO氏が、お互いに顔を見合わせて驚く。
N氏「あー、どうも」
O氏「あー、どうもどうも」
N氏「お久しぶりです」
O氏「こちらこそ、お久しぶりです」
N氏「何年ぶりになりますか?」
O氏「五年ぶり……くらいですか?」
N氏「え? そんなに経ちますか?」
O氏「あ
故郷に海ができる【掌編小説】
あなたゴルフする? あたしはしない。でも穴のことなら分かる。ほらグリーンに空いているまあるい穴。あれって不思議な大きさよね。大きすぎもせず、小さすぎもせず。他の何にも似ていない穴。すごく的確な空洞。
パパが開けた穴もちょうどそれと同じくらいの大きさの穴だった。
園芸用のスコップを持っていきなり庭の畑を掘り始めたの。畑っていっても趣味(というかパパの暇つぶし)の家庭菜園用だから、全然猫の額みた
悪魔【掌編小説】
悪魔はレンブラントの肖像画に出てくるような立派な身なりをしていた。
まるで中世の昔からそこにいるようだった。
イタリアの小さな村の十字路に、何百年も立ち続けているのだろうか。
村人達は悪魔を一瞥もせずに目の前を通り過ぎていく。
ただ一人、村の画家だけが悪魔の姿を認め、それを絵に描いた。
絵を見た村人達はその不吉さにおののき、画家の首を撥ねた。
悪魔は今でも村の十字路に立っている。
大晦日の夜【掌編小説】
大晦日の夜。
こたつに大人達が集まって年を越そうとしている。
まだ子供だった、兄、私、弟は、除夜の鐘を聞こうと意気込んでいたものの、早々に寝床で布団をかぶってしまった。
眠い目をこすりながら小便に立った私は、障子の向こうで親戚の誰かが父と母にこう言ったのを聞いた。
「子供の内で、誰が一番かわいいか?」
父は田舎のオヤジらしく「長男だ」と言った。
母は優しい声で「やはり末の子がかわいい」
部屋の写真【掌編小説】
彼の部屋にはおびただしい数の写真が貼られている。
本当におびただしい数だ。
貼られているというより、幾重にもかさなった写真の下に壁が塗り込められている、と言ったほうがいい。
彼は写真家を目指しているのだ。
彼には大きな情熱があった。
しかし、その情熱の器の中に才能は満たされてはいなかった。
それでも彼は毎日写真を撮って部屋に貼り続けた。
何十年かが経った。
彼は写真家にはなれなかった
ポラロイド【掌編小説】
ベッドの上にはまだ男の跡が残っていた。シーツの皺や、汗の湿り気が朝方までここにいた男の存在を示していた。起き上がって下着を身につけ、窓から無遠慮に入ってくる夏の光線を鈍い頭でずっと見ていた。
床には憶えの無いポラロイドカメラが転がっていた。きっと男が忘れていったのだった。手に取ってシャッターを切るとフラッシュが焚かれた。薄暗い部屋が写真一枚分の時間、白くなった。吐き出されたフィルムに、昨夜の名
ペンギンの夢【掌編小説】
眠りに落ちると私はまた夢の中でペンギンに生まれ変わっていた。
南氷洋の水は密度の濃い碧色で、分厚い雲のような氷の下を私は仲間達と泳ぐのだ。
ペンギンは悩める哲学者である。
その悩みとは詰まるところ「鳥であるのに飛べない」という一言に尽きる。
ペンギンたちはそのアイディンティティの欠如、コンプレックスと向き合う煩悶、絶望と希望の輪廻に身をシロクロさせながら、氷の海を泳ぎ続けるのである。
実
札束イグザミネーション【掌編小説】
栄えある我がW大学探検部に入部するにはひとつの試験がある。
その年の活動費、すなわち探検部総勢30余名が身を粉にして働き、貯めた、探検の支度金。およそ600万を学内の部室から部長宅まで運び届けるのである。
その役には入部希望の新入生(探検の「た」の字も知らない18、9の青瓢箪達)が当てられる。
無論、かつてこの私もその試験をくぐり抜けてきた者だ。
小さな頃から怖い物知らずで通して来た私は、60
西荻窪の森【掌編小説】
そもそもの始まりは幼稚園児の持っていたどんぐりだった。
どこかの遠足で持ち帰ってきた木の実が、小さな手のひらからこぼれ、街中の公園にぽとりと落ちた。
百年経って森が出来た。
東京23区の西の端の杉並区のそのまた端に大きなケヤキの森。
それは公園の範囲を超えて、住宅地を飲み込んでいった。
恐るべきスピード。毎日毎日、新しい木が地面から生えてくる。
アスファルトを破ったり、家を持ち上げたり
マウンドの陽炎【掌編小説】
僕がその男を見つけたのは町外れの草野球場だった。
野球場といっても、そこはもう随分と前に現役を引退したグラウンドで、雑草に覆われたダイアモンドには申し訳程度にホームベースが置いてあるだけだった。夏の盛りの今は雑草も伸び放題で、ただの野っ原と変わらない有様だった。
男は本来ならピッチャーマウンドのある辺りに立って、ホームベースではなく、ライト方向を眺めていた。その先に特に何があるわけでもな
『故郷に海ができる』序【掌編小説】
あなたゴルフする? あたしはしない。でも穴のことなら分かる。ほらグリーンに空いているまあるい穴。あれって不思議な大きさよね。大きすぎもせず、小さすぎもせず。他の何にも似ていない穴。すごく的確な空洞。
パパが開けた穴もちょうどそれと同じくらいの大きさの穴だった。園芸用のスコップを持っていきなり庭の畑を掘り始めたの。畑っていっても趣味(というかパパの暇つぶし)の家庭菜園用だから、ぜんぜん猫の額み
アジサイは自分がいつから「アジサイ」と呼ばれるようになったのか、思い出そうとしていた。【掌編小説】
アジサイは自分がいつから「アジサイ」と呼ばれるようになったのか、思い出そうとしていた。糸を引くような六月の雨は今日も街を濡らしている。もっとも、アジサイにとっては雨降り以外の天候など存在しないのだが。
Chronic rainy syndrome。慢性雨降り症候群と呼ばれる、生きているかぎり雨に降られ続ける病。主治医が真っ白なカルテにその病名を書き込んだ日から、少女の名前は「アジサイ」になっ
クリスマスでもハロウィンでもないけれど【掌編小説】
兄ちゃん久しぶり。山の冬は長いよ。長いけど作業所の中は石油ストーブを焚いているから暖かいよ。今まであまり言わなかったけど、俺は石油の匂いが好きなんだ。
ホームで暮らしていると刺激はないけど、心が落ち着いていられるからいいよ。風邪? 引いてないよ。発作も起こしていないし、体はすこぶる順調だね。
そうそう、このあいだ知らない人がホームに来たんだ。五十代くらいの男の人で、あまり顔色が良くなかっ