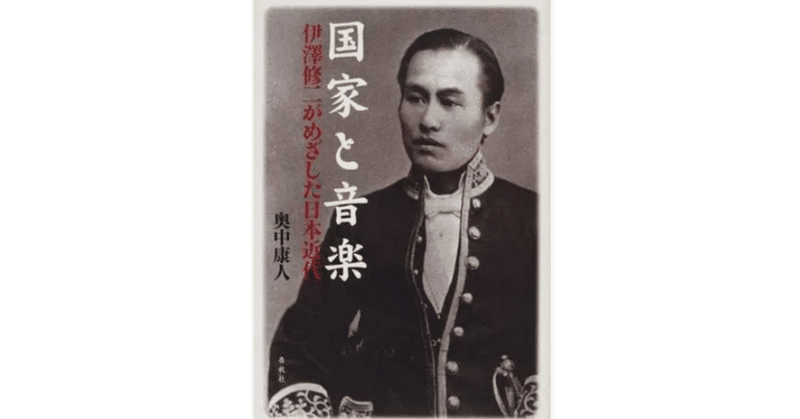
明治政府の西洋音楽導入施策(唱歌教育)におけるキーパーソン・伊澤修二を探る
当noteでは約2年前から記事を書き始め、音楽のジャンルや価値観の違いに関する疑問を出発点とし、クラシック音楽史と各ポピュラー音楽史を並列で論じていくことを大きな指針として記事を投稿してきました。
メタ音楽史のシリーズや、分野別音楽史のシリーズで、従来バラバラに存在していた各音楽史の系譜を並べて書くという目標はひとまず達成でき、その系譜を詰め込んだ音楽史図表も多くの方に見ていただけました。
が、これだけでまだゴールではありません。上記の系譜はすべて「西洋音楽史」であり、日本人として重要な「日本音楽史」が全く入っていません。
日本音楽史もまた、西洋音楽史と同じ分断の構図が起こっています。つまり、
「クラシック音楽史を調べていってもジョン・ケージらの『現代音楽』で終わってしまい、ロックやヒップホップなどの『現代の音楽』にたどりつかない」(この文の意味がわからない人は過去の記事を読んでください)
のと同じように、
「日本音楽史を調べていっても、武満徹らの『現代邦楽』で終わってしまい、Jpopや邦ロックなどの『現代の日本の音楽』にたどりつかない」
のです。
そのため、現在筆者は日本の音楽に関する各系譜についてそれぞれ絶賛勉強中で、様々な書籍を地道に読み進めているのですが、今回は、読んでいて特に「日本の音楽を考えるにあたって重要な内容だ」と感じた、こちらの本の内容を紹介していきたいと思います。
「国家と音楽 ~伊澤修二がめざした日本近代~」(奥中康人 著)
こちらは、明治期の日本の西洋音楽導入にあたって大きな役割を果たした「伊澤修二」を中心として、当時の状況を研究した書籍です。
伊澤修二は東京音楽学校(現・東京藝術大学)の初代校長であり、その前身となる音楽取調掛からその長を務めた人物です。彼の経歴を追い、その時代の時代潮流を知ることで、当時の音楽教育のありようを綿密に解析する、新しい洋楽受容史となっています。
【第一章】
鼓手としての伊澤修二 ~明治維新とドラムのリズム
現在の日本には西洋音楽が満ち溢れています。それは、クラシックだけではなくジャズ、ロック、ポップス・歌謡曲はもちろん、「日本の心」と形容されることも多い演歌ですら、西洋音楽が基礎になっています。
日本における西洋音楽の始まりは、幕末の鼓笛隊からでした。一般には明治政府の欧化政策によって西洋音楽文化の受容に影響したとされがちですが、その前に黒船来航によって各地に鼓笛隊が誕生していたのです。伊澤修二も少年時代、信州の高遠藩での鼓笛隊において、鼓手を務めていました。伊澤はドラミングを完璧に習得しており、優秀な鼓手だったそうです。
欧米列強が開国を迫った1850年代になって、日本は国防のために西洋式の軍隊を整備する必要性に気が付きます。軍艦や大砲、小銃などのいわゆる「ハードウェア」は、購入して揃えれば済む話でした。しかし、手に入れたものはそう簡単に操作できるようなものではありません。
大きな軍艦は大勢の人々がそれぞれの持ち場で自分の役割を果たすチームワークが求められ、大砲や小銃も撃つまでにいくつもの複雑な手順を正確にこなさなければなりませんでした。何より、小銃を持った歩兵たちがそれぞれバラバラに戦うようでは全く意味がなく、銃隊を編成し、号令によって組織的に行動してこそ効力が発揮されます。このような人間の動き方、すなわち「ソフトウェア」というべき側面をも西洋式に更新しなければならなかったのです。
秩序や規律のある集団行動を円滑に行うためのトレーニングの基礎が行進訓練であり、これにスネアドラムが用いられたのでした。珍しい異国の音楽を楽しもうとして西洋楽器が導入されたわけではなく、軍楽隊を率いた欧米の強烈な軍事力に直面し、対等に交渉して生き残るために同じ軍事力を備える必要に迫られ、そのトレーニングのためのドラムや鼓笛隊の制度も採り入れなければならなかったのです。
さらに、行進(ドラムマーチ)に加え、命令を伝達する合図(ドラムコール)としてもスネアドラムが用いられたのでした(進軍・静止・点火・右ヘ向ケ・集合・円陣・退軍など)。ドラムの音が自分たちの命と直結しており、まさに「No Music, No Life」というべき状況でした。こうして調練ドラムが採用され、スネアドラムと横笛を携えた折衷式の「幕末鼓笛隊」が誕生します。
当初は国防のために採り入れた西洋式軍隊・軍楽ですが、戊辰戦争という内戦でも用いられることとなり、伝統的な武士の戦い方が中心の旧幕府軍に対し、西洋式の集団行動を身に着けた新政府側が勝利したのでした。
さて、この時期、領民を軍事組織に取り込もうとする動きは全国的に見られましたが、領民の立場からすると貴重な労働力を兵隊として取られて困惑することでした。日々の暮らしに直結する一揆などならまだしも、戊辰戦争については「何のために戦うのか」という明確な目的意識を持ちえませんでした。自分の年貢や利権に関係するのであればともかく、幕府と諸藩の政治力学や欧米列強の国際関係について思いを巡らせるのは困難だったのです。
長崎に滞在していたカッテンディーケは、日本人が「太鼓や歩兵の調練に大変熱心」であるにもかかわらず、「祖国防衛のために力を合わせる義務意識が薄い」と考察していました。長崎の一商人に「長崎が脅かされたときに町を防衛できるのか」と尋ねると、「そんなことは我々の知ったことでは無い。それは幕府のやることだ」と答えたといいます。
和太鼓と異なる西洋のドラミングで身体を訓練するだけでは充分ではなく、人民をどのようにして国政に参画させるのか、という課題が明治新政府に持ち越され、そこで西洋音楽のさらなる根本的な導入が必要となっていったのです。
伊澤の鼓手経験は一般に「少年時代の1エピソード」として軽く触れられるだけにとどまり、「音楽取調掛の創設で西洋音楽を導入するアイデアのきっかけとなった」という程度に結び付けられるのみですが、これでは短絡的すぎます。
西洋式のドラムは芸術としてではなく「近代的な身体」のために導入されたものであり、そのさらなる課題として「国民教育」を考えるにあたり、伊澤や明治新政府らは「西洋音楽」を意識せざるをえなくなっていったのでした。
【第二章】
岩倉使節団が聴いた西洋音楽 ~ナショナリズムを誘発する合唱
欧米諸国との不平等条約改正の予備交渉や、各国の文物視察・調査・親善交流などを目的として、1871年に岩倉使節団が出港しました。報告書『特命全権大使米欧回覧実記』に記録が残っていて、使節団は訪問先の欧米諸国でさまざまな西洋音楽を聴いたことがわかっています。
この『回覧実記』はさまざまな研究者から注目されているそうですが、残念ながら音楽史の研究者がもっている興味に応えてくれるような文献ではない、と、従来考えられていました。岩倉使節団らの見識不足によって、偏向的で情報の不十分な記録であるとされていたのです。しかし、その評価は芸術至上的な音楽学の視点から見たものではないか、と指摘します。
『回覧実記』には外交儀礼時の音楽の記録が最も多く、次いで学校の音楽や軍隊の音楽についても散見されます。たしかに断片的で、楽器などについて詳しく観察されておらず、芸術的観点から見るとおもしろくないでしょう。しかし、ここで問題にすべきなのは情報量や知識の多少ではなく、明治初期当時の人々(少なくとも明治政府中枢)にとっての「音楽」の捉え方自体についてです。
それを考えるにあたって、ボストンでの「太平楽会」というコンサートの記録が注目されます。
このコンサートは「World's Peace Jubilee and International Musical Festival」のことで、アメリカの南北戦争とヨーロッパの普仏戦争が終結したことを祝う大規模な平和記念コンサートでした。当時のプログラムなどの別の資料を見ると演奏曲としてバッハやベートーヴェンが含まれていたことがわかっており、さらにヨハン・シュトラウス本人が舞台に登場してオーケストラを指揮したこともわかっています。しかし、『回覧実記』にはそのことに触れられていません。一方で、軍楽隊の演奏に盛り上がる聴衆のようすや、アンコールでの聴衆の熱狂的な反応には感動し、その「愛国心」に想いを馳せているのです。
このようなレポートに対して音楽学者は頭を抱え、「この地点では日本人の知識が乏しく音楽教養が稚拙だったため、"正しく" 鑑賞することができなかったのだ」というように解釈されてきました。
しかし、岩倉使節団の調査能力の高さは優秀であり、ベートーヴェンやヨハンシュトラウスの名声を知らない知識不足とは考えづらいのです。記録にはオーケストラや合唱団の人数、ホールのキャパシティや予算、出演者のギャラまで記されています。つまり、彼らは「取捨選択」をして、大作曲家について書き残さなかったのです。現在の我々の常識ではそれが「当時の限界」のように見えますが、それは現在の常識が勝手に設けた固定観念です。
そもそもこのコンサートが客観的にみて芸術的な場であったのかも疑わしく、当時としても異例といえるほどの大規模なものであったため音響面も芳しくなく、純粋な音楽的感興を期待できたかどうか疑わしい、という中で、日本人らが感動したのは「数万人単位の人々がある音楽に対して熱狂的に拍手を送り、あるいはみんなで一斉に同じ歌を歌う」という現象そのものになったのではないか、ということがいえるのです。
南北戦争終結からまだ数年。平和記念祭だからこそ、南北を音楽で包み込む一体感を必要としていたのかもしれません。ギルモアやフォスターなど、あるいはヤンキードゥードゥルや星条旗などの愛国歌がアンコールで大合唱され、聴衆の愛国心を誘発していたということは十分考えられ、岩倉使節団らはそれを敏感に察知していたのです。
そうなると、岩倉使節団が「アメリカの聴衆の愛国心に感銘を受けた」というのは、日本人の音楽知識の低さによる勘違いなどではなく、むしろ、非常に正確な理解だったのだといえるのです。
そして、そのような大合唱や愛国的熱狂のために、西洋音楽教育が必要であることも、理解したのでした。
【第三章】
洋学と洋楽 ~唱歌による社会形成
伊澤修二は少年時代から優れた頭脳を持っており、幼少より読書をし、学問に親しんでいました。その頭脳を以てして数多くのドラムコールや長いドラムマーチを暗記し、幕末鼓笛隊の鼓手を務めることができました。そして、明治維新後の伊澤はもっぱら西洋の学問を勉強することになります。
1869年(明治2年)、明治政府は東京に大学を設立し、それまでの各学問所を弾き継ぐように大学を3つに分けました。しかしまだ廃藩置県が行われておらず、各藩でも洋学教育が行われており、人材が地方に分散していたため、1870年(明治3年)、新政府は諸藩の規模に応じて1~3人の人材を政府に貢進するように命じます。これを貢進生制度といい、彼らは大学南校で学ぶこととなりました。頭脳の中央集権化で、伊澤も高遠藩から選ばれた一人でした。
1872年(明治5年)の「学制」による改組の折には、伊澤はその幹事に選ばれるなど、まさにエリートコースであり、しかも徹底的に洋式の教育を受けた近代国家の官僚に相応しい有望株でした。この「学制」から国による教育が本格的に開始され、音楽は「唱歌」という名前で教科が制定されましたが、内容が決まらず教える教員もいないため「当分之ヲ欠ク」として実施されませんでした。
1873年(明治6年)伊澤は「『ゼ・チヤイルド』といふ書」に出会います。これは、マチルダ・H・クリーゲの「The Child, Its Nature and Relations」という、フレーベル主義の幼稚園教育に関する書で、ここで伊澤は教育に強い関心を持ち始めました。
フレーベル主義とは、幼児教育の父と呼ばれ、世界で初めて幼稚園を創設したドイツの教育者・フリードリヒ・フレーベル(1782-1852)が提唱した教育方法で、現在の日本での幼稚園教育もフレーベル教育が基本となっています。フレーベルは、幼児期の「遊び」によって「生きるために必要なさまざまな能力」が身につくと考え、歌遊びや運動遊びを重視しました。
この時期、アメリカにおいても幼稚園教育は黎明期であり、伊澤は同時代の洋書・資料を通読し、熟知していきました。そして伊澤はある報告書において「唱歌は精神に、運動は身体に効用があり、唱歌教育が運動とともに重要である」と記し、伊澤の唱歌教育に関する考えの初出がみられます。その根拠はフレーベル主義の主張と見受けられます。
このような音楽観は音楽を自律した芸術だと考える立場からは否定的に扱われますが、伊澤が何か検討違いをしていたわけでは無く、同時代のアメリカにおいても音楽効用論は先進の常識として真面目に議論されていました。
フレーベルは子供に親しみやすい俗謡や子守唄を用いた唱歌遊戯を通じて道徳教育を目指したことを伊澤は深いレベルで理解し、フレーベル主義の教育書にある西洋の歌曲をそのまま使うのではなく「本邦固有ノ童謡ヲ折衷シテ」、伊澤はこの段階で唱歌遊戯を試作しています。
現在の芸術音楽家が考えるような音楽そのものを教える科目としての音楽教育ではなく、フレーベル主義に基づいた、全人形成・人間教育という目的のための手段として音楽に注目があたっていったのでした。このような発想は、伊澤の独善的(独創的)な思い付きではなく、当時のお雇い外国人が持ち込んだアメリカ教育界や西洋の教育論の主流の考え方を摂取した結果だということがいえるのです。
伊澤は、さらにより詳しい現地調査のため、1875年(明治8年)、アメリカへ留学に行きます。
【第四章】
国語と音楽 ~文明の「声」の獲得
留学先で伊澤が受けた教科の中に「Vocal Music(唱歌)」という科目も並んでいました。エリートの伊澤は、ほとんどの科目について「さほどの困難無しに修業」できたとされていますが、その中で唱歌だけがうまく出来ませんでした。
校長は唱歌を免除してやろうと提案しています。そもそも唱歌は必修科目ではなかったので、それほど重要な科目ではなく、校長の提案を受け入れても良かったはずなのですが、それでも伊澤は唱歌の習得にこだわりました。それは、渡米前の伊澤がフレーベル主義の教育思想を充分に吸収し、児童教育における唱歌の役割の大きさを認識していたからで、唱歌はどうでもいい科目ではありませんでした。また、実は政府上層部から音楽を履修するよう指令があったからではないかという説もあります。
留学したばかりの1875年秋、伊澤はボストンの小学校を見学し、フレーベル流の教育の実践を確認しました。伊澤はここで初めてアメリカの教育実践に接して驚いたのではなく、欧米の教育書によって予習済みだった知識を再確認して感心したのです。唱歌に対するこのような正確な理解があったからこそ、彼にとって唱歌ができないことは深刻な問題でした。
さて、幕末鼓笛隊では優秀な鼓手だった伊澤は、漠然と「音楽が苦手」だったのでは決してなく、「音階を歌うこと」が出来なかったのでした。「ド、レ」くらいであれば大丈夫だが、「ミ、ファ」になると音が上ずり、まともに音程を取ることが出来なかったといいます。
校長は「西洋の音階は日本の音階と異なっているから、その習得が難しいのも当然のことだ」と同情の言葉をかけており、音階の差異が認識されていたことがわかります。
ここで、この時代、欧米の「文明」社会と、それ以外の「未開な」社会が比較される文脈における「音階」にはデリケートな意味が含まれていました。
「欧米で使われる音階は7つの音で構成される一方で、日本・中国・インドなどの未発達なアジアの音階は5つの音符しかない。第4音、第7音の抜け落ちた不完全な音階でつくられたハーモニーは、洗練された耳には大変不快な結果をもたらす。音楽が国民性や国民の文明化の度合いを指し示していることを考えれば、音階の西洋化は大変な偉業である。」というボストンの記事まで見つかっています。
つまり、当時公教育における音楽とは社会形成の手段であり、到達すべき目標が「近代文明社会」である中で、音階はその社会の「文明化の度合い」を表していました。科学的計算によって導かれた12平均律による「完全な」7音の音階に対し、5音音階は2つも音が欠けている未開・発展途上の表象だったのです。
下層階級の子どもや幼児・生徒ですら「完全」な西洋音階を用いて歌うことが出来ることに対し、伊澤ら日本人はその「教育水準の高さ」として感嘆したのです。
文明の尺度として音階をとらえることは、それぞれの音楽文化に固有の特徴として尊重し合う現在の文化相対主義からすると容認されない考え方ですが、当時の西洋中心社会では常識だったのでした。
唱歌に苦戦していた伊澤はメーソンに教えを乞い、西洋音階を習得することに成功します。伊澤は、唱歌教育の重要性を熟知してアメリカに渡り、声の出せない音程に気が付き、それをトレーニングによって克服したのです。この経験が、帰国後のメーソンとの教材開発に繋がり、日本の唱歌教育における初の教科書『小学唱歌集』につながります。
さて、伊澤は英語の発音にも苦戦していて、グレアム・ベルに発音の矯正を求めました。ベルは現在では電話の発明家として有名ですが、当時は言語障害者に発声・発話を教える教師として知られていました。父親のメルヴィル・ベルの開発した「視話法」が有名で、グレアム・ベルはそれを引き継いだ音声生理学のスペシャリストだったのです。
伊澤はベルによる視話法によって英語の発音を克服しましたが、日本に帰国してからの伊澤はこのメソッドを応用して日本語の発音(方言の矯正)や台湾における言語教育に用いたのです。
近年指摘されているとおり、江戸時代まで日本語は決してひとつではなく、地域的・階層的差異がありました。もっとも江戸時代の多くの人々は行動範囲が狭い社会の中で生活をしていたため言語の不自由さは深刻では無かったのですが、明治になって廃藩置県や四民平等によって自由な移動が可能となったときに、国民の話し言葉をどうするかは重要課題として浮上します。
近代国家の教育は、国語をひとつの言語文化に統一して国民が意思疎通できるようにしなければなりませんでした。地方やマイノリティの言語文化の存在を蔑視して「標準語」を設定する言語改革は一見するとかなり強引な中央集権的文化政策のようですが、国民が自分の意見を表明したり、他人の意見を聞いたりする基礎能力は民主主義の根幹にかかわる問題であり、むしろ言語マイノリティーが不利益を被らないようにするための啓蒙運動だと考えられていました。
加えて、ベルの視話法が音声生理学に基づくフィジカル・トレーニングであることを考えると、メーソンの音階練習との共通性が明瞭になってきます。
つまり、正確に発音できなかった母音・子音を自在に出せるようにすることと、7音の音高すべてを獲得することは全く同じで、これこそが「Vocal Culture」という分野だったのです。「国語」と「音楽」という別々の科目に見えるものですが、同じ「声のコントロール法」の矯正教育として、文明社会の国民間コミュニケーションに必須の能力だと考えられたのです。
伊澤が諸学問を学んだ当時は、1859年に出版されたダーウィンの『種の起源』による進化論が知識人のあいだで一大ブームとなっていました。伊澤はとりわけ地質学、古生物学、植物学などに興味を深めたようですが、これらはすべて進化論を理論的根拠として関連する分野であり、伊澤は自然科学への傾倒というよりも進化論思想への傾倒を深めたといえます。これは他の留学生にも共通していました。進化論という理学思想は当時の知識人であれば身に着けておかなければならない基本原理でした。
その意味で、伊澤がアメリカ留学中に音楽を学んだのも、進化論に基づいた科学的研究だったのでした。日本人には特定の音や特定のピッチがうまく出せないことを確認し、それは近代教育を受けていない日本人の発声器官が西洋人に比べて野蛮で未発達だからだと考えたのです。
洗練された話し言葉を持ち、あるいは歌うことのできる欧米国民のように、日本人が文明的な声を持つためには、その身体能力の差を解消することによって可能となると考え、音声器官の改良・矯正のために有効な方法として学んだのが、ベルの視話法やメーソンの唱歌教授法だったのでした。
伊澤は文明国のアメリカの国語(=英語)を日本に移植しようなどとはまったく考えておらず、言語障害者への啓蒙活動や地方の方言矯正によって日本語を改良すれば、「標準語」により国内コミュニケーションが円滑に行われるようになると信じていました。視話法が英語普及のための道具では無かったように、メーソンの唱歌教授のメソッドも、必ずしも「西洋音楽普及」のための道具ではなく、日本人の声の文化を均質化して、全国民が同じ音階で声を合わせて歌うためのメソッドだったといえます。
構音器官の仕組みを科学的にトレーニングすることによって、より進歩した文明社会にふさわしい音声を獲得し、文明国のスタンダードに並ぼうとしていたのです。
【第五章】
徳育教育と唱歌 ~伊澤修二の近代化構想
1878年(明治11年)、アメリカから帰国した伊澤には、多岐にわたる教育行政の仕事が待ち受けていました。その中に、一般的に知られている西洋音楽導入の業務も含まれるのですが、従来の伊澤修二研究においては、伊澤の人物像は曖昧なものになってしまうという問題がありました。
伊澤の西洋音楽の普及や音楽教育の活動を、文明開化・欧化主義と結びつけて肯定的に評価しようとする研究においては「開明派」の側面を強調する傾向が強く、伊澤の国家主義的な活動についてはほとんど言及されません。逆に明治時代から敗戦時までの音楽教育のあり方、特に天皇制に結びついた封建主義的な音楽教育を否定的に見ようとする時には、伊澤の国家主義的な側面を格好の攻撃材料として批判する傾向があり、従来の「伊澤修二研究」は二分されており落ち着きが悪いのだそうです。
この矛盾を解消する説明として通常、先進的な西洋芸術の導入を「従来」目指していたのに、明治10年代に政府や文部省の政策が保守に転じたために、「徳育教育」として音楽が政治利用され、唱歌教育が国家主義的でおかしな方向に進んでしまった。というストーリーが語られます。
しかし、伊澤のアメリカ教育思想の受容や「唱歌遊戯」の試行、アメリカ留学で学んだ音声トレーニングとしての唱歌など、「国民教育」という目標に集約される唱歌の構想を考えると、「保守への転向と政治利用に振り回された」という捉え方をする必要はないといえそうです。
前時代への逆走として封建的な徳育思想に後退したように見えても、それは近代教育思想によくみられる三育(智育・体育・徳育)のひとつとして矛盾なく接合できる「徳育唱歌による近代化」である、という伊澤の構想が理解できるはずです。
「芸術」は二の次で、「教育」のツールとして音楽を用い、天皇崇拝の国家主義教育に利用するというありかたが、さも伊澤や明治政府の暴挙のようにとらえてしまうことは、現代の音楽学者の勝手な期待と誤解であり、近代化・啓蒙のための教育として音楽が必要とされていた、という社会的文脈を考慮しなければなりません。
日本で芸術という観念が一般に定着するのは明治時代末になってからのことであり、しかもそれは徳育教育などの教育思想と両立するものとして成立したのでした。
以上がこの書籍の内容になります。日本音楽史において西洋音楽導入を考える上で、非常に重要な示唆を与えてくれる内容ではないでしょうか。
より詳しい引用資料や議論を読みたい方は是非書籍本文を読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

![音楽史note[JUN]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/138783555/profile_c84af2a23c59f9583876f3c8dba39814.png?width=60)