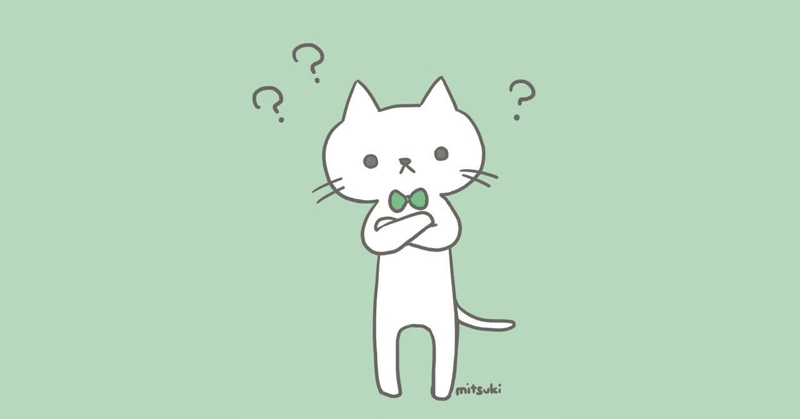
「強迫性障害」ってなに?
俳優の佐藤二朗さんが公表したことにより、昨今メディアなどでも取り上げられ始めている「強迫性障害」。
徐々に世の中にも「強迫性障害」という言葉が浸透され始めている部分もあるかと思います。
しかしながら、まだまだ認知度は低く、その実態もいまいち掴みづらいところもあるかと思ったので、そもそも「強迫性障害とは一体どういうものなのか?」一般的に言われていることについて、元当事者である「りん」の視点も交えつつ、出来る限り分かりやすく説明していきたいと思います。
強迫性障害について既に知っているという方も、あまりよく分かっていないという方もぜひご覧くださいませ。
①「強迫性障害」とは何か?
⑴簡単に一言で表すとどうなる?
「過度なこだわりによって、日常生活に支障が出てしまう病気」のことを言う。
⑵別の呼び方はあるの?
「強迫性障害」は英語では「Obsessive-Compulsive Disorder」と表記され、「OCD」と略称されることから、強迫性障害のことを「OCD」と呼ぶ場合もある。
⑶発症する時期とその割合
主に思春期、成人初期の10代〜20代に発症しやすく、100人に3人ほどの割合で発症すると言われている。
→この数字は心療内科などで診断された、国が認知している数だと思うので、実際はそれ以上にいると思われる。
⑷発症原因
本人の気質や生まれ育った環境、生理学的な要因(脳の神経物質など)が強迫性障害の発症に影響を与えているのではないかと一般的に考えられているが、それらはあくまでも仮説段階であって、現在もはっきりとした原因は分かっていない。
⑸WHO(世界保健機関)の強迫性障害に対する認識
強迫性障害は、WHO(世界保健機関)※によって「経済損失および生活の質の低下に影響する10大疾患」の一つとされている。
それほど、強迫性障害による苦痛や支障は大きいものとの認識がされている。
※WHO→世界保健機関(World Health Organization)のこと。
すべての人々の健康を増進し保護するために、互いに他の国々と協力する目的で設立された。
WHOにおける健康の定義は、病気の有無ではなく、肉体的、精神的、社会的に満たされた状態にあることを掲げる。
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることが基本的人権であると謳う。
⑹成り立ち(強迫観念と強迫行為)
強迫性障害の症状は、主に「強迫観念」と「強迫行為」から成り立って生まれる。
【強迫観念】
→自分の意志とは反して、頭に浮かんでしまう考えのこと。
自分でも「合理的ではない」と分かっていても、なかなか払いのけることのできない考えのこと。
〈元当事者からの一言〉
→これの何が苦しいかというと、ずっとぐるぐるそのことばかり考えてしまって、他の物事に何も手をつけられなくなってしまうことですね。
【強迫行為】
→自分でも「やりすぎ」「無意味」なことだと分かっていても、「強迫観念」によってやらずにはいられなくなる行為のこと。
〈元当事者からの一言〉
→“やりたくないのにやらずにはいられない”
それをやることは不本意なのに、やらないと不安で何度も何度もやってしまう。やればやるほど、どんどん不安は膨れ上がっていく。この負のループってめちゃくちゃきついんですよね。
②症状の種類
前項に記載した「強迫観念」や「強迫行為」は、絡まり合いながら様々な症状となって現れるため、人によって症状の状態は多岐にわたる。
しかしながら、以下では代表的な症状の種類について紹介したい。
⑴不潔恐怖
汚れや菌などを過剰に恐れてしまうこと。
〈元当事者から一言〉
→例えば、何度も手を洗ってしまったり、ドアノブや手すりなど「汚い」と感じてしまったものは触れなくなってしまったりする。
様々な「不潔」なものに恐怖を抱き、身の危険を感じて避けていくことが増えていき、だんだんと行動が制限されていく。
⑵加害恐怖
「誰かに/何かに危害を加えたかもしれない」と不安になってしまうこと。
〈元当事者からの一言〉
→例えば、車や自転車で「人」「物」をひいてしまっていないか、何度もその場に戻って確認してしまったり、事件や事故として、テレビなどに自分が出ていないか確認してしまったりする。恐怖のあまり、行動も制限されてしまい、行動しなければいけない時は半端ないストレスや恐怖を抱える。
⑶確認行為
それが「本当に出来ているかどうか」不安でたまらなくなり、何度も確認せずにはいられなくなること。
〈元当事者から一言〉
→例えば、「戸締まり」「ガス栓」「電気のスイッチ」などを何度も確認してしまったり、じっと見張ったり、指差し確認や手でさわって確認したりする。何度も何度も繰り返してしまうので、その時間が生活の中心となっていってしまう。
⑷儀式行為
自分で決めた手順で物事を行わないと悪いことが起きてしまうと不安になったり、納得が出来ず気持ち悪くなってしまったりして、毎回同じ手順でやらなければ気が済まなくなること。
〈元当事者から一言〉
→例えば、仕事や家事などに必ず決まった手順があったり、お風呂で体を洗う順番があったりする。
また、それがきっちり守られていないと何度もその手順をやり直したりしてしまう。
⑸数字へのこだわり
不吉な数字や幸運な数字に過剰にこだわってしまうこと。
〈元当事者から一言〉
→例えば、「4」や「9」の数字は「死」や「苦」を連想してしまい、不吉なことが起こる気がして、それらの数字は何としてでも避けずにはいられなくなってしまうこともある。
その他、奇数や偶数にこだわったり、歩き方やノックの回数など、納得のいくまでやり直したりする。
⑹物の配置、対称性などへのこだわり
物がきちんと配置されているか、左右対称になっているかこだわってしまうこと。
〈元当事者から一言〉
→例えば、必ず机の決まった位置に、リモコンを並べなくてはいけなかったり、額縁などをしっかりまっすぐ水平に飾られていないと気が済まなくて、何度も手直ししてしまう。
⑺縁起恐怖
神や仏、縁起などによって、「バチが当たるのではないか」「不幸が起きてしまわないか」不安になってしまう考えのこと。
〈元当事者から一言〉
→縁起のいい数字やジンクスなどを過剰に気にし過ぎてしまい、その通りにやらないと「不幸になってしまう」と不安になってしまう。
頭の中で「嫌な」/道徳的に「悪い」イメージが浮かぶと、それだけでも「バチが当たってしまうのではないか」と不安になり、何度もそのイメージを打ち消そうとしてしまう。
③強迫性障害の治療法
一般的な強迫性障害の治療法として、「認知行動療法」と「薬物療法」の二つがあると言われている。
前者は主に心に働きかけ、後者は身体に働きかける役割を担っている。
⑴認知行動療法
「認知行動療法」とは、「認知」(物事の認識)を整えることで、「行動」を変えていくことを目的とする心理療法のひとつになる。
その中でも強迫性障害の治療法として代表的なものとして「曝露反応妨害法」がある。
この「曝露反応妨害法」とは、強迫性障害の当事者の方が「強迫観念」による不安に立ち向かい、「強迫行為」をしないで我慢をするという治療法になる。
この治療法を継続していくことで、強迫観念が弱まり、それにより強迫行為をしなくても済むようになることが期待されている。
⑵薬物療法
うつ病などの治療で用いられる抗うつ薬のSSRI(セロトニン再取り込み阻害薬)が主体となって、薬物による治療が行われる。
一般的に、この薬を服用することで感情や気分の安定を促す“セロトニン”と呼ばれる脳内物質が増えることが症状改善につながると考えられている。
④まとめ
強迫性障害は決して珍しい病気ではなく、その症状は日常生活と密接に関わっていること。
だからこそ、症状が悪化すればするほど、「生きているだけでしんどい」といった状態になってしまい、社会生活だけでなく、日常生活を送ることも難しくなってしまう。
しかしながら、現在もその原因ははっきりと分かっておらず、強迫性障害の治療には心理療法と薬物療法で改善していくことが期待されている。
りん
-------------------------------------------------
☆この記事をほんの少しでも気に入って下さったら、「いいね」や「コメント」「フォロー」でお知らせいただけると、とっても嬉しいです☺︎
あなたの一つの行動が、私にとっては大きな創作活動の源です。
いただいた想いは、今後の記事に代えて全力でお返しいたしますm(_ _)m
-------------------------------------------------
「りん」としての活動を続けていくために、より良いものを「あなた」へお届けしていくために、あなたの応援は欠かせません。 いただいた想いは、必ず記事へ還元していきます。💐
